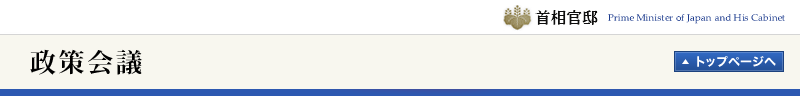検証・評価・企画委員会コンテンツ分野会合(第3回)
議 事 録
日 時:平成28年2月5日(金)15:00~17:10
場 所:中央合同庁舎4号館 1208特別会議室
出席者:
- 【委 員】
-
中村座長、相澤委員、内山委員、岡村委員、奥山委員、
喜連川委員、佐田委員、重村委員、杉村委員、瀬尾委員、
竹宮委員、野坂委員、野間委員、林委員、宮河委員、
森永委員
- 【関係省庁】
- 経済産業省 平井文化情報関連産業課長 総務省 豊嶋情報通信作品振興課長 外務省 渡邉文化交流・海外広報課首席事務官
- 【事務局】
- 横尾局長、増田次長、磯谷次長、田川参事官、永山参事官、廣重企画官、 中野参事官補佐、阿部参事官補佐
- 開会
- コンテンツ海外展開の一層の推進
- 意見交換
- 閉会
○中村座長 では、第3回「検証・評価・企画委員会(コンテンツ分野会合)」を開催いたします。
本日御出席いただいている委員の方は、配られている座席表のとおりです。
では、知財事務局長から御挨拶をいただきます。
横尾局長、お願いいたします。
○横尾局長 また本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年、全体の会合とコンテンツの会合と2回開催させていただいて、「知財推進計画2015」の実施状況についていろいろ御意見をいただきました。その後、一つ御報告ですが、TPPの大筋合意を受けまして、11月末に「知的財産分野におけるTPPへの政策対応について」、知財本部決定をしております。お手元に資料をお配りしておりますが、これが政府全体のTPPの政策大綱に盛り込まれているということでございまして、TPPの国内担保と合わせて、TPPを活用して海外の市場を開拓していくということで、コンテンツもまさにクールジャパンの一つの大きい要素として大変重要な要素になっております。
今年度は今日ともう一回、2回会合を予定しておりますが、昨年の議論、TPPの大綱を踏まえまして、「知財計画2016」に向けた議論をさらに深めていきたいと思っております。検証・評価・企画の「企画」の部分、これからどうしていくかという点により重点を置いて議論を深めていきたいと思っております。
あわせて、もう一つ配付しておりますが、パブリックコメントということで、「知財推進計画2016」に向けた意見募集を、今年は年初にやらせていただいております。いろんな御意見を踏まえて、この委員会の場で検討の題材に具体的にしたいということで、コメントをいただいております。今日は御紹介にとどまりますが、次回の会合で必要に応じ検討状況を御報告して、さらに議論をしたいということで、コンテンツの海外展開、それを支える制作力強化、その他の課題について、さらに議論を深めていきたいと思っておりますので、どうぞ積極的な御意見を頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願いしたいと思います。
○中村座長 よろしくお願いいたします。
本日は、「コンテンツ海外展開の一層の推進」というテーマのもとで議論を行うことにしております。
議事に移る前に、事務局から配付資料の確認をお願いします。
○永山参事官 お手元の資料でございますが、資料1が本日の会議の論点に関する資料、資料2-1から2-3がそれぞれ3省庁からの説明資料。資料2-4が内山委員の説明資料。資料2-5が野間委員の説明資料。これはメーンテーブルのみの配付とさせていただいておりますが、その資料を配らせていただいております。
また、参考資料として、局長のほうから話がございましたように、参考資料のとおり、「知財推進計画2016」の作成に向けて意見募集をした結果、団体企業からコンテンツ分野についていただいた意見につきまして、それぞれ1から6、「知財推進計画2015」の柱立てに沿って分類をさせていただいておりますけれども、1の海外展開の推進、2が法制度の基盤整備、4は国際的な知財保護、5が人材育成、6がその他ということで整理をさせていただいております。本日は時間の関係で御紹介しませんが、また適宜御紹介させていただきたいと思います。
以上でございます。
○中村座長 では、議事に入りますが、今日の議題は、先ほどの資料配付説明に沿って行っていきたいと思っています。
まず、事務局からの説明があって、3省からの報告を受けます。その後で2名の委員の方から報告をいただいて、その後で全体の議論に入るという流れにしたいと思っております。
では、全体議論に先立ちまして、事務局から「コンテンツ海外展開の一層の推進」に関する論点について説明をお願いします。
○永山参事官 それでは、資料1をご覧いただけますでしょうか。本日の「海外展開の一層の推進」に関する論点のペーパーでございます。全体的な構成については、1の「海外展開推進に向けた政府の取組みについて」、めくっていただいて、2の「海外展開における情報・ノウハウ等の共有について」、3として「民間企業による継続的な海外展開について」、大きくこの3つの点から整理をさせていただいております。それぞれについて、これまで委員の先生方からいただいた主な意見、本日の主な論点という形で整理をさせていただいております。
まず、「1.海外展開推進に向けた政府の取組みについて」。これまでの意見としては、事業としての継続の重要性。また、目的・ターゲットを明確にすることの必要性。また、対象国としてASEAN以外の国にも広げていくことが必要ではないかという御意見をいただいているところでございます。
本日の論点としては、後ほど各省から説明がございますけれども、これまで政府が実施してきた政策につきまして、その基本的な考え方、成果、効果を踏まえてどのような課題があるのか、また、今後さらなる取り組みとしてどのような施策が必要かという点について御議論いただければと思います。
続いて、「2.海外展開における情報・ノウハウ等の共有について」ということで、これまでいただいた意見は、情報共有、集約する組織の必要性。また、ベストプラクティス集、そのようなものをつくる必要があるのではないかという御意見をいただいております。
主な論点としては、最初のポツが省庁、実施主体、公的な主体、J-LOPなどさまざまな事業を進めておりますが、そういう省庁、実施主体が得たノウハウ・情報をどのように集約、共有、活用していくのか、そのために今後どのような取り組みが必要かという観点。
また、民間企業においても海外展開を推進していく上で得たノウハウがございますが、それをどう集約、共有していくのかということ。それに対して政府はどういう役割が果たせるのかということについて、論点として整理をさせていただいております。
最後、3が「民間企業による継続的な海外展開について」ということで、これまでの委員会での意見としては、コンテンツ等製造業など関連産業との連携の必要性についての御意見。括弧書きをしておりますが、現地のパートナーとの連携が重要であるという御意見。海外展開に向けて企業の意識自体を変えていく必要性があるのではないかという御意見。また、権利関係については、権利者情報のデータベースの整備の必要性についての御意見。また、映像、動画配信について同時配信をすることの必要性についての御意見。
その他として、よろず支援拠点については、コンテンツ分野の支援拠点というのも必要ではないかという御意見をいただいているところでございます。
主な論点としては、最初のポツは民間企業が具体的にどのような取り組みを行うことが必要かということで、まず民間企業の立場でどういうことが必要かということで、例として関連産業との連携、現地パートナーとの協力体制の構築、制作段階からの権利処理ということが必要ではないかということで、例として示させていただいております。
2つ目のポツが、そういう民間の取り組みに対し、政府としてどういう支援をしていくのか、どのような取り組みが求められているのかということで、例として連携のための仕組みづくり、また、プロデューサーなどの人材育成、海外市場の調査の実施、また、普及・啓蒙、権利処理の問題、データベースの整理、相談体制に関する周知、こういうことが例として考えられるのではないかと思っております。
1枚めくっていただいた後、参考の資料として政府の主な施策について、それぞれの目的に照らしてマッピングをさせていただいた資料、これまでも配付させていただいております。
1枚めくっていただくと、「分野ごとの海外展開モデル(イメージ)」ということで、上のほうの2つ目のポツにありますように、分野ごとにターゲットとか視聴者層、展開方法、それぞれ異なるので、その状況に応じた戦略が必要ではないかという資料。
最後は、コンテンツに関する市場調査として、公的な機関が実施した既存のものとしてどういうものがあるのかというものを参考資料としてつけさせていただいております。
私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○中村座長 ありがとうございました。
今、説明がありましたように、前回の委員会で目的や対象が政府の施策、明確でないのではないかという御意見ですとか、情報共有が重要だといった御発言がございました。そのような発言を受けまして、関係省庁からこれまでのお取り組みについて、目的、基本的な考え方あるいは成果といったことを再度整理してもらいましたので、経済産業省、総務省、外務省からその取り組みを説明いただきます。
関係省庁からの説明の後に一旦質問の時間を設けまして、その後、内山委員、野間委員からプレゼンテーションを行っていただいて、自由討議は最後にまとめていただこうと思っておりますので、御意見はそちらで御発言いただければと思っております。
では、まず経済産業省の取り組みの説明をお願いします。
○平井経済産業省文化情報関連産業課長 かしこまりました。経済産業省のコンテンツ課長、平井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
資料につきまして、各省庁別にとじてございますので、資料番号の2-1が経済産業省から提出させていただいている資料でございます。
今回、コンテンツの海外展開の一層の支援ということでございますので、これまでやっていることの成果を踏まえて、これからのことを整理させていただいております。
1枚目のスライドはこれからのことでございますので、先にこれまでの成果のほうを御説明申し上げたいと思います。2ページ目について簡単に御説明申し上げます。
これまでも経済産業省としまして、総務省あるいは外務省、関係省庁さんと一緒になりましてJ-LOP、日本のすぐれたクールジャパンのコンテンツを海外に積極的に展開していこうということの支援事業を進めてきたものでございます。平成24年度の補正予算をスタートといたしまして、これまで2回こういった施策を講じたところでございます。
具体的には日本のコンテンツを海外に展開するときにハードルとなりますローカライズ、つまり、言葉の翻訳やテロップ、そこに対しての2分の1の補助の支援というもの。
2つ目といたしまして、海外に持っていくようなプロモーション、プロモーション費用の2分の1の補助を公募型で進めているものでございます。
今のところ24年度補正予算に関しましての結果が手元に来てございますので、そこにつけさせていただきました。これは成果の部分でございまして、まずどれぐらいやったかというところに関しましては、昨年ここで御報告させていただいたかと存じます。数字を口頭で申し上げますと、24年度補正予算に関しましては、経済産業省分といたしまして120億円余り計上させていただきまして、実際に提案いただきまして、その中から採択された案件が3,815件。実際に3,815件が出ていった先の国をカウントいたしますと82カ国になります。実際にお使いいただいた企業で海外売上の増加額、1,250億円等の実績をつくったものでございます。
それに関しましての成果でございます。2ページの表に海外展開という意味の成果を取りまとめさせていただきましたけれども、これまでは国内に閉じていたが、実際にJ-LOPで初めて展開したという事業者の数は、J-LOPを利用した事業者の数の大体4割ぐらい、260社はJ-LOPによって初めて海外に展開されたということでございます。
また、これまでももう既に海外に展開していた企業も含めまして、どれぐらい発信先の国がふえたか、あるいはプロモーション先の国が増えたかということでございますけれども、下のグラフに描いてございますとおり、言葉の翻訳事業のほうに関しましては、それまでの平均は大体1社当たり12カ国余りであったところが、22カ国に水平展開が図られている。また、イベント、プロモーションに関しましても、例えばBtoBのイベント、つまり、国際的な展示会や取引マーケットへの出展でございますが、それまで3.7カ国ぐらいにしか出していなかったのが4.8カ国にふえているという形で、着実な成果を積み重ねているところでございます。
これを踏まえまして、最初のページに戻っていただきまして、今後の展開といたしまして、今の国会の冒頭で可決、成立いただきました27年度の補正予算の中で、経済産業省といたしまして66億9,000万円御計上いただきまして、これに基づきまして引き続き日本のコンテンツの海外展開を支援していきたいと考えてございます。
今、執行準備中でございまして、この執行をお引き受けいただける民間の団体を公募の手続によりまして選定作業中でございます。選定次第、その団体を経由しましてコンテンツの事業者の方々に公募をかけたいと考えているところでございます。
事業のイメージ、右のほうでございますが、矢印が2つ出てございまして、右のほうの流れは従来と一緒でございます。民間のコンテンツ事業者の方の公募に基づきまして、現地化やプロモーションを支援していく。2分の1、3分の2の補助金を提供していくというものでございます。
一方で、従来と違いますのは左側の矢印もあることでございます。つまり、従来は補助金をお出しすると、その事業者が海外に展開される、海外に実際に足を運んでプロモーションされるということでございましたが、それだと、結局、どの事業者がどういうコンテンツをどういう権利関係で持っていっているかわからない、将来につながって無体の資産になっていかないのではないかという一部の御指摘もございましたので、今回はきちんとデータベースの形で整理していきたいと思っております。
例えば映像でございましたら、もちろん、その映像のもととなった原作はどなたなのか、その映像そのものの著作権は誰なのか、映像の中に音楽が使われているとすれば、音楽はどのような形で権利が入っているのか、そういったことをデータベース化する必要があるかと思います。
例えば音楽の場合でしたら、曲や歌詞だけではなくて、そこに実演家が入っていらっしゃるのであれば、実演家の権利関係もどのような対応関係になっているのかということ。アーティストに基づいた権利情報というものも必要かと思いまして、そこのデータベースの設計もしていきたいと思っております。
ただ、ここは権利を処理する機関ではございません。あくまでも権利情報を集めるものでございまして、従来さまざまな機関が権利のクリアリングをやっていらっしゃいますけれども、その権利情報をここにまとめるだけであって、ここは権利処理そのものを行うものではございませんので、その点、事業の重複等はないように工夫していきたいと思っております。これがJ-LOPの今後の話でございます。
また別の話題になります。3ページにお進みいただけますでしょうか。これはクールジャパン機構のこれまでの出資案件でございます。クールジャパン機構といいますのは、平成25年10月に設立いただきました官民ファンド、民間の方々と国とが共同して出資したファンドでございまして、正式名称を「株式会社海外需要開拓支援機構」と申します。こちらのほうでこれまで官民ファンドとしましてエクイティー、出資の形でいろいろとリスクマネーを提供しているところでございますけれども、その中のコンテンツ分野に関してリストをつけさせていただいております。
Tokyo Otaku Mode、海外向けの、特にネット関係の販売のプラットフォームから始まりまして、6つ並べさせていただいたところでございます。
それぞれおもしろい事業、あるいは日本のアニメ等のコンテンツの海外展開を実際にサポートするプラットフォーム事業でございますが、それぞれのところは概要のところをお読みいただく形にして、御説明は省略させていただきたいと存じます。
次が、事務局のほうから御提示されているうち、これまでJ-LOP事業でありますとか政府出資事業を通じて蓄積されたノウハウをどのようにして水平展開していくのか、そこのハンズオンの支援の仕組みについて、今やっていること、これから考えていることをまとめたのが4ページでございます。
J-LOP事業といたしましても、過去足かけ3年にわたりまして事業を進めてまいりましたので、ローカライズの企業に関して、あるいは海外のイベントに関してノウハウがたまってございますので、それを生かしたビジネスマッチングのイベントをするとか、海外イベントに向けての合同説明会をする。そのような形で支援を進めているところでございます。
一方で、クールジャパン機構のほうも過去の出資事業等を通じましてノウハウがございますし、また、出資を通じての人脈等を築いたところでございますので、地方でそのエクイティーに基づいて海外に展開しようという企業向けの説明会を開きますとか、あるいは実際に出資を決めた投資先に対しましては、お金を提供するだけではなくて、そういったノウハウを持った人材を派遣することでハンズオンの支援を強化する、そういった取り組みを進めているものでございます。
最後に、事務局のほうから御指摘の点、3ページにありましたよろず支援拠点等を活用して、コンテンツ分野においてもワンストップの支援体制が必要ではないかということでございます。これに関しましてはまだ検討途上でございますが、一番左下に幾つもの支援機関が書いてございます。よろず支援拠点というのが、左下のオレンジの中の右の欄の真ん中あたりにございます。これは事務局から御指摘されている機関でございますが、これは中小企業支援の機関でございまして、47都道府県に一つずつこういった拠点を国のほうで指定いたしまして、そこに国のほうから資金支援も含めまして人員を配置して、中小企業のあらゆる悩みをそこでお聞かせいただく。こうした支援機関を幅広く結集した「新輸出大国コンソーシアム」を設立し、技術開発から市場開拓に至るまで、様々な段階に応じて総合的な支援を可能とする仕組みを検討しているところでございます。その中で、海外ビジネスに精通した専門家が個々の企業の担当として張り付き、支援機関の紹介、現地での商談や海外店舗の立ち上げなどのサポートを行う。こういった仕組みで進めているものでございます。
ただ、残念ながら後ろのネットワークのほうにそのコンテンツ分野でお詳しい方々がきちっとネットワークが組めているわけではございませんので、そういったところをここに書かせていただきました。例えば工業所有権情報・研修館でありますとか、JETROさんでありますとか、そういったノウハウを持った人たちとのネットワークを築く形で、ぜひワンストップの相談体制を築き上げていきたいということを検討しているところでございます。
簡単ではございますけれども、以上でございます。
○中村座長 どうもありがとうございました。
続いて、総務省の取り組みの説明をお願いします。
○豊嶋総務省情報通信作品振興課長 総務省のコンテンツ振興課長の豊嶋と申します。どうぞよろしくお願いします。
お手元の資料2-2について説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
総務省では放送コンテンツの海外展開の施策を進めております。表紙をおめくりいただきまして、まず1ページ目は、目的、事業の中身についてまとめたものでございます。
上のほうに「1.目的・対象国」というところがございますが、放送コンテンツの海外展開を行う狙いという点で、日本の魅力を継続的に発信していくということをしながら、あるいは番組と連動した取り組みを通じまして「ヒト・モノ・カネ」の移動を促進させるということで、ビジット・ジャパンあるいはクールジャパン、地方創生等に貢献をしてきたいというものです。
特に対象国としましては、今後中間層がどんどん拡大をしていく、あるいは相対的にインバウンド・アウトバウンドの高い上昇効果が期待できるという観点から、今、ASEANを中心としたアジアの新興国を対象に事業を実施しております。とりわけ個別の国で申し上げますと、ここに掲げております6カ国を重点国と位置づけして展開をいたしております。
具体的な事業としましては、平成25年度から補正予算という形でございますが、実際に海外の方に見ていただく放送番組をつくっていただきながら、それを展開する。そのための支援をするという事業を進めております。平成25年度補正予算につきましては、ここに掲げているとおり、13カ国で43事業を実施しました。また、平成26年度補正予算につきましては、14カ国、34の事業を現在展開しております。ちょうど今、平成26年度補正予算につきましては、実際に番組がそれぞれ完成して、放送が完了したところ、あるいはまだ放送を継続しているところで、進行中のものでございます。
事務局の御指摘に関連する部分として、放送コンテンツの海外展開に関係する波及効果等についてでございますが、2ページ目でございます。個別の例でございましたが、25年の補正事業で行ったものとして2点ほど掲げているところでございます。
左側は山陰中央テレビがシンガポールで行ったものでございますが、シンガポールの制作会社と日本のお魚を紹介する情報バラエティー番組を共同制作させとていただきました。その際、漁業協同組合連合会とも連携しまして、「PRIDE FISH」ということで、ここに「のどぐろ」とか「マグロ」があるのですけれども、取り上げながら紹介をしたものです。
これにあわせまして、現地の日本食レストラン「WADATSUMI」と連携をしながら、番組と店舗の連動プロモーションを実施させていただいたところでございます。例えば放送番組終了後、「WADATSUMI」自身の売り上げが、2015年2月にオープンしたのですが、その当初比で180%増加したというのがございました。
あるいは右側は、北海道テレビがタイの地上波で放映をした取り組みでございます。下のほうに○がございますが、北海道の物産展におきまして、番組の映像を使いながらコロッケを販売したところでございますが、4カ月の販売を想定していましたが、16万個が2カ月余りで完売をするということがございました。
特に経済波及効果の部分につきましては、今、検討をしているところでございます。具体的な放送コンテンツの海外展開を通じた経済波及効果ということについて、アウトバウンドとインバウンドの効果についての試算を今年度の調査研究という形で進めております。本日、間に合いませんでしたので、正確な数字を申し上げられないのですが、試算を行っております。アウトバウンド・インバウンド込みですが、いわゆる費用対効果について、平成25年度補正予算で実施した事業について試算をしたところ、約10倍前後ぐらいの経済効果が見える見込みということで、今、最終的な精査をしておりまして、年度内に取りまとめをしたいと思っておりますので、またこういう機会がございましたらお示ししたいと思っております。
あと、放送コンテンツの海外展開に関係するKPIの関係で申し上げますと、放送コンテンツの海外の売り上げの数字について、今、2013年の数字が出ておりますけれども、2014年の数字については、大変申しわけございませんが、2月中には何とかまとまる見込みと聞いておるところでございまして、その数値をこの時点では申し上げられない状況ですが、前年度2013年は約106億円という売り上げの数値が既に公表されておりますが、それを上回る、増加する傾向になる見込みだと聞いておりますので、これも必要な数値がきちんと固まりましたら、ぜひ報告する機会をいただければと思っております。
3ページは来年度以降の取り組みの部分でございます。引き続き放送コンテンツの海外展開の促進ということに取り組んでまいります。概要の部分でございますが、1ページで説明いたしました目的とほぼ同じでございますが、3行目に「TPP協定の活用促進による新たな市場の開拓」というものも加えさせていただいております。いわゆる農産品も含めました市場の開拓にも資する観点から行うこととしております。
現在、平成27年度補正予算につきましては、本国会において成立いたしましたので、引き続き補正予算ということで、12億円の執行に着手しようとしているところでございます。
あわせまして、これから国会の審議に向かいますが、これまではございませんでしたが、継続的に行うという観点で、平成28年度の当初予算のほうに2.2億円計上しております。事業的にはどちらかというと補正予算のほうが規模的には大きいものを想定しておりますが、地方のローカル局等も含めまして海外展開できるようにということで、今、当初予算に計上しております。当初予算はこれまでなかったものでございますので、これが国会で御承認いただければ、この2つの事業を並行して今年度進めてまいりたいと考えております。
なお、ノウハウの共有の部分について、これも資料がなくて恐縮でございますけれども、平成26年度分は今、継続中でございますが、特に平成25年度分の事業をやりながら蓄積したノウハウという点で申し上げます。この事業、いわゆる日本のテレビ局と海外が共同でつくっていくという面が非常に強うございまして、共同制作を通じまして、例えば現地の商習慣、あるいは番組の規制とか、いろんな知見が徐々に蓄積されつつございます。このノウハウにつきましては、実際に推進においていろいろ御尽力いただいていますBEAJ様におきまして、例えばホームページの掲載とかそういう形で関係者への周知をできないかということで、今、検討を進めているところでございます。
あわせて、総務省とBEAJが連携をしながら、これまでの取り組みについて各地での説明会を随時開催しながら周知をしていきたいということでございまして、ここの取り組みもひとまずまとまりましたら、御報告させていただく機会がありましたらと存じます。
最後の4ページ目は、海外展開に絡む部分として権利処理の部分でございます。これまで放送コンテンツの海外展開に関連する権利処理ということで、実演家様に係る権利処理、レコード原盤権に係る権利処理について、迅速な取り組みを実証実験という形で行ってまいりました。
そのうち実演家につきましては、既にaRma(アルマ)におきましていわゆる自走化が完了しておりまして、平成27年4月から自走化が行われておりますが、さらなる迅速化、効率化が図れないか。あるいはレコード原盤権については本年度まで実証実験という形で進めておりますが、来年度以降、どういう形で進めていくのが適切か。これらに関し、いわゆる関係者におけるルールづくりをしようということで、昨年末に実演家、レコード制作会社、放送事業者、有識者等々を含めまして連絡会を設置いたしました。
そのもとで各権利に分かれまして実務者連絡会を開催しておりまして、実演家につきましては、現在処理している方法について、特に放送とネット配信もあわせて迅速にできる手続ということで、今、行っているものについてさらなる見直しができないかという点について実務レベルで調整をしております。
あわせて、レコード原盤権については、実証実験が今年度で終了しますので、それを踏まえて、来年度以降、どういうルールのもとで行うかということについての連絡・調整を進めているところでございます。ひとまず今年度末に一定の整理をするべく、今、作業を進めているところでございます。
総務省からは以上でございます。
○中村座長 ありがとうございました。
では、外務省の取り組みの説明をお願いいたします。
○渡邉外務省文化交流・海外広報課首席事務官 外務省文化交流・海外広報課の渡邉と申します。
本日は、事務局から御依頼のありました2つの事業について御報告させていただきます。1点目は放送コンテンツの海外展開支援事業、2点目は「文化のWA」というアジアとの交流強化のプロジェクトです。
資料2-3を1枚めくっていただきますと、放送コンテンツの海外展開支援事業の概要を記載しております。外務省では、国際交流基金を通じまして、商業ベースではなかなか日本のコンテンツが放送されない国や地域に対して、日本のドラマやドキュメンタリーなどの番組を無償提供するという事業を行っております。
これは総務省や経済産業省とも連携しまして、重複のないように、商業ベースでは展開が難しいという国を中心に番組の無償提供を行う事業です。
対象国は、アフリカ、中南米、アジア、大洋州などです。こういった地域の国々で、日本の放送コンテンツを放映することによって親日感を醸成し、親日層を形成していくということで外交政策に資する、あるいは日本の企業が展開しやすくなる、そういった効果を期待して事業を実施しています。
将来的には、これらの国で日本の番組に関心を持っていただいて、さらに放送したいということになれば、商業ベースへの展開を期待しています。
この事業は、3ページ目でございますが、国内ではいろいろな事業者から放送コンテンツを提供していただき、在外公館に要望調査をかけまして、事業実施対象国に対して放送可能なコンテンツを提供していくという流れで実施しておりますが、番組や対象国につきましては、関係機関、関係省庁と調整の上、要望を出してきた国のテレビ局に対して提供できるコンテンツについて契約をして進めている次第です。
現在の実施状況ですが、現在実施中の事業の予算としましては、平成26年度の補正でお認めいただきました30億がベースとなっております。その予算を活用いたしまして、現地のテレビ局へ打診した結果、120局を超えるテレビ局から約800番組についての提供希望がありました。この中から約70カ国の放送局に対して、約330番組を提供しているところです。
番組の提供例としましては、ここに3つ挙げておりますが、ドラマやアニメ、あるいはドキュメンタリーといったものを提供しています。
これらを提供し始めて、放送がやっと始まったところですので、具体的に挙げられる成功例がたくさんあるわけではないのですが、これまでも類似の事業をやってきた中で、あるいは今回大規模にこの事業を展開している中での成功例を御紹介させていただきますと、例えばトルクメニスタンにテレビ番組を提供しましたところ、先方が日本のテレビ番組に大変関心を示してきて、自分たちでも日本のテレビ局に番組提供について、交渉したいというような関心が示されて、こちらのほうから先方へ国内の連絡先を渡してつないだこともあります。
モンゴルでは、現地でアメリカの番組しか放送しないチャンネルに対して、ドキュメンタリーの番組を提供するということに成功しまして、今年から日本の番組が放送されることになっております。そのテレビ局ではほかのテレビ番組も希望しておりますので、これからさらに多くの日本の番組が放送されていくのではないかと思います。
これらの事業を行っている中で、事業が始まったばかりですが、課題として出てきております話を御紹介します。現地のテレビ局と話を詰めていく中で、現地では地上波のみならず、衛星放送ですとかケーブルテレビ、あるいはインターネットでコンテンツを放送することができないかという話もありますし、提供する放送素材につきましても、デジタルであったり、ファイル形式が違ったりという話が交渉の過程で出てくるものですから、国内の放送許諾条件とちょっとずれがあることも結構ありまして、それでなかなか契約がスムーズにいかずに、時間をとってしまうということもあります。また、私どもが番組を提供している国は商業展開が難しい国ということで、開発途上国がかなり多いのですが、そういったところでテレビ局の担当者が変わりますと方針が180度変わってしまう、あるいは交渉している中でレスポンスが遅いということあります。そういったところは今後課題として取りまとめていこうと考えております。
現在事業として進行しているところですので、今後課題やノウハウをまとめ、そして検証して、こういった場で御報告させていただく、あるいは放送事業者の方々との今後のやりとりの中でフィードバックさせていただくということになろうかと思います。
それからもう一つの事業のほうですが、5ページ目になりますが、こちらは、平成25年に日・ASEAN特別首脳会議において安倍総理から表明しました「文化のWAプロジェクト」と言いますが、2つの柱で構成されています。
1つは「日本語学習支援事業」と言いまして、現地で日本語を教えておられる先生方の補助として日本語パートナーズ、日本語を勉強している人あるいは先生のパートナーになるような方を日本から派遣するという事業です。
もう一つの事業は「芸術・文化の双方向交流事業」です。こちらは日本の文化を紹介するだけではなくて、双方向で紹介しようというもので、この中の一つが東京国際映画祭との連携交流事業です。
6ページ目にありますが、東京国際映画祭と協力させていただきまして、国際交流基金では、アジアの映画交流のプラットフォームをつくって強化していく取り組みを進めています。例えば、アジアの映画を紹介する部門「CROSSCUT ASIA」を設けまして、アジアの映画を集中的に紹介する、あるいは映画関係者を日本に招聘する、さらには映画監督を顕彰するといったような事業を行っているものです。
こちらのほうも2014年から始まったばかりですが、これまでなかなか集中的に紹介することができなかった東南アジアの映画を上映する機会がだんだん増加することになりまして、これからも継続したいと考えております。逆に東南アジアの映画を日本で紹介するだけではなくて、東京国際映画祭と協力しましてフィリピンやカンボジアで日本映画祭を開催して、向こうでも紹介するというようなことも行っております。今年度、フィリピン、カンボジアで開催した映画祭には2万5,000人が訪れております。
東京国際映画祭との連携事業での課題としましては、東京映画祭全体の広報というのは大々的にやられているわけですが、この中において東南アジアの映画部門「CROSSCUT ASIA」の広報をうまくやっていくというところがスムーズにいっていない面もあり、集客がこれからの課題と考えているところです。
また、従来、東南アジアの映画が数多く紹介されてきたわけでもありませんので、関心も欧米の映画に比べますと低いものですから、こういった招聘事業を行いまして、バイヤー、セラーを招聘しても、なかなか成約率が低いということもあります。こういった課題が出てきておりますので、課題を検証しつつ継続していきたいと考えているところです。
以上でございます。
○中村座長 どうもありがとうございました。
では、各省からの説明について御質問があれば、挙手をお願いいたします。意見交換は最後にまとめて行おうと思っておりますが、もし何か質問がありましたら、お出しいただけますでしょうか。いかがでしょうか。どうぞ。
○野坂委員 説明どうもありがとうございました。各省に質問したいと思います。
まず、経産省です。経産省の資料の中でクールジャパン機構に触れていらっしゃいました。平成25年にスタートしたばかりで、まだ日が浅いわけでありますけれども、リスクマネーの投入ということで、やはり投資に対するリターンをいずれ考えなければいけないと思うのです。3ページの資料ではそういったリターンの状況については出ておりません。日が浅いので具体的なリターンというのはまだ先なのかもしれませんけれども、既に投資した案件で何らかのそういう兆しといいますか、手応えみたいなものが出てきているのかどうか、それについて補足で説明していただければと思います。
2点目は総務省です。総務省の説明の中で、先ほど経済効果で10倍前後という話がございましたが、これの意味がよくわからなかったのです。要するに、予算の投入に対して10倍ぐらい何らかのものが出た、売り上げが伸びたという趣旨なのか、もう少し詳しく説明していただければと思います。
また、これと関連するかもしれませんが、外務省の資料の中で、商業ベースに乗らない国に対する番組の提供を330ぐらい予定しているという説明がございましたけれども、これに相当する総務省の数字、つまり、商業ベースとして考えられている国々に対して、実際どれぐらいの数の番組が提供されたのか、あるいは今後提供する予定なのか、教えていただければと思います。
最後に外務省ですが、外務省は今、商業ベースに乗らないものを中心にということで、重複のないようにするという説明がございました。私たち、前回の議論でも情報の共有、情報の連携ということに大変ポイントを置いてきました。そういう意味では、商業ベースに乗らないものといずれ商業ベースに乗るかもしれない、あるいは乗っていかなければいけないという情報について、外務省、総務省、あるいは民間等を含めて、どういう形で情報共有、連携を図っていらっしゃるのか。どこかにコントロールタワーというか、司令塔があって、そういう番組の海外展開についての戦略を練る、そういった手段をお持ちなのかどうか教えていただければと思います。
○中村座長 どうぞ。
○平井経済産業省文化情報関連産業課長 それでは、最初に経済産業省でございます。
クールジャパン機構のリターンの見込みということでございます。正直申し上げてまだスタートしたばかりでございまして、配当の形、あるいはそれ以外の、IPOみたいな形での成果まで至っていないという点に関しましては、御指摘のとおりでございます。官民ファンドでございますから、国のほうからもしかるべきシェアでファンドにお金を入れておりますので、そういったものに対してリターンの目標、KPIとしまして、1.0を割り込んでしまうと、これはマイナスになっているということですので、1.0以上のリターンをきちんと確保できるようにポートフォリオを考えていくというのは当然でございます。
また、国のほかの官民ファンドと同様に、官邸のほうでそういったガバナンスがちゃんと持たれておりますので、そこへ適宜これからの数字も御報告していく所存でございます。
個別の案件でございますけれども、ポートフォリオの中でどうしても時間がかかるもの、例えば人材育成みたいなものはすぐにはいかないわけでございますが、一方で、すぐに動き始めているもの、例えば衛星放送で番組を流し始めるとか、インターネットでその商品を含めたネットの販売を開始するというような足の速い事業に関しましては、それなりにサブスクライバーの数をふやしているという意味での手応えは感じているところでございます。
○豊嶋総務省情報通信作品振興課長 2点御質問があったと思います。
まず1点目ですが、集計しているものですから、まだお出しできなかったのですけれども、経済効果として今、分析を進めようとしていますので、フレームワークだけ申し上げます。簡単に申し上げると、今、試算として出そうと思っているのは、我々は平成25年度補正予算で事業を行いましたが、投資の金額に対して、効果としてどのくらいの効果があったかという前提でやっています。その場合、効果として捉える範囲というのは、詳細に詰めなければいけないのですが、大きく分けてインバウンドとアウトバウンド、この2つがあると考えています。
先ほど小さな話でコロッケといった話がありましたが、例えば番組を通じることによって、現地でその番組を取り上げたものに関係して、売り上げなり海外で効果が出たもの、これがアウトバウンドの効果の部分となります。それと、逆に日本に来られて観光をされる、あるいは来られて日本の国内で消費をされる部分、この辺りの部分がいわゆるインバウンド効果として捉えられるのではないかと思っています。
ただし、その事業で行ったものと関連するものとして、そこの売り上げ等の効果との比率で10倍前後になるのではないかと思っているのですが、どうしてもこの話というのはいろんな要素が絡みますので、インバウンドとしてどこまでを一応対象として推計をはかろうかというところが、いろんな意見がございますので、今、ここの集約をしておりますが、おおむねの考え方を申し上げますと、平成25年度補正予算で投じた事業費に対して、インバウンド及びアウトバウンドとしての具体的な売り上げ等々の部分との対比、比率ということで分析を出していきたいと考えております。
あと、放送番組の海外展開の関係で、外務省の裏側になるという意味でビジネスに乗りやすいという点ですが、個々の放送事業者さんは個別に当たっているので、個別というのは今、手元にないのですけれども、大まかに申し上げますと、継続的にビジネス、例えば番組で言うと、番組そのものを販売することもあれば、最近、どちらかというとフォーマット販売というか、番組のコンセプトそのものを提供して、実際にはその現地で番組をつくっていただいているという形もあります。いずれにしても、日本の放送番組を起点としてビジネスとなっているものとしては、今、東南アジアのほうに力を入れていますが、もともとの関係で言うと、いわゆる商取引として成り立っているものとすれば、例えば北米あたり、あるいは最近は中国でもそういうのが出始めておりますけれども、そこら辺がもとから実績がありましたという点であれば、その点があるかなと思います。まさに東南アジアにおいてバイヤーとしての成長が見られますので、ここに今、集中投資をしているというものです。
雑駁な答えで申しわけございませんが、そういう考えでおります。
○渡邉外務省文化交流・海外広報課首席事務官 御質問いただきました情報の共有、連携という点ですが、私どもは国際交流基金を通じて商業ベースでコンテンツの展開が難しい国を対象としておりますので、商業ベースで展開できる国については、私どもの事業の対象にならないようにする必要がありますので、外務省・国際交流基金が要望調査をしまして、日本の番組を要望してきた国については、実際に提供する前に、総務省、経産省とよく連絡をとりまして、どういった国を対象としようとしているかを情報提供しまして、それで関連機関あるいは放送事業者とも情報共有をさせていただきつつ、事業を行っているところです。
これに限らず、放送コンテンツの海外展開という事業そのものが総務省、経産省あるいは観光庁と連携している事業ですので、そこは重複のないようにということで、課長レベル、それからそれ以下のレベル、それ以上のレベルでも、意見交換を行い、情報共有しつつ進めていっております。
○中村座長 ほかに質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
では、続いて委員からのプレゼンに移りたいと思います。内山委員と野間委員に御用意いただいておりますので、まずは内山委員から御発表をお願いできますでしょうか。
○内山委員 それでは、始めさせていただきたいと思います。
(PP)
事務局からこういうお題をいただいておりましたので、あくまで外野の研究者の立場でお話をさせていただければと思います。
1つだけ注釈がありますけれども、外野の研究者の発言ですので、事実誤認とか間違いがあるかもしれません。そうしたものがあれば、遠慮なく御指摘をいただければと思います。
それから、私は出版方面の知識が余りなくて、この中にそれが入っていませんが、今日はこの後、野間社長のプレゼンもありますので、そこはお任せしたいと思います。
(PP)
まず、現状です。これは総務省の情政研が毎年出している放送番組の海外番版の売り上げです。2010年を底にして、今のところ順調に伸びている。安倍政権当初にあった3倍増といったところもおそらくはいくのだろうなという外野の期待です。
(PP)
映画のほうの輸出です。先週新しい数字が出てびっくりしたのですけれども、非常に大きな伸び方をしております。映画のほうは2012年を底にして伸びているという状況であります。
(PP)
アニメは映画、放送あるいはマーチャンダイジングを含めてといったところの数字で、動画協会さんがまとめている数字です。こちらも2012年を底にして順調に伸びているといったところだと思います。
(PP)
音楽のほうをトータルで見る方法はなかなかないと思うのですが、JASRACさんが出しているライツ収入の部分を代表値としてとろうと思って見ています。こちらも2012年を底にして、ちょっとでこぼこがありますが、一応ふえているというベクトルはあろうかと思います。
(PP)
ゲームです。これはCESAさんが毎年まとめていらっしゃるデータで、データのとり方が変わったということがありましたので、2012年まででグラフはつくってあります。ただ、13年、14年の数字は下に書いたとおりでございます。同じく2012年を底にして、きっと伸びているのだろうというふうに言えるかと思います。
(PP)
ここまでのところで2点だけ押さえさせていただきたいのですが、いずれも2012年あるいは10年といったところを底にして伸びているというトレンドはあろうかと思います。
データを取りまとめているのが、放送は総務省ですけれども、ほかは全て業界団体さんが取りまとめているといったところがポイントとしてあろうかと思います。
その上で、幾つか問題提起ということで、2点ばかり置きたいと思います。本当にグランドデザインのレベルで、政策目標をどういうふうに置いていくかといったところ。まさしく今日のテーマで、コンテンツ産業の海外展開において目指すべき方向性。象徴的に言えば、ハリウッドのようなことを目指すのかどうなのか、あるいはそれができるのかといったところ。
もう一つは、流通構造の問題をそろそろ考えてもいいのかなと思っております。
(PP)
1つ目の問題提起で、グローバルプレーヤーを目指すかといったときに、業界の方が多いので、何となく直感的におわかりになると思います。
(PP)
コンテンツの幾つかの分野においては、まさしくグローバルプレーヤーとドメスティックメジャーとか、民族系といった切り分けあるいは一種の分類みたいなものがあろうかと思います。象徴的なのは、恐らく映画と音楽かと思います。つまり、映画でしたら、ハリウッド6大メジャーは、世界中どこ行ってもシェア1位、2位を争える。各国のドメスティックメジャーは1位、2位を争うのですけれども、自国の外に出てしまうと、ほとんどシェアをとれないといった構造。ハリウッドだけが世界中でそういった1位、2位をとれるという構図。
音楽も昔は6大メジャーだったと思います。EMIとかBMG、ポリグラムがあって、いろいろ統合があって今、3大メジャーになっていますが、似たような構図になるのかなと思います。
こういったグローバルプレーヤーの世界を日本は目指せるのかどうかといった問題だと思います。
(PP)
条件的にどういったものがあるのだろうということで、昔、こういったものは学術研究もあったので改めて振り返っていたのですが、こういった条件が挙がってくるのかなと思います。こういった条件に照らし合わせたときに、実は数年前から思っているのですけれども、日本のコンソール型ゲームだけはグローバルプレーヤーの資質を持っていた、あるいは今も持っていると思いますが、持っていたというふうに私は考えております。海外収入の規模が圧倒的に桁が違うのです。先ほども見たとおり、映画や放送あるいはアニメといったところは数百億円単位の海外収入規模。それに対して、ゲームは数千億あるいは兆の単位に乗ってくるといったところ。
それから、世界中主要拠点に支社があって、そこでローカルプロダクションあるいはライセンシングを行うという体制をつくっていったといったところ。音楽メジャーの構図にかなり近いのだろうなと解釈をしておりました。
(PP)
この画はいろんなところで使っているのですけれども、昔、VIPOというところにいて一生懸命やっていたときにつくった絵の一つで、ちょこちょこと直しながらつくってはいますが、私がわかる範囲の各コンテンツになると、大体こういう国際化の進展をしているのではないかなと解釈をしております。
縦軸にあるものは、一般的な企業の国際展開とか国際化といったときのステージ、あるいは発展段階とみなしてください。
5番目の「トランスナショナル経営」というのは、日本でしたら、例えばメーカーさんだったら、明らかにこういうレベルに達しているところがたくさん存在しているわけですけれども、コンテンツ分野ではなかなかそこまで行かない。ここに到達しているのはアメリカの資本のところばかりというのが現状で、それに対して、ゲームのコンソール型はやはり食い込んでいっただろうなと解釈はしております。
(PP)
何でという話で、必ずいろんな方々が指摘される件ですけれども、もともとこういう文化的な商品、財、グッズに関しては言語という天然の貿易障壁がある。英語という経済的に豊かで、ある程度人口が多いところの壁を突破するのはとても大変だというのは、皆さん、よくおっしゃるとおりで、数字でとっていくとこんな感じかと思います。
いい比較対照で、イギリスとフランスという似たような規模感の国で、隣接していて、両方ともそれなりに国際的な存在を示している国ですけれども、放送番組や映画の輸出ということでカウントしていくと、全然桁が違ってくるという状況になっています。
御存じのように、フランスは第二次世界大戦後、ド・ゴールが一生懸命フランス語を外交の道具にしていろいろやったときもあったのですが、それをやってもなかなか英語の壁というのは越えられないといったところがあります。
ただ、フランスやドイツは、欧州という大きなリージョンで考えれば、強いプレーヤーであるというのも一方の事実です。
(PP)
なかなかこういう数字はとれないのですけれども、たまたま私、毎年買っている年鑑の中にあったので引っ張ってきました。ちょっと古いですが、2011年で、欧州15カ国の主要チャンネルで放送された番組の原産国、もとの国の集計をとったものが13ページの画になります。圧倒的に強いのは3段目にあるアメリカで、シェアは52%です。自国の数字は1段目のほうにある13点何%で、それもなかなか押されている状況です。
そういう中で、フランスは1.68%、ドイツは2.22%という形で、数字だけ見ると小さいなと思うのですけれども、なかなか健闘しているというレベルにあります。イギリスは、ある意味で中間値にあって、3.87%という数字になっていて、フランス、ドイツよりは明らかに強いのですが、もちろんアメリカほどにはいかないというところです。
蛇足的に言えば、日本もそこそこ食い込んでいて、その中で1.1%のシェアをとっていて、一応カナダやオセアニアとは戦えるレベルまで来ているといったところで、数字はとることができるかなと思います。
そうしたグローバルプレーヤーでもない、でも、各国の中でドメスティックプレーヤーである、あるいはリージョナルメジャーとしてある程度の競争力を持てるといったとき、どんなことを考えなければいけないかなといったときに、やはりこういった話なのかなと思います。
(PP)
基本的には国際的なBtoBのネットワーキングの強化といったことが必要になってくるでしょうねといったところで、大きく流通部門のネットワーキングと制作部門のネットワーキンググループと分けたときに、流通部門のネットワーキングに関していっぱいいろんなことを日本の政府もこれまでやってきていると思いますし、これからも期待されているのだと思いますが、相対的にそれに比べれば、制作部門のネットワーキングはまだまだこれからという話ではないでしょうかといったことです。
具体的なことで言えば、先ほど豊嶋課長からも御指摘がありましたけれども、国際共同製作を通してその現場がネットワーキングしていく、あるいはノウハウの共有をしていくということも必要でしょうし、それから日本はあまり意識しませんが、世界のいろんな国が意識していることは、ハリウッドの巨万の金をいかに引っ張ってくるかということを考えるので、グローバルプレーヤーの投資誘致をどういうふうに考えていくかということも、ほかのことに比べれば日本は割に意識していないのかな、あるいはしたくないのかなというところがございます。
それを間接的にどう支援していくかという話なのですが、これは個人の持論としてずっとある話ですけれども、こうしたものを補助金型でやるのではなく、基本的に税制でやるべきで、これがグローバルスタンダードだと考えます。日本の国内制度、税制でやることが難しいというのはVIPO時代に聞かされましたので、重々承知しているつもりですが、ただ、それは国際的に見たときに普通ではないと考えます。
データの公表という問題。先ほども議論がありましたので、次のシートでいきます。
それから、社会的な問題意識。何でコンテンツ産業を守ったり、支援したりするのか。波及効果が高いからというところが一つ争点になっていますけれども、一つだけ指摘しておきたいことは、例えばヨーロッパは戦間期からこうしたコンテンツ支援ということを盛んにやっています。その背景にあったことは、ハリウッドからの集中豪雨的な輸入に対する危機感です。文化的な危機というところを強く持って、それで国家を挙げて守った、あるいは支援した。それがいまだに続いているといったところがあります。
そこまで意識を持つかどうかはまた別の問題ですけれども、世界で見れば、そういう意識もありますよといったところだと思います。
(PP)
データの共有ということでありますが、別に国際ということに限らず、こういったメディア系、あるいはコンテンツ系といったときに、大体官公庁経由のもので言うと、この3つかなと思います。実際私も使っています。
ただ、正直言いますとここが発信の一次データがそれほど多くないのです。つまり、業界団体さんがまとめたデータを転載しているというスタイルのものが多くて、ほかさんがまとめたものを転載しているというものであれば、例えば民間が出しているものでも十分いいものがあろうかと思います。別にこれを押すということはないのですが、例えば電通総研さんが出している「情報メディア白書」などというのは、もっともっといろんなところから転載しています。なので、一次データがあるかどうかというところがその価値となってくると思うのですが、先ほどのデータチェックで見たとおり、かなり多くのデータを業界団体に依存しているというのがこの国の現状だと思います。ほかの国でいくと、例えば補助金をたっぷりまいているフランスなどは、政府であったり、日本で言うところの独立行政法人がそれをまとめてやるということをやっています。
一方で、例えばイギリスではTV Export Bibleというのがありまして、pactという業界団体さんがまとめています。
どこでまとめるかというのは、それぞれのお国柄の事情もあると思いますので、一概にこうだと言うつもりはありませんが、安倍政権になってJ-LOPのように桁が違う補助金を出し始めたということであれば、もう少し政府側も集めてもいいのだろうなと思いますし、民間側ももう少し出してもいいのではないかと思います。
補助金が少ない時代であれば、民間が勝手にやっていることについて、民間が情報提供する義務はないわけですけれども、公金を使って多少なりとも民間活動の支援がなされているとすれば、そこは一応情報提供を求める理屈があるわけで、J-LOP以前と以後では一次データの問題に関しては全く状況が変わってきていると思います。
どういう情報を共有するかといったところでは、定量データを共有するという問題と定性データを共有するという問題があって、定量データ自体は、業界団体さんが出してくれている面もあるので、比較的共有はできるほうだと思います。ただ、今のように東南アジアを重点にやっていて、東南アジア方面のデータがあるかというと、本当にないです。欧米方面を経由して探そうと思ってもなかなか見つからないというのが実情でして、もし引き続き東南アジア方面を重視していくのであれば、ここはある程度真剣に、データ収集体制を考えたほうがよいと思います。
もっと難しいのは定性データの問題でございます。これは企業さんの経営戦略であったり、競争優位にかかわる問題になってくるので、企業さんはなかなか出したくないというのが本音だと思いますので、この辺を今後どうするかなというところはあろうかと思います。
私は昔、VIPOというところにいたときに、総務省の予算をいただきまして、『放送番組海外展開ハンドブック』という本を2回ぐらい出させてもらったことがありました。そのときもなかなか情報を出してもらえなかったのですけれども、成功ストーリーは逆に出していただけるので、多分次のタイミングは、そういう成功ストーリーを集めたようなもの、しかも件数が多いものというものをつくってもいいのではないかなと考えます。
(PP)
もう一点の論点は流通構造の問題です。
(PP)
やはりネットの問題です。ずっとこの政策の論議は、基本的には国際的なBtoBを想定していて、どちらかというとフェース・トゥ・フェースでという側面を重視していると思います。グローバルプレーヤーは、別に見本市に行かなくても、自分たちで商談の場をつくれてしまうわけですね。L.A.Screeningであったり、BBC showcaseであったり、あるいはカンヌ映画祭期間中にハリウッドメジャーは豪華なホテルを借り切りますから、別に公設見本市に依存しなくていいのです。しかし、リージョナルメジャーであったり、ドメスティックメジャーだとどうしても公設見本市に頼らざるを得ない。それがMIPであったり、Cannes Marcheであったり、E3であったり、SIGGRAPHであったりというような状況だと思います。それぐらいある意味ではグローバルプレーヤーの流通構造というは強いわけですが、短期的に成果を出したいというのであれば、そこに乗っけたほうが早いというのはあるかと思います。
次のページは、古いデータなのでお許しいただきたいのですが、ポケモンの映画バージョンが海外展開したときにどうだったという話で、一応海外には5本出ているはずです。最初の3本はワーナー・ブラザースが世界配給をやったのですね。すさまじくいい結果を出してくれているのですが、その後の2本というのは、ミラマックスが配給しています。世界から上がってくる収入が全然違っていたと。それぐらいハリウッドメジャーの収益力は強いということなのです。
(PP)
ただ、そのことを本当によしと考えるかどうかは全く別の問題だと思います。それはいろんな意味で行間がある話だと思います。
もう一つ、そうした現状のフィジカルな流通構造に対して、ネット配信ということをそろそろ真剣に考えましょうよというタイミングで問題提起をさせてもらいます。
(PP)
ネット配信で今、一つ危惧している問題は何かというと、外国なので個社名は許してもらいたいと思うのですが、SpotifyであるとかNetflixとか、こうしたネット配信におけるグローバルプレーヤーというものが形成されつつあるのではないか。先ほどの映画と同じように、こうしたところは世界中でシェア1位、2位を競う。また、現地にはそれぞれドメスティックメジャーがいて、それらとシェア1位、2位を争うというような構図が徐々につくられつつあるのではないでしょうか。
1~2年前であれば、ネット配信は安くて売りたくないというのもいろいろ聞いた話ですけれども、最近はあまりそういう声が聞かれず、むしろ買付単価が上がってきたという指摘も徐々に出始めています。
2行目に書いたことは不正確なので、余り積極的に取り上げていただきたくないのですが、先週、映連で新しい映画の輸出の伸び、50%伸びたよという数字が出たときの理由の背景で一つ言われたことは、北米向けアニメの配信収入の伸びという要素が一つ言われました。どう考えてもNetflixとAmazon Primeなのです。それから、その2行下、2つありますけれども、英語の新聞記事で、1月末というのは、御存じのように、Sundanceというインディペンデント映画の大きな映画祭があって、そこもマーケットになっているわけですが、AmazonとNetflixがすさまじい買付をやっているという記事がぼこぼこと出ました。だから、こうしたネット配信という新しいアウトレットがいよいよ確立しつつあって、海外収入を考えるときに、この辺もそろそろ真剣に取り組むということを考慮したらどうでしょうかという問題提起でございます。
以上でございます。
○中村座長 ありがとうございました。
続きまして、野間委員からの御発表をお願いします。
○野間委員 講談社の野間でございます。
今日は、弊社の海外戦略と課題ということでお話をさせていただきます。他のコンテンツ産業と比べてどの程度進んでいるのかわかりませんけれども、御説明をいたしたいと思います。
(PP)
まず最初に、全体像を話しまして、その中で北米事業を例にとって現状及び課題ということについて御説明をさせていただきます。
(PP)
1ページ目です。ただいま弊社は海外に現地法人を全部で12社ほどつくっております。100%出資の会社、ジョイントベンチャーでやっている会社、いろいろあるのですが、特徴を言いますと、これら12社のうち10社はここ10年以内に立ち上げたもの、残りの2社はこの10年以内に事業構造を全く変えたというところです。
このうち、台湾は長期的な投資ということで、まだ黒字が出る段階には行っていないのですが、おかげさまで、ほかの地域はきちんと順調に利益を上げているというところです。
もう一つ言いますと、12社ある中で日本人を日本から派遣しているのは2人だけ、アメリカと中国に1人ずつ送っているだけで、あとは全部ローカルのマネジメントに任せてやっているというのが特徴かと思っています。
全体の海外事業で言いますと、一番多いのはライセンスを販売する、版権を許諾するというところで、マンガがメインです。全世界で25の国と地域にマンガを許諾しているという状況です。
私どもの海外展開の狙いというところで申し上げます。今年で創業107年になるのですけれども、「おもしろくてためになる」出版物を読者に届けるということをミッションとしてやってまいりました。けれども、最近、言い方を若干変えていまして、「『おもしろくてためになる』出版物」というのはもうやめましょうと。我々は電子書籍もいっぱい出しているし、アニメもつくっているし、ゲームもやっているし、グッズもやっているし、いろんなことをやっているので、とりあえず出版物に限らず、「おもしろくてためになるもの」をまずつくりましょうということです。それをこれまでは「読者に」という言葉を用いていたのですが、そのように製品、商品も多様化してきたということで、「読者に」とは言わずに、「より多くの人々に」というように意識と言葉を変えてきています。より多くの人々というのは、日本国内に限らず、全世界を対象としてやっていこうというのが、ここ10年ぐらい私が社内で言ってきたことでございます。
国際部門の収入の伸びなのですけれども、ここ5年のトレンドで見ますと、2010年から2015年にかけて大体2倍ぐらいになっています。後ほど御説明します北米の現地法人の売り上げというのは、5年前は大きな金額ではなかったのが10倍以上に伸びているというところです。
(PP)
この点を御説明しますと、社内の国際部門の収入というのは通常ロイヤルティーの収入なので、金額としては大きくならないということです。ところが、北米の場合は、実際にマンガ及び書籍を製造し、販売して流通させているということで、売り上げがこういうふうになっております。
このアメリカの数字、また、アメリカのロイヤルティーから類推すると、恐らく全世界で私どものマンガ及び書籍、雑誌の小売価格ベースだと、多分200億円から、それ以上ぐらいかなというのが現状でございます。
(PP)
先ほどの国際部門の収入の伸びをお見せしております。これは先ほど内山先生のグラフにもありましたけれども、地上波テレビ番組の輸出金額だとか、アニメ業界の海外収入の図と結構似ているのです。表の中にもあるのですが、北米のマンガ・アニメバブルが崩壊したのが2007~2008年ということで、そこで一旦売り上げが落ちました。そのころに海外収入を伸ばさなければいけないなということで、海外の現地法人を積極的につくっていって、インフラ整備をいたしました。最初のページに絵がありましたけれども、インフラをつくり上げたところに『進撃の巨人』という非常にビッグなタイトルが出て、それがうまく乗っかって今、非常に順調に数字を伸ばしております。
(PP)
ここからアメリカの話をさせていただきます。アメリカに今、4社ありまして、ホールディングカンパニーとマンガの会社、書籍の会社、あと、昨年つくりました電子書籍の配信とマーケティングを行う会社という4社の体制でやっております。
実はアメリカに現地法人をつくってから今年で50年になるのですけれども、50年前から何をやっていたかというと、40年間はほぼ日本の文化の輸出です。日本食の本を出したり、武道関係の本を出したり、日本の小説を紹介したりということで、ある意味利益を度外視して、文化交流というところでやってきました。もちろんその活動のなかからは、村上春樹さんを紹介して、世界的に有名になっていただいたりという実績も残してきたのですけれども、ここ10年ぐらいでその構造を変えようということで、きちんとビジネスをやりましょう、アメリカで自ら出版をしましょうというふうに変えてきました。その結果、組織、戦略を再構築したというところでございます。
アメリカに限らないのですけれども、今、そういった事業をやっていて、課題となることが大きく3つありまして、一つは海賊版対策、もう一つはマーケティングをどうしようかということ、もう一つはコストというところでございます。
(PP)
次のページが北米の現地法人の売り上げの金額の推移です。先ほど申し上げたとおり、こうやって伸びてきています。赤い部分がマンガの売り上げなのですが、まだまだ成長の余地はあるなと思っておりまして、これまでアメリカでは電子書籍の配信、マンガの配信というのは余りやっていないのです。うちも出しているのが100タイトルぐらい。日本ではマンガの配信だけで2万タイトルぐらい出しているので、この後、アメリカでもここ1年で2,000タイトルまで増やそうと思っていますので、そうなるとさらに売り上げの拡大も見込めると思っております。
(PP)
海外事業をやっていく中で、先ほど申し上げた課題のところで言いますと、まず海賊版対策ということがあります。これは平成25年度、経産省さんの調査では被害額が推定2兆円です。2兆円、そのように巨額の被害をどうするのかと。我々だけではもうどうしようもないというのが正直なところでございまして、何とか省庁と一緒になってやらせていただいております。ただ、その逆を考えると、全部が全部、市場になるとは思えませんが、可能性として2兆円の市場が待っているのだという前向きな捉え方もありますので、そこは実は期待しているところでございます。
では、具体的にどういう海賊版被害に遭うのかという一つの例をお話ししますと、日本で毎週毎週コミック雑誌、「少年マガジン」とか「ヤングマガジン」とか「モーニング」とか出ますけれども、それらの発売前になぜかマンガが海外のオンライン上に出てしまうということが恒常的に起きています。
昨年11月、その犯行グループの一人が窃盗で逮捕されました。その際は、昨年の法改正でいわゆる電子出版権というものができましたが、その権利に対する侵害ということで捕まえることができましたけれども、まだまだイタチごっこというところです。
そんな中で、海外のファンの人たちの声を聞くと、日本の出版社がタイトルを出さないから悪いのだと。我々だって日本の読者と同じように毎週毎週本を読みたい、マンガを読みたいと。でも、実際海外にそれらの作品が流通するのは、たとえばマンガの連載が単行本になったあとに2~3カ月遅れで出るということで、非常に不満を持っておられた。海賊版はもちろん悪いことだと思うのですが、日本の出版社は海外出版には消極的で、海外のファンに冷たいとまで言われていたので、そこは何とかしなければいけないということで、2013年から私どもでは人気作品25タイトルを、国内のコミック誌を発売するのと同時にアメリカで配信を始めました。
その後、アメリカだけでなく、韓国、台湾、フランスなどでも雑誌の発売日と同じ日、同時に配信を行っています。
そこから結果論として思わぬ事態が起こりました。多少実験的な作品、言い換えますと海外では余り受けないだろう作品、紙では刊行しづらいなという作品を電子で配信したところ、結構アクセスが集まったのですね。例えば女性向けのコミックなどで言いますと、学園恋愛物、いかにも日本風なもの、2年ぐらい前だと「壁ドン」とかそういうものがはやりましたけれども、アメリカではそんなものは受けないだろうなどと思っていたら、意外とアクセスが集まったのです。さらにそれを紙で出してみたら非常に売れたということで、意外な効果、想定外の効果というものもあらわれてきています。ある意味海賊版がマーケットを広げておいてくれたということもあるかと思っております。
そのように正規版を積極的に投入していくということもありますけれども、一方で経産省さんと一緒にマンガ・アニメ海賊版対策協議会というものもやっておりまして、次から次へと海賊版サイトを見つけて、これをやめるようにという警告の作業を延々とやっているのですが、一向になくならない。講談社としても個別に海賊版対策に取り組んでいるのですが、年間千万単位のお金がかかっていて、やっていられないなというのが正直な気持ちです。今後は法的手段に出るとか、いろいろなことを考えて対応しようと思っていますけれども、基本的には正規版をどんどん投入していきます。同時に、海賊版サイトを徹底的に潰していくということをやっていきたいなと考えております。
(PP)
マーケティング、プロモーションというところなのですけれども、昨年サンフランシスコに講談社アドバンストメディアというものをつくりまして、電子書籍の配信とマーケティングを行っています。ここで何をやっていくのかというところで言いますと、当然のことなのですが、やはり英語で情報発信をしていかないといけないということです。日本語で幾ら情報発信しても、見てくれる人は見てくれますけれども、英語だと見てくれる人の数が違うということで、アメリカから全世界に向けて情報を発信していこうということを今進めております。
(PP)
画面の右のほうにウェブサイトがありますが、日本で我々が手に入れられる情報、我々しか手に入れられない情報です。要は、このように海賊版サイトでは見られないような情報をサイトに入れようということです。作家の裏話であったり、編集者の裏話であったり、そういったものをいろいろ入れていったところ、非常に大人気になりまして、これまでGoogle検索などで「講談社コミックス」などとやると、検索の上位に海賊版サイトがずらりと出てきたのが、やっと正規のサイトが海賊版サイトを超える、肩を並べることができたということで、そういったところが第一歩なのかなと思っています。
我々が日本で持っているコミックの販売のノウハウを携えて、電子コミックの販売ノウハウと、アメリカでIT系の企業と組んで会社を興したのですけれども、彼らIT系企業が持つ情報、新しいマーケティングの仕方とか、そういったものを駆使して世界に打って出ようということを考えております。
インターネットの普及、浸透によって全ての情報が一瞬のうちに世界に広まっていきます。結局のところ、そうなると、世界にファンがいると考えるよりも、ファンがたまたまいろんなところにいるだけだと考えて、日本に限らず、アメリカだろうと、フランスだろうと、タイだろうと、そういう人たちに我々が持っている情報、「おもしろくてためになる」というものを平等に同時に配信していく、同時にお知らせしていく、伝えていく。そういったマーケティングを何とか実現しようということで今、やっているわけです。そういったノウハウにしてもどんどん変わっていきますので、そのあたりも非常に大きな課題かなと思っております。
(PP)
最後にコストのことなのですけれども、これも非常に大きな課題です。先ほどインターネットの同時配信をやっていると言いましたが、毎週毎週締め切りぎりぎりにマンガの作家さんが原稿を入れてきて、そこから時間のない中で翻訳をし、それをまたクオリティーのチェックをするという作業をずっとやっていますと、時間の問題、労力、お金、これらのコストが非常にかかっています。実際、同時配信だけでは全くペイしないという側面があるので、そこで経産省さんのJ-LOPを積極的に活用させていただいております。
先ほど、正規版を同時配信で投入することによって海賊版対策にもつながると申し上げましたけれども、一方で、J-LOPのお金を使わせていただくことでマーケティングの活動にも十分つながっていますし、海賊版対策にもつながるということで、ぜひ引き続き多大なる御支援をお願いしたいと思っております。
その他の課題については、国ごとにいろいろあるのですが、たとえば中国などですと、新しいマンガが出るとすぐにその商標をとられてしまうということがあります。その商標をまた取り返すのに非常に手間がかかっています。さらにはお金もかかっています。言葉は乱暴ですが非常に面倒です。
あと、マンガに対して、中国ではなかなか出版の認可がおりないといういわゆるコンテンツ規制もございますし、ヨーロッパ等でも海外製アニメを制限する動きというものもございます。そういった課題に対して、我々だけでは解決できない部分において、ぜひ国のお力をおかりしたいと思っております。
最後になりますけれども、ここ10年ぐらい非常に積極的に海外展開をやってきたのですが、やってきたからわかったことと、やってみなかったらわからなかったことというのがあります。それらをひとつひとつ解決していって、結果的に売り上げとして大きいタイトルが出たり、出なかったりという経験をしながらビジネスを拡大することができました。
先ほども申し上げましたけれども、我々がみずから解決しなければいけない問題と、我々では本当にどうしようもない問題があります。2兆円の海賊版市場、被害というのは我々だけでは何ともならないですし、各国の規制の問題等とあわせて、ぜひ国レベルで御支援いただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○中村座長 どうもありがとうございました。
意見交換をしたいと思います。主な論点は、事務局が最初に説明をしてくれた資料1を参考にしてもらえればと思うのですけれども、主にポイントは2つだと思います。1つは、これまでの政府の仕事、施策をどのように評価するのか、検証するのかということ。もう一つは、民間と政府の今後の取り組みをどうするかということだろうと思います。
1つ目、政府から先ほどの説明がありましたように、これまで行ってきた取り組みや成果をどのように評価するのかということが1つ。もう一つが、いろいろと政策支援ツールはそろってきまして、民間にボールが投げられている状況でもありますので、民間として行うべきこと、その上で政府がすべきことは何なのかということを念頭に置いて意見をいただければと思います。意見、コメント、何でも結構ですので、お出しいただければと思います。いかがでしょうか。では、奥山さんからお願いします。
○奥山委員 奥山でございます。
非常に興味深いいろんなプレゼンテーションをありがとうございました。これまでの評価ということですが、もう数字が物語っているように思います。こういった成果が上がっていることをより多くの人に知ってもらうことも大事ではないかなと考えておりまして、私は幸いこういうところに座らせてもらっていろいろ勉強させてもらって、非常に役に立っているのですが、マスメディアその他を見回しても余り情報が流れてきていないという状況があって、中村先生の御本とかブログを拝見していますけれども、それ以上にもう少し広報をやらなければいけないのではないかなと思います。
今後のことなのですが、これはある一定の期間やらないとだめではないかなということは、例えば産学連携の事例などを考えてみるとよくわかると思います。TLOをつくったのですけれども、中途半端なところでいろいろがたがたしたということがあって、さはさりながら、十数年の成果が今、ここでいろんなふうに出てきていると感じておりまして、ですから、せっかくこれだけ勢いよく始めた事業ですので、10年、ひょっとしたらそれ以上のスパンで継続していけるように考えていただきたいと思います。
以上です。
○中村座長 ほかにいかがでしょうか。では、相澤さん、お願いします。
○相澤委員 政策として進められてきていることは評価できると思います。ただ、収益を上げるには正規品を積極的に展開していかなければならないので、その展開のためには、ファイナンスが重要です。そのための政策が引き続き進められるべきであると思います。
円滑に投資が行われるために、収益を上げるための政策的な努力をしていかなければならないと思います。
そこでは、コンテンツを流通させるときに、日本の法制度が障害になっていないのかということについても検討する必要があるのではないかと思います。アメリカでコンテンツが発展していることの背景の一つに、アメリカの法制度があると思います。したがって、コンテンツの発展のために、著作権法を含めた法制度の検討が必要です。
それから、先ほどの外務省による支援の中で、既に行われているかもしれませんが、在外公館が積極的に現地において、日本の企業の利益のために活動するということが重要であると思います。例えば、日本の在外公館でも、フランス大使館などは積極的にフランス大使館を使ってレセプションなどを行って、フランスの企業のためにフランス大使館が活躍しているという話を良く耳にします。日本大使館も在外公館においてそういう活動を積極的にやっていただくと良いと思います。
○中村座長 ありがとうございます。
では、森永委員、お願いします。
○森永委員 皆さんのデータと同じように、成果が上がっていることは明らかであります。問題は、この後、立ち上げたマーケットに対して二の矢、三の矢をどういうふうに撃っていくか。具体的に申し上げますと、東南アジアのミャンマーでは地上波の民間の放送局、MNTVというところに放送枠を確保して、民間企業のトヨタさんと三菱商事さんのスポンサーをつけて大河とか朝ドラを流すということをやったり、地方の民放さんの番組なども放送するということを1年目にやって、なかなかいい感じで立ち上がってきていて、地元の人々に対する日本でのようなイベントもやってきたわけですが、やはり1年目、かなりお金がかかって、持ち出しもありました。
1年目はBEAJさんの助成を受けたりしてやったわけですけれども、2年目は日系企業24社の協賛を受けて、ミャンマーの樋口大使、それから公使も非常に熱心に活動していただきまして、1年目に比べるとコストを削減しながら、皆さんの協力をうまく得て2年目に二の矢を撃っていこうと。三の矢、来年に向けてもそういう全体の補助金だけでなくて、いろんな方々の協力も得られながら、NHK、あるいは関連も含めてどういう形にやっていくかということを模索しつつやっております。
もう一つは、立ち上がってくると必ずライバルが出てくる。これがベトナムなのですけれども、ここはTBSさんがもともと熱心にやっておられたということもあるのですが、NHKも地元の国営放送の教育専門チャンネルの立ち上げについて要請がありまして、相談をしながら、コンテンツの許可とか、教育テレビの設備そのものを整備していくということをコンサルして展開をしていて、「大科学実験」を初め、さまざまな番組をベトナム語で放送されて、いい雰囲気になってきたのですけれども、これは個別名は削除していただきたいのですが、早速韓国のKBSさんがオール韓国の体制で、放送枠をスポンサーでつけて、事実上、向こうにとってはほぼ無償の形で出てきます。
だから、ミャンマーも、ベトナムでこういうふうに出てきましたけれども、マーケットがある程度立ち上がってくると、必ず出てくるだろう。そうしたら、それに対して、いつまでも最初の形でなくて、どういうふうに形を変えて官民一体でうまく展開していくか、これが今後の大きな課題だと思っております。
それから、先ほどもありましたけれども、技術が進んでいくにつれて、東南アジアでも欧米ほどではありませんが、2020年前後で放送のデジタル化をやります。早いところもあります。そうすると、放送とネットの権利をどうするかという問題が課題になってきていまして、既にタイとかベトナムではそういう課題がふえておりますので、そこの点も整理が必要かと思います。
最後に一言だけ。海賊版対策。それは放送の局もすごくひどくて、海賊版のいろいろ新しい認証の技術とか出てきていますので、その辺も取り込んだりしながら、政府間レベルでもどういう形を組んでそれを減らしていって、正規のものを出すという形に持ち込むかという3点が重要だと思います。
以上です。
○中村座長 ありがとうございました。
では、重村委員、お願いします。
○重村委員 海外展開事業を実際に行っている立場から、具体的なお話をしていきたいと思います。放送コンテンツに関して言うと、海外に出していく場合、2つ方法があると思います。1つは、日本のマーケットに向けてつくられた作品を海外に売っていくという形です。最近は日本の広告マーケットがシュリンクしていますから、各放送局も積極的に今やっているところです。そういう点では、民間は、海外展開に非常に熱心になってきていて、なかなか本当の数字を出しませんが、予想以上に日本の作品は出ていると思っています。
キー局に限らず、地方局も海外展開事業部門というものを持ちまして、北海道は非常に有名ですが、最近は福岡、広島、四国の局も海外展開事業部門を作って作品を海外に売るようになってきております。ただ、売るだけでは全く大したお金にならないわけですから、当然経済波及効果を考えて、いろいろな企業との連携をとって、そこで取り上げている内容を活かす
マーケットをつくりながらやっていくという形も広がっています。ここの部分は徐々にではあるけれども進んでいるなという感じがしております。BEAJ事業もその一つだと思います。
そこでお願いしたいことがあるのですが、今年は本予算がとれるかもしれないのですが、今までは補正予算でやっていたわけです。大変大きいお金をいただいているのですが、具体的に言いますと、予算がとれて、それで請負主体を公開入札して、それから企画を決めるという段取りになると、実際に企画を採択するというのが8月末から9月になるのです。日本の場合、そういう予算というのは単年度予算でやらなければいけないわけですから、10月-3月の間で番組を流してください。なおかつ、検証評価も3月までの間に出してくださいとなります。
BEAJでは、年が明けてから毎週採択した局の方を呼んでヒアリングをして、トレーラーも見たり、中身も見たりしているのですが、各社が一様に言うのは、これは全く無理な計画ではないかと。なぜかといいますと、10月から放送するのに、9月の段階でオーケーになっても、普通、物をつくる場合は、対象国の局のニーズを聞いて、こちら側の企画とマッチングさせていくという作業をやるわけです。そうなると、相当急いでも12月の末から1月の頭から実際に現地で放送が始まるという状況になるわけです。
一番大きい問題は、こういう番組ですと、国内でも国外でも自治体であるとか企業は一緒に協力していろんなことをやりましょうという話にはなります。ところが、おわかりだと思うのですが、大体予算というのは年初に決めるわけです。だから、やりたいのだけれどもお金はありませんという形になる。
特に東南アジアの国などの場合は、日系企業、例えばジャカルタならJJCみたいな商工会が非常に強いのですけれども、ほとんど秋以降の段階では使えるお金がありませんという問題が出てくる。
もう一つは、今、各自治体ともインバウンドのためにいろんなイベントをやるわけですが、このイベントも海外でやるケースというのは年度頭に決めていますから、放送が決まった段階でそれとマッチングさせることが非常に難しい。
なおかつ検証・評価の問題になると、どういう形でやるか。いろんな方法を考えてやっているのですが、これも1月から放送が始まって、3月までにその結果を出しなさいと言われても、なかなか正確な数字というのは出てきません。
先ほど豊嶋課長もおっしゃっていましたが、そこの中で非常に重要な部分というのは、日本の情報が海外に出ることによって、日本の商品が動いたり、観光客が日本に来るという具体的数値を出さなければいけないのですけれども、これははっきり言えば非常に長いレンジの中で見ていかなければいけないわけです。だから、継続性の中で見ていくべきです。こういうものに関して検証・評価をどういう形で行っていくか。すなわち、日本の会計年度の中で全て物事、決着をつけるという問題ではなくて、個々のケースに応じて考えていかなければいけないのではないかと思っています。
例えばちょっと冗談的に言うと、タイの放送局の人間に言われたのですが、日本の紹介番組というのは最近、大変よくできてきている。なおかつタイの放送局が非常に喜んでいるのは、BEAJ事業では、タイの放送局の人間に来てもらって制作をする。日本側の局がそれをサポートして日本の放送ノウハウを向こうに渡していくという形をやっているわけです。そういう点では評価も高いし、レポーターもその国の人間なのですが、問題は、このシステムでは、「日本が紹介されるのはいつも秋から冬のシーンばかり」という話になる。
ある日本のネットワークは東北をテーマにしています。東北というのは夏祭りが有名ですが、この方式では全く紹介できないわけです。紹介してもそれはアーカイブを使うことになります。
やはり一番影響力があるというのは、向こうの有名なタレントが来てその場にいるということが大事なわけです。
ベトナムもVTVの話もありますが、ホーチミンTVとの間は、大阪の局がやっているという形で、バラエティーに富んだ日本の番組の出方をしているのですが、問題は日本の大手の旅行代理店と現地の旅行代理店が組んで、この番組で見た場所をツアーするということを組もうとしたのですが、1月から放送を開始して3月に終わるわけです。そうすると、本来で言うとちょうど今、春節、テトの時期が旅行客が多いのだけれども、まだ放送をやって間もない。そのため、2月の末から3月となると、現地の旅行代理店から客が全然集まらない。できれば4月以降、桜の時期にしてほしいという話になるわけですが、こうなると、これまた我々のレンジとちょっと違ってくる。こういうところを具体例でもって考えていかなければいけないだろう。
先ほど野間さんから「やってみなければわからない」という話がありましたが、全く同感だなと思うのは、イスラム系の国の「ハラル規制」が一昨年、去年とだんだん厳しくなってきています。ハラルマークであるとか、日本国内がイスラム観光客を受け入れられるような体制をつくってほしいということが言われています。
ハラルの問題というのは、日本の有名店を紹介したときに、豚や何かを料理した食器を使わないで、別のフライパンで調理しているかどうかの検証をしてくれとか、いろいろ言ってくるわけです。我々は、そういう部分も情報をきちんと上げながら、毎年こちらがシステムを変えていかないといけない。
もう一つ、「プロダクトプレイスメント」に関してです。我々の側から言うと、そういう番組の中にうまく商品を取り込んで紹介するというふうに考えますけれども、国によってはそこをチェックして、それは広告であるとして広告料を払えという要求を出してきます。
いろいろたくさん申し上げましたが、情報を常にお互いに共有していく作業をやっていかないと、これだけの税金を使ってやっている事業が実効性を持ってこないのではないかというのが私の実感です。
以上です。
○中村座長 どうぞ。
○佐田委員 山口大学の佐田です。
今、ちょうどイスラムのハラルの話題が出ましたので、少し関連することです。大学で知財の授業をやっている中で、コンテンツの権利処理の問題とかを学生にも、今少しずつ考えさせているのですね。そのときに、コンテンツ問題を検討している委員会があるということを学生に伝え、日本の放送の番組で海外で売れそうなものはどんなものがあるかということを、特に留学生に聞いてみました。NHKでやっているような大河ドラマとか朝ドラとか、そういうものに丸がついてくるかなと思ったら、×がついたのがあったのです。それはどういう理由かと聞きましたら、去年の暮れの年末恒例の番組でした。ご覧になって記憶がある方もおられると思いますが、裸で出ていた芸人がおられましたね。完全な裸ではないのですが、学生のコメントとしては、イスラム圏では、その学生はイランからの留学生で、そんな映像はだめです、こういうのは一切放送できませんというのです。これは本当なのかどうなのか、意見というよりも質問をしたかったのです。
学生からそういうコメントが来て、先ほどたまたまイスラム圏のハラルの問題が出ましたが、コンテンツ問題は、それが本当なら権利処理の前に文化処理が必要ではないかなと思った次第です。要するに、その国の文化を何も知らないで、しかしながら日本の放送界を引っ張っていくようなところの局が、そういうことを知らないわけはないと思うのですが、もしその番組をそのままその国に持っていったときに全然だめと言われたら、せっかく皆さんの受信料でしかも大きな経費を掛けてつくっている番組が、その価値が霧散してしまうとは、コンテンツの海外展開を推進しようとしている中で、実にもったいない気がします。こういったコメントは失礼かもしれませんけれども、裸の芸人を出すか出さないかはプロデューサーの考えでしょうが、国挙げてコンテンツ事業の展開を図ろうとしているのであれば、そういった観点からのチェック体制はどうなんだろうかとか。また結果として霧消してしまった場合には、それぞれのプロデュースされている方々のところに今回のような教訓となる情報が共有できる仕組みが必要ではないだろうかと思ったしだいです。何となく気になったものですので、学生達には調べてみるということでお茶をにごしたところです。学生はこのような問題には特に関心を持っていますので、また機会があったら、いろいろと情報をいただければありがたいと思います。
○中村座長 では、瀨尾さんと林さんの順でお願いします。
○瀬尾委員 大分いろいろ素材が出てきたという感じがあると思います。
実際に海外、いろんな展開が出て、いろんな欠陥を今のようにフィードバックがあったりしていいと思うのですが、一つ申し上げたいのは、今、データベースや何かをいろいろやっているのですが、大分データベースも権利所在データベースとしてあちこちできてきているのですけれども、やはり連携が足りないと思います。例えばこの前、音楽の処理についてJASRACさんともいろいろお話をしたのですが、例えばJASRACさんなどは膨大な音楽データベースを整備されて持っていらっしゃるのです。これをきちんと連携していくと、例えばユーザーはかなり簡便に処理をできるようにもなっていけると思いますし、いろいろ複合したコンテンツを処理するときにも、単独でデータベースができているし、データベース自体が散発的かつ短命であるような場合が多い。つまり、インフラとしてデータベースを、公でも構わないし、どこでもいいのですけれども、きちんとしたコンセプトで広げていかないと、局所的なデータベースが幾らあっても、これは余り意味がなくなってしまう。例えばナショナルアーカイブのようなことを考えたときにも、基本的に権利所在データベースは必要になりますから、今、それが非常に多くできてきているのに、連携がいまいち不十分であるというところは大変もったいないと思います。
ですので、海外展開をしていくためのインフラとしてのデータベース、その連携を例えばインターフェースであり、APIをきちんと確保するなり、そういうことを確保した上で展開していくということを、これだけ出てきているのだから、もうそろそろ全体的な視野からやったほうがいいのではないかと思います。
もう一つは、ジャカルタにしてもパリにしてもテロがございました。人の集まるところとか、一般の方を巻き込んだようなテロが多発しております。これは非常に残念なことではありますけれども、その中で日本がテロの起きていない場所、観光として注目されているというところは現実問題としてあると思います。今、日本に対する興味が非常に高まっている時期なので、インバウンドについては、単純に地方のコンテンツを流して、地方に来てくださいというのではなくて、もっと日本という国の宣伝としてやはりこれも連携していくべきではないかなと思っています。
総じて申し上げますと、データベースにしても、施策としても、各省庁さん、経産省さんも総務省さんも外務省さんもなさっていらっしゃることは成果が出てきている非常にいい時期にありますので、これをうまく連携させて、そしてより効果を相乗化させることと、データベースも施策もして、インバウンドについて、地方の方たちの体系的な戦略として観光を進めていったら今、効果が上がるように思います。実際にデータベースでいろんなことを運用している中で、今、日本のインバウンドは大変可能性があって、これは2020年に向けて右肩上がりでいけるチャンスだと思いますので、データベースとインバウンドについては連携してやっていくことが重要かなと考えました。
以上です。
○中村座長 林委員、お願いします。
○林委員 ありがとうございます。
検証・評価というこの会議において、本日、経産省、総務省、外務省からこれまでなさってきたこと、また、今後の補正予算や平成28年度予算での施策について御紹介いただいたわけですが、既に委員からも多数詳細なお話がありましたように、単年度予算のもとでの補助金という枠組みのもとで、成長戦略の一つであるコンテンツの海外展開を図っていくという政策を実現するのは無理がある。これをこの検証・評価の中で確認できないものかと思います。
では、どうすればよいのか。今まで、どうしても予算の枠組みから補助金でやらざるを得ず、各省、課題はわかりながらもここまで来ていると思うのですが、事ここに至っては、そのようなスピードでやっていては効率的な政策実現が図れないことは明らかなので、抜本的にあり方を見直すべきであると思います。少なくとも3年の中期計画なり5年の計画を立て、どのように限られた政府予算をここに投じていくのかということを考えなければいけないと思います。
ところで、先ほど、クールジャパン機構、正式名はクールジャパンファンドではなく、株式会社海外需要開拓支援機構でございますが、についてお尋ねがありました。いわゆるファンドとして捉えますと、やはりエグジット段階での収益率が幾らかということが論点になってくると思います。
私、実はクールジャパン機構の関係者でございますので、少しお話しさせていただきたいと思うのですが、もちろんリスクマネー、大事な税金を投ずる以上、エグジット段階での収益性が確保できなければ投資できません。既に13件投資しており、コンテンツ以外のものもこの3月から5月ぐらいにどんどんLA、ロンドン、パリ、さまざまなところで実際に目に見える形での出店が続きます。そういった形で手がたくやっておりますが、さはさりながら、政策実現のツールとしてこの機構のあり方を考えると、いわゆるファンドで収益を上げるものとは性質が違う面もあります。
今日の資料2-1の「クールジャパン機構の投資決定案件」で紹介されている案件はいずれも、本来であれば国が政策として行うべきもの。例えばSDIの買収につきましても、言語の壁を乗り越えて日本コンテンツを発信するためには、ローカライズの基幹インフラが必要であるために世界最大と言われるSDIを買収したわけでありますし、それ以外にも人材育成とかテレビ番組、特に「WAKUWAKU JAPAN」などの放送チャンネルを展開しているわけですので、収益性だけではなく、政策波及効果がKPIの大きなベンチマークになっているということも御理解いただきたいと思います。これが1点目でございます。
2点目なのですが、ただいまデータベースのお話がありました。まさに情報を共有化、横串を刺すという意味では、データベースの点は非常に重要だと思います。使われていないデータベースとしてJASRACの件もございましたが、私が個人的に思いますのは、NHKの件です。公共放送の受信料収入としてNHKは毎年約6,000億円を得ており、その結果、NHKは既にデジタルマスターの処理をしたコンテンツを50万タイトル持っているそうです。いわば埋蔵金、埋蔵タイトルと言ってもいいかと思うのですが、その蛇口が開くかどうかは今、NHKに委ねられております。例えばWAKUWAKUチャネルや外務省の国際交流基金などを通じて、さまざまな国際発信するときのコンテンツとして、NHKが持っている50万件のデジタルライブラリーを使えないのか。海外の番組でも歴史番組やサイエンス番組があったりしますが、NHKの優良なドキュメンタリー番組など、歴史的価値があるものもございますので、この埋蔵コンテンツの活用もぜひ御検討いただけないものかと思います。
以上です。
○中村座長 喜連川さん、お願いします。
○喜連川委員 JSPSの科研費というのが今、2,300億ぐらいの規模で大学の研究者等に配分されているわけですけれども、その中で一番大ヒットしたのが研究予算の繰り越しだと思います。つまり、諸般の事情で年度の中で消化しなくてはいけないという制約は物すごく大きくて、これのリラクセーションは、研究者にとっては本当に涙が出るほどうれしいような状況ですので、政府の多様な補助金に対していろいろ緩和ができれば、これは国益に非常に大きく資するのではないかということを1点申し上げたいと思います。
それから、日本データベース学会の役員として申し上げますと、データベースを統合するというのは、実は思ったより物すごく大変なことでございまして、結構地道なことをきっちりきっちりやっていく必要があります。したがいまして、私は瀨尾先生の御意見に大賛成なのですけれども、これは一朝一夕には絶対いきませんものですから、セマンティクスからオントロジーから、ありとあらゆるものがかかわってきますので、これもぜひじっくりと取り組んでいただければありがたいと感じます。
以上でございます。
○中村座長 どうもありがとうございました。
では、このあたりで本日の会合を閉会したいと思います。
最後に、今日の議論について知財事務局長から総括いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○横尾局長 いろいろ御議論いただきまして、ありがとうございます。コンテンツの海外展開はかなり進んできたという前提で、ある意味次のステージを考えていく時期かなと今日の議論を伺っていて思いました。
今、最後に議論になった、特に年度、予算のあり方というのは、たしかJ-LOPも前はファンドだったのですね。違いましたか。○横尾局長 基金形式だったので、もう少しフレキシブルだったのが、単年度予算化にむしろ変えられた経緯があるので、それはなかなか難しい問題なのですけれども、何ができるかというのは引き続き考えていかなければいけないですし、例えばこれは使えるかどうかわかりませんが、独立行政法人の交付金だと、もうちょっと使い方がフレキシブルだというのはあるので、そういうことも考えるかもしれないですし、仮に単年度予算でも、今、各省の運用がどうなっているかあれですけれども、4月になる前から事実上手続を開始できるはずなので、もうちょっと前倒し。私が前、予算を執行したときは、少なくとも衆議院を通っていればいいのではないかということで、手続を進めた。それが今、可能かどうかわかりませんけれども、何か工夫ができるのか。だんだん細かい議論になってきますが、その辺も考えたほうがいいのかもしれないです。
クールジャパン機構については、人によっていろんな議論があるのですが、全体としてクールジャパン機構としてプラスならいいのではないか、個別のプロジェクト全てについて常にプラスのリターンがあるように考えなくていいのではないかという議論は常にあります。だから、そこはどこまでクールジャパン機構としてフレキシブルにできるのか、これもテーマかなと思っています。
データベースについては、確かに連携が重要だと思いますが、専門家の喜連川先生からそう言われるとなかなか難しいのかもしれませんが、ここはスタディーしてみる必要があろうかなと思っている次第でございます。
いずれにせよ、一定の成果がかなり上がっているという中で、次の一歩をどうするか、引き続きいろんなお知恵を拝借できればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○中村座長 では、次回の会合について、事務局からお願いします。
○永山参事官 次回のこの会合につきましては、3月22日火曜日の10時から。検討テーマとしては「コンテンツ制作基盤の強化」ということで開催させていただきたいと思っております。会場など詳細については決まり次第、また事務局から御連絡をいたします。
○中村座長 では、閉会いたします。
どうもありがとうございました。