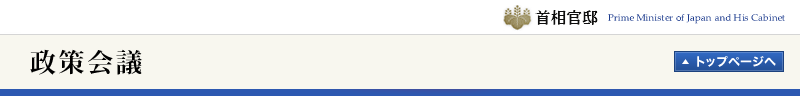������m���V�X�e�������ψ���i��S��j
�c �� �^
�� ���F����28�N1��27���i���j16:00�`18:20
�� ���F�����������ɂS���� 1208���ʉ�c��
�o�ȎҁF
- �y�� ���z
-
�����ψ����A�ԏ��ψ��A���ψ��A�T��ψ��A��A��ψ��A���ψ��A
�����ψ��A����ψ��A���z�ψ��A�R���ψ��A��c�Q�l�l
- �y�����ǁz
- �����ǒ��A���c�����A�c��Q�����A�i�R�Q�����A����Q�����⍲
- �J��
- �Z�p�v�V�ɂ��V���ɐ�������̎戵��
�i�P�j3D�v�����e�B���O�ɂ����̂Â���v�V�ƒm�����x
�i�Q�jAI�ɂ���Đ��ݏo�����n�앨�̎戵�� - ���̑�
- ��
�������ψ��� ����ł́A�F�l�����낢�ł��̂ŁA������u������m���V�X�e�������ψ���v�̑�S�����J�Â������܂��B
�䑽�Z�̂Ƃ��남�W�܂�����������܂��āA���肪�Ƃ��������܂��B
�{����o�Ȃ��������Ă���ψ��͍��ȕ\�ɔz���Ă���Ƃ���ł��āA�{���͊�A��ψ��A�c���ψ��A�{���ψ��A����ψ��͌䌇�ȂƂ̂��Ƃł��B
���ꂩ��A�{���́u3D�v�����e�B���O�ɂ����̂Â���v�V�ƒm�����x�ɂ��āv�̋c�_�Ɋւ��܂��āA������ЃJ�u�N�̈�c�l�Ɍ�o�Ȃ����������Ă���܂��B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
�ł́A�c���ɐ旧���܂��āA�m�������ǒ�����䈥�A���������������Ǝv���܂��B�����ǒ��A���肢�������܂��B
�������ǒ� �x���Ȃ�܂������A�F�l�A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�{�N���A�ǂ�����낵�����肢�������Ǝv���܂��B�N���̍ŏI��́A��ς����f�B�X�J�b�V�������ł����ȂƎv���Ă���܂��B���N���ǂ�����낵�����肢�������Ǝv���܂��B ���T�u�Y�Ƌ����͉�c�v�Ő����헪�̐i���̂��߂̍���̌������j�����肳��A���̒��Łu��S���Y�Ɗv�����i�^IoT����̐V���Ȑ��x�������v���ŏ��ɏo�Ă��܂��āA�C�m�x�[�V�����A�x���`���[�n�o�̋����A���̂��߂ɑ�S���Y�Ɗv���ɏ�������IoT�A�r�b�O�f�[�^�AAI���̎Љ���{���i�ނɂ�Č��݉�����m�I���Y��̖��_�͂���B���ꂩ��A���x�E���[���̐����Ƃ������Ƃ������헪�̌������j�ɂ����荞�܂�Ă���܂��̂ŁA���������Ӗ��ł́A���Ѝ���̋c�_������ɐ[�߂Ă�����ȂƎv���Ă���܂��B
�܂��A���ۓI�ɂ�WIPO�̔N��ō�N11���ɏo���A�{���̃e�[�}�ł�����ǂ�3D�v�����e�B���O��AI�̘b�������G��Ă��܂��B���ɁAAI�̓��{�b�g�Ə����Ă���܂�����ǂ��A�܂������̋c�_���Ƃ������ƂŁA���������Ӗ��ł͉�X�̋c�_�����Ȃ����s���Ă��邩�ȂƂ����C�͂��Ă���܂��̂ŁA���АϋɓI�Ȍ�c�_������������Ǝv���܂��B�ǂ�����낵�����肢�������Ǝv���܂��B
�������ψ��� ���肪�Ƃ��������܂����B
�ł́A�c���Ɉڂ�܂��傤�B
�܂��A�����ǂ���z�t�����̊m�F�����肢���܂��B
������Q�����⍲ ����ł́A�{���̎����ł����A�����Ƃ��ĂT�_��p�ӂ��Ă���܂��B
�����P�Ƃ������ƂŁA3D�v�����e�B���O�Ɋւ��鉡�u���̃X���C�h�����B
�����Q�Ƃ��܂��āAAI�Ɋւ��铯�������u���̃X���C�h�����B
�����R�Ƃ��āA�ԏ��ψ�������o���������Ă��܂��X���C�h�����ł������܂��B
�܂��A�����S�Ƃ��āA�c�u���̃X�P�W���[���Ɋւ��鎑���B
�Q�l�����P�Ƃ��āA�{����舵���e�[�}�Ɋւ��邱��܂ŏo���ӌ����������̂��������Ă���܂��B
�����ɂ��Ă͈ȏ�ł������܂��B
�������ψ��� ��낵���ł��傤���B
�ł́A�c��ɓ���܂��B����e�_�̂Q�ԖځA�Z�p�v�V�ɂ���ĐV���ɐ�������̎�舵���ɂ��Ă̋c�_�Ƃ������ƂŁA�{���͐�قNjǒ����炨�b������܂����悤�Ƀe�[�}���Q�ł��B3D�v�����e�B���O��AI�B���̘_�_�̂P�ځA�u3D�v�����e�B���O�ɂ����̂Â���v�V�ƒm�����x�v�ɂ��āB����͎����ǂ���_�_�ɂ��Đ��������肢�ł��܂����B
������Q�����⍲ ����ł͌���������Ă��������܂��B���茳�����P����������������Ǝv���܂��B
�����P�̍\���ł����A�O���ŁA3D�v�����e�B���O�ł��̂Â��肠�邢�͎Љ�ǂ��ς�邩�Ƃ����T�v�����Ă������܂��B�܂��A�㔼�ŁA���ꂪ�m���V�X�e����ǂ̂悤�ȉe����^���邩�Ƃ����_�_�����Ƃ�������ɂȂ��Ă������܂��B
����ł́A�O�����炩���܂�Ō���������Ă��������܂��B
�܂��O���Ƃ��āA���̂Â���v�V�Ƃ������Ƃł������܂����A�R�y�[�W���������������B3D�v�����e�B���O�ł��̂Â��肪�ǂ̂悤�ɕς�邩�Ƃ������Ƃɂ��ẮA�傫���Q�̕������ŕς��ƌ����Ă���܂��B�P�́A��蕡�G�A���t�����l�̂��̂Â��肪�ł���悤�ɂȂ�Ƃ������ƁB������́A�l���܂߂����L����̂ɂ��̂Â��肪�g�傷��ƌ����Ă�����̂ł������܂��B
���̃y�[�W���玖��������Љ�Ă���܂��B
�S�y�[�W�A�T�y�[�W�Ƃ������Ƃŕ��G�Ȃ��̂Â���Ƃ������ƂŁA�悭�Ȃǂɂ��o�܂��G���W���̓������i�̈�̐��`�ł��Ƃ��A���邢�̓C���X�g������܂����S���V�~�����[�^�[�Ƃ������ƂŁA���G�ȓ����\���������̂�3D�v�����e�B���O�ł����悤�ɂȂ�Ƃ����̂��P�̕������ł������܂��B
�U�y�[�W�A������̕������A���̂Â���̐���̊g��Ƃ������Ƃł������܂��B������ɂ��ẮA�f�[�^������A����������̂����邱�Ƃ��]�����e�Ղɂł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃł������܂��āA�l���܂߂ăA�C�f�A�������Ă���l���������̂Â���ɎQ�����₷���Ȃ�A�C���f�B�[�Y���[�J�[���o�Ă��邾�낤�Ƃ����悤�Ȍ����݁B
���ƁA3D�f�[�^�����L���āA�A�C�f�A�����L���Ă��̂Â��������Ƃ��A�X�l�̃j�[�Y�ɑΉ��������̂Â��������Ƃ������悤�ȐV�������̂Â���̓��������҂���Ă���܂��B
�V�y�[�W�ɂ����܂��āA���̂悤�ɂ��낢��Ȑl�����̂Â���ɎQ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��ƁA������Ȃ���Ƃ������̂��d�v�ł���A���W���Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���܂��B���ۂɃv���b�g�t�H�[���Â���Ƃ����̂́A�����O�ɂ����ăA�����J�̊�Ƃ��������܂����A���{�̊�Ƃ����g��ł���Ƃ���ł������܂����A�����������v���b�g�t�H�[���Â���Ƃ������Ƃ������o���Ă���ł������܂��B
�W�y�[�W�ł����A������3D�v�����e�B���O�S�̂ɂ��Ăǂ������ۑ肪���邩���A�m�������łȂ��đS�̂��ȒP�ɐ����������̂ł������܂��B
�܂��A�Z�p�I�ɂ����҂͂����̂ł�����ǂ��A���̒i�K�ł���Ȃɉ��ł������킯�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�Z�p�I�ɂ܂��܂��ۑ肪�����˂Ƃ����Ƃ���B���ƁA������g�����Ȃ��l���܂��܂��K�v����˂Ƃ����悤�ȁA��ՂƂ��Ẳۑ�͂���킯�ł����A���ꂪ������B������Ă������ŁA3D�̋Z�p���Љ�Ƃ��Ďg���Ă������̊�ՁA���x�̈�Ƃ��Ēm�I���Y���ǂ�����̂��Ƃ������Ƃ́A�����Ζ���N�������̂ł������܂��B�{�ψ���ł́A���̊������̒��̒m�I���Y�ɂ��Č�c�_���������������ƍl���Ă���܂��B
�����܂ł�3D�v�����e�B���O�Ɋւ��铮���̊T�v�ł������܂��āA11�y�[�W���炪�{���̘_�_�ɂȂ��Ă���܂��B
�_�_��������ŕ�����Ă���܂��̂ŁA11�y�[�W�ɂ͑��_�Ƃ������ƂőS�̂����Ă������܂��B�܂��A�ǂ������ω����\�z����邩�Ƃ������ƂŁA���K�i��3D�f�[�^����ė��ʁE���Y���邱�Ƃ��e�ՂɂȂ����ŁA���R��������p����A�͕�i�𗬒ʂ����萶�Y����Ƃ������Ƃɂ��g����\��������B
������_�Ƃ��āA�V�����`�̂��̂Â���A�A�C�f�A�����L����A�l�̃j�[�Y�ɍ��킹�����̂Â���Ƃ��������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�����������Q�̑傫�ȕω�������̂��Ȃƍl���Ă���܂��B
���̕ω���m���Ƃ��Ăǂ̂悤�ɑΉ����Ă������l���鎞�ɁA������Ɠ��̐����Ƃ��ĂQ�ɕ����čl����̂���낵�����ȂƎv���ċL�ڂ��Ă���܂��B
�܂��A���Ƃ��ƒm�I���Y����������̂ɂ��Ă�3D�f�[�^�̗����p���邢�͕ی�Ɋւ���c�_�ƁA���Ƃ��ƕی삳��Ă��Ȃ��悤�Ȃ��̂ɂ��Ă��A��������낢��Ȑl�����R�Ɏg�������ł��Ƃ��A���邢�͂܂������̂������������₷���Ȃ�Ƃ������`��3D�̋Z�p���e�����Ă��镔��������ł��낤�Ƃ������Ƃɂ��āA�ł́A�ی�E�����p�Ƃ����̂͂ǂ��������ƂɂȂ�̂��Ƃ������̐��������Ę_�_������Ă��������Ă���܂��B
12�y�[�W����́A���ꂼ��̊e�_�ɂ��Ă̌�����ɂȂ�܂��B
�܂��A�m�I���Y���ŕی삳��Ă���ꍇ�ɂ��āA3D�f�[�^�̖@�I�ʒu�Â����ǂ��l���邩�Ƃ������Ƃł������܂��B
��̎l�p�͂��ł����A�܂��A���̐��x�̌�����Ƃ��āA�m�����ŕی삳��Ă�����̂������Ȃ����Y���ꂽ�ꍇ�ɁA���̐��Y�s�ׂ₻���Ƃ����s�ׂ͌����N�Q�s�ׂɊY������Ƃ������ƂŁA���̃C���X�g�̉E���̐Ԏ��ŏ����Ă��镔���ł������܂��B
�����A�Ԏ��ŏ����Ă��镔���̑O�i�K�̂Ƃ���A�f�[�^�̌`�ł̗��ʁE���Y�����₷���Ȃ邱�Ƃ�\������ƁA�O�i�K�A���Ԓi�K�̉��F�ŏ����Ă���Ƃ���ɂ��Č������y�Ԃ��Ƃ��K�v���ǂ����A�������������Ƃ�����l���Ă����K�v�����邩�ǂ����Ƃ����Ƃ��낪�A�P�ڂ̘_�_�Ɛ��������Ă��������Ă���܂��B
���̉��̃A)�A�C)�Ə����Ă���̂́A���s�@���Ɋ�Â������ł����A����������߂ł�����\���͂��邯��ǂ��m��͂��Ă��Ȃ��Ƃ����̂��A�ӏ��A�������邢�͒��쌠�ŕی삳��Ă�����́A������̏ꍇ�����s���̂悤�ɂȂ��Ă���܂����A�ی���y�ڂ��Ƃ����ϋɓI�ȕ����Ɏ����Ă����̂��悢�̂��A�����ł͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��낪�P�ڂ̋c�_�̃|�C���g�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B
14�y�[�W�́A�O�̃y�[�W�Œ��ԓI��3D�f�[�^��������Еz����s�ׂɒm�������y�ԂƂ��������u�����ꍇ�Ƃ����c�_�ł������܂��B�ی삪�y�ԂƂ����ꍇ�ɁA���̕ی��������x�����I�Ȃ��̂ɂ���Ƃ����ϓ_�ŁA���ʂɊW���邢�낢��ȃv���[���[�A�ǂ������������ʂ����ׂ����A�S�̂Ƃ��Ăǂ������d�g�݂��u���Ă����K�v�����邩�Ƃ������ƂŁA�f�[�^�𐧍삷�鑤�ł̎��g�݁A�Ⴆ�A�f�[�^�𗬒ʂ���ۂɕ������h�~�[�u���u����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��l������̂ł͂Ȃ����B
���ƁA���Ԃ̎��ƎҁA�v���b�g�t�H�[�}�[�ł��Ƃ��A�v�����^�[�����l�Ȃǂ��z�肳���Ǝv���܂����A���������������N�Q�Ɋւ���ӔC�𐧌����ꂽ��A���邢�͖h�~�`�����ʂ����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ǂ̂悤�ɍl���邩�B
�Ō�ɁA���[�̗��p�ҁA���[�U�[�̗���Ƃ������ƂŁA��@�s�ׂ�}������Ƃ����ϓ_����A���炩�̑�A�Ⴆ�Β��쌠�ł���Ă���_�E�����[�h�͈�@���݂����Ȃ��Ƃ��l������̂��ǂ����Ƃ������悤�ȑI���������������Ă���܂��B
15�y�[�W���A�ی�Ɨ����p�̃o�����X�Ƃ������ƂŁA�ی삵�Ă������肻������Ƃ������Ƃ͓��R�d�v�Ȃ��Ƃł͂���̂ł����A����Ɨ����ł�������g����悤�ɂ���Ƃ������Ƃ��厖�ɂȂ��Ă���B���̎d�g�݂��ǂ̂悤�ɍl���邩�Ƃ������_�ł������܂��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A3D�f�[�^�����L�E���H���邱�Ƃł��낢��Ȃ��̂Â��肪�o�Ă���Ƃ����Ƃ���A���邢�̓��[�J�[������Ȃ��Ȃ����ߋ��̏��i���O�҂��Đ��Y����Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ��A3D�ɂ���Ă��₷���Ȃ�Ƃ������Ƃ������Ă���܂��B�����������j�[�Y������̂Ŏ����I�ɎЉ�i�ނƂ����Ƃ���͂���܂����A������~���ɐi�߂�Ƃ����ϓ_����A�m���Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȏd�g�݂��u���Ă������Ƃ��l�����邩�Ƃ����̂��_�_�ł������܂��B
����A�C�f�A�Ƃ��āA���C�Z���X�\���ł��Ƃ��A���s�̖@���́u�ƂƂ��āv�v���ł�����̂��ǂ����Ƃ��������Ƃ��������Ă��������Ă���܂��B
16�y�[�W�A17�y�[�W���܂���̕ʂ̌ł܂�Ƃ������ƂŁA���܂ł͌�����������̂��f�[�^�ɕς�������ɂ��̈������ǂ����邩�Ƃ����c�_�������̂ł����A16�y�[�W�A17�y�[�W�́A���Ƃ��ƌ������Ȃ��悤�Ȃ��̂ɂ��Ă�3D�f�[�^�̎�舵�����ǂ����邩�Ƃ������_�ł������܂��B
�ŏ��̘g�ł����A�ی삳��Ă��Ȃ����̂����Ƃ�3D�f�[�^���������̂�����A����͎��R�ɗ����p�ł���ƍl���Ă悢�̂��ǂ����B��̍H���Ƃ����̂͊��S�Ɏ��R�ł����̂��A���邢�͂��������ʂ̉������K�v�Ȃ̂��Ƃ��������_�ł������܂��B
�܂��A���Ƃ��Ƃ̃��f���ɉ��猠�����Ȃ�����Ƃ����āA3D�f�[�^�ɂ������ɁA����3D�f�[�^�ɂ����猠�����Ȃ��̂��A���邢�͉����ی삪�K�v�Ȃ̂��ǂ����Ƃ������Ƃ��낪�Q�ڂ̎��_�ł������܂��B����3D�f�[�^����ɓ������Ă͍��x�ȋZ�p�I������H�v���ꍇ������ƌ����Ă���܂��āA�����������s�ׂ�m�����x��ǂ̂悤�ɕ]�����邩�Ƃ������Ƃł������܂��B
�ŏ��̎��_�A���R�ȗ��p���������ǂ����Ɋւ��ĉ��̕����ŁA���s�@���Ɋւ���ی�\���������Ă���܂����A�܂��A���p�ɂ��Ă͕s�������h�~�@�ŃC���X�g�̈�Ԓ[�̂Ƃ���A�����悤�Ȃ��̂������Ĕ���Ƃ����Ƃ���ɂ��Ă͕ی삪�y�ԁA������ɂ߂Ċ��Ԃ�������Ƃ�������I�ȋK���ł͂���܂����A�����������\��������B���Ԓi�K�̂Ƃ���͂ǂ����邩�Ƃ������Ƃ����낤���Ǝv���܂��B
�܂��A�Q�ڂ̘_�_�A���f������3D�f�[�^������Ƃ����Ƃ���ɂ��ẮA17�y�[�W�ł������܂����A���쌠�@�̍l�����Ƃ����̂��Q�l�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃŏ����Ă������܂��B����́A3D�f�[�^���v�}�ł���ƍl����A����ɒ��쌠���F�߂���̂��ǂ����Ƃ����c�_�ƑΔ�ōl���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł������܂��B
���A�v�}�Ɍ������y�Ԃ��ǂ����Ƃ����̂́A����ɂ���Ĕ��f���������Ƃ���͂���̂ł����A�P�̔���Ƃ��ẮA���ʂɏ����������ł͑n�쐫�͔F�߂��Ȃ�����ǂ��A�ȗ���������A�ڍׂɏ������邢�͑��݂��Ȃ������������ȂǁA�����n��I�ȍH�v���F�߂��Ă��鎞�ɂ͒��쌠��������\��������Ƃ������l������������������������܂��B�����������l������ϋɓI�ɍ̗p���āA3D�f�[�^�̂Ƃ���ɂ��Ă������V�����d�g�݁E�ی���l���Ă����K�v������̂��A���邢�͌��s�̂܂܂ł悢�̂��ǂ����Ƃ������Ƃ��낪�c�_�̃|�C���g�Ƃ��Č�p�ӂ����Ă��������Ă�����̂ł������܂��B
�����ǂ���̐����͈ȏ�ɂȂ�܂��B
�������ψ��� ���肪�Ƃ��������܂����B
�����āA���̘_�_�Ɋ֘A���܂��āA3D�v�����e�B���O�����p�������̂Â���̃l�b�g���[�N���Ɏ��g�܂�Ă��銔���J�u�N�̈�c�l����A�Z�p��r�W�l�X�̎��ԓ��ɂ��ăv���[�������Ă������������Ǝv���܂��B��c�l�A�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
����c�Q�l�l �����J�u�N�̈�c�Ɛ\���܂��B�{���́A�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
���傤�ǒ��߂ŁA�����P�̂܂���15�y�[�W�ڂł��傤���A���[�X�P�[�X�ɂȂ�悤�Ȏ��Ⴊ�������܂��āA����A�e���r��������́u���[���h�r�W�l�X�T�e���C�g�v�Ŏ��グ�Ă����������̂ł����A���傤�Ǎ��g���^����i-ROAD�Ƃ����d�C�����Ԃ��������Q�`�R�N�Ŏ��Ɖ��A�T�[�r�X��������Ƃ������Ƃœ����Ă���܂��āA�G�N�X�e���A�̃p�[�c�̂ł��Ƃ��A���̃C���e���A�̃p�[�c��ʏ�̃C�[�V�[�T�C�g�ł��ƁA�|�`�|�`�Ɖ����Ă����ƍŏI�I�ɂ͍ɂ��s�b�N�A�b�v�Ƃ��Ă��͂�����Ƃ������f�����A���̏ꍇ�̓|�`�|�`�Ɖ����Ă����ƁA�����Ŏ�����3D�f�[�^�����܂��āA���̐l��l��l�ɍ��킹���I�[�_�[���[�h�̃p�[�c���̔�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������ƂŊJ�������Ă��������Ă���܂��B����́A������}�X�J�X�}�C�[�[�V�����Ƃ����Ƃ���ł͂���̂ł�����ǂ��A���傤�ǂ��킹�ă����T�[�Y����Ƃ������{�̃N���E�h�\�[�V���O���̃x���`���[����Ƒg�܂��Ă��������āA������I�[�v���C�m�x�[�V�����^�A�l��3D�f�U�C�i�[�̕�����������ŁA�ڋq�j�[�Y�ɍ��������̂��I�[�v���ɂ���Ƃ������Ƃ����܂��Ɏn�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B�Ȃ̂ŁA�����������[�K���̘_�_�Ƃ����̂́A��X������Ȃ����ɘ_�_���o���ē����Ă����Ă���Ƃ����`�ɂȂ�܂��B
�Ⴆ�A�����������ꍇ�A�ǂ������r�W�l�X���f���ł�点�Ă��������Ă��邩�Ƃ����Ƃ���ł����A���Ђ�Rinkak�v���b�g�t�H�[���Ƃ����`�ł�点�Ă��������Ă���̂ł����A����������̏ꍇ�g���^����ɂȂ�ƁB���̎��ɃI�[�v���C�m�x�[�V�����^�ɂ��̂������Ă����Ƃ������ɁA������l�̃f�U�C�i�[������������݂Ȃ���g���^����̃p�[�c������ƁB���Ђ�3D�v�����^�[���[�J�[�ł��Ȃ��H��ł�����܂���B������3D�f�U�C�i�[��H����l�b�g���[�N�����Ă��������Ă���v���b�g�t�H�[�}�[�ł���Ƃ����`�ŁA�E���̍��͎Y�Ƃ�3D�v�����^�[���������̍H��l�����S�Ȃ̂ł����A�f�W�^�������H��l�ƃl�b�g���[�N�����Ă��������āA���������`�Ńr�W�l�X����点�Ă��������Ă��܂��B�ł��̂ŁA���Ђ̎��Ƃ́A������������IT�T�[�r�X�ƂŁA�����������鐻���ƂƂ����`�̃n�C�u���b�g�^�̃r�W�l�X���f���ł�点�Ă��������Ă���Ƃ����`�ɂȂ�܂��B
���̎��ɉ�X����ɂ���Ă��邱�Ƃ́A��{�I�ɂ�3D�f�[�^����͂�����A�œK�ȃf�W�^���Z�p�I��ł�������A�œK�ȍH��I�肪�ǂ̃��[�h�^�C���ŁA�ǂ̉��i�ŁA�ǂ̑f�ނłł���̂�����͂��āA�œK�ȍH��������o���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��āA����͎��̘_�_�ɂȂ�Ǝv���܂�����ǂ��A������AI�Z�p���g���Ă���Ă���Ƃ����`�ŁA���̃r�b�O�f�[�^�I�Ȃ��Ƃ���点�Ă��������Ă���܂��B
�����̏o���ł����A���Ƃ��ƃG���N�g���j�N�X�Ɛl�H�m�\�̃\�t�g�E�G�A���������Ă����G���W�j�A�ł������܂��āA�Ȃ��A���̂Â���ɂ���̂��Ƃ����Ƃ���ł����A�������g�̏o���������ł��āA�N���[�Y�h�C�m�x�[�V�����ł��̂Â��肪�����Ƃ��܂������Ă����Ƃ��낪�A���͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ���ŁA����10�N�A20�N�̓\�t�g�E�G�A�����܂������Ă����ƁB����̓I�[�v���̎d�g�݂����܂����������Ǝv���Ă���܂��āA���������v�z�����̂Â���̐��E�ɂ��܂���������ŁA���̋ƊE���n�b�s�[�ɂ������ȂƂ����v���ł�点�Ă��������Ă��܂��āA��X�̃r�W�����Ƃ��Ắu���̂Â���剻�ցv�Ƃ����悤�Ȍ`�ł�点�Ă��������Ă���Ƃ���ł������܂��B
�O�����I�ȂƂ���ɓ���O�ɁA��قǂ̂��b�ł����ƁA�\�t�g�E�G�A�̂Ƃ��낪���������剻�A������f�W�^���E�f���N���^�C�[�[�V�����ƌ�����Ƃ��낪�A����10�N�A20�N���������܂������Ă������ȂƎv���Ă���܂��B
���̂ق��̗��R�ł����A�V�F�A�����O�G�R�m�~�[�݂����Șb���ŋ߂Ō����ƒ��ڂ���Ă���Ǝv���̂ł�����ǂ��AAirbnb�ł��Ƃ�UBER�Ƃ��A���ƌ�قnj�Љ���Ă���������Ǝv���܂����A���[�J�����[�^�[�Y�Ƃ����悤�ȁA������LINUX�^�̎ԃ��[�J�[�݂����Ȃ��̂��������܂��āA���������I�[�v���Ȏd�g�݂ł��܂������Ă����Ƃ����Ƃ��낪���������o�n�߂Ă��邩�ȂƎv���Ă���܂��B
�Ⴆ�A�f�W�^���L���̐��E�Ƃ����̂́A�����������l�ȃv���[���[������G�R�V�X�e�����ł��オ���Ă���Ƃ����`�ɂȂ��Ă���܂��B�������g�����Ƃ���AI�o�g�Ȃ̂ł�����ǂ��A�O�E�͔��Ƃ����L���ƊE�ɂ���܂��āA�Ȃ��L���ƊE�ɂ����̂��Ƃ����ƁA������r�b�O�f�[�^��́AAI�I�ȋZ�p�����������p���ꂽ�̈�ł��āA���ɃO�[�O���A�t�F�C�X�u�b�N�Ȃǂ��������͂���ꂽ�̈�ŁA�����������G�R�V�X�e�������ł�����ƁB�����A�������g�̌̋��̓����Ȃǂ͍��A�E��������̏ɂȂ��Ă��܂��āA�N���[�Y�h�C�m�x�[�V�����Ƃ����̂��ǂ�ǂ�����������Ȃ��Ă��邩�ȂƂ������Ƃ������Ă���܂��B
���A���̂Â���̕ω��̒��ŁA�P�̃L�[���[�h�Ƃ��Ă���̂��A������f�W�^���t�@�u���P�[�V�����Ƃ����Ƃ���ŁA�f�W�^���t�@�u���P�[�V�����Ƃ����͉̂�����Ƃ������Ƃł����A������R���s���[�^�[�Ɛڑ����ꂽ�f�W�^���H��@�B�ɂ���Đ�������Z�p�̑��̂Ō����Ă���܂��B�ł��̂ŁA3D�v�����e�B���O��킸���[�U�[�J�b�^�[�ł��Ƃ��A������f�W�^������@�B�Ƃ������Ƃ�����܂߂đS�ē����Ă��܂��B�����郍�{�b�g�̗̈�������Ă��܂��B���N�O�ɁuMAKERS�v�Ƃ����悤�Ȗ{�����������s�����Ǝv���̂ł����A�����������Ƃ��낪�l�܂ŗ����Ă���Ƃ������ꂪ�A�����傤�Ǘ�����Ƃ����Ƃ���ɂȂ�܂��B
�ŏI�I�Ɍl�����[�J�[�ɂȂ��Ă����Ƃ����R�A�ȃL�[���[�h�ł�����ǂ��A�P�́A������f�W�^��DIY�A�ƒ��3D�v�����^�[�����y���Ă������ƂŁA���܂łł��Ƌ��^������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��ɂ����悤�Șb���A�ƒ�łP����ł����̂������Ƃ����Ƃ��낪�A������l�̖��剻�ɂȂ���ƌ����Ă��܂��B
�Q�ڂ��������傫���̂ł�����ǂ��A�R�~���j�e�B�[�Ƃ����Ƃ���ŁA�f�W�^���̃R�~���j�e�B�[���L����Ƃ����Ƃ��낪�A�����鋤�n���s����A�Ƃ��ɂ���Ƃ����Ƃ��낪�������d�v���Ȃƍl���Ă��܂��B
���̗��ł��������[�N����̂��A������3D�f�[�^�ł������܂��āA���ꂪ10�N�O�ł��ƁA�l�b�g���[�N�̖�������܂���3D�f�[�^�����ʂł��Ȃ������B���ꂪ���̓l�b�g���[�N�̖�肠�邢�̓c�[���������ɂȂ��Ă���Ƃ��낪����܂��āA3D�f�[�^�̗����������������܂��Ă���Ƃ����Ƃ���ŁA�l�̃��[�J�[���[�u�����g�Ƃ����̂��N���邾�낤�ƌ����Ă���܂��B
3D�v�����e�B���O�ɖ߂点�Ă���������Ǝv���܂����A3D�v�����e�B���O���̂͑傫���Q�������܂��āA�P�́A������l�p��3D�v�����^�[�A������͎Y�Ɨp��3D�v�����^�[�ł��B���͂���́A�K�[�g�i�[�̃e�N�m���W�[�n�C�v�T�C�N���Ȃ̂ł�����ǂ��A�l�p��3D�v�����^�[�͂����鎀�̒J�Ɍ������Ă���Ƃ����ł��āA�ŏI�I�ɉƒ�ɕ��y���邩�ǂ����͂킩��Ȃ��Ƃ����ɂȂ��Ă��܂��B�����A�Y�Ɨp��3D�v�����^�[�Ɋւ��Ă͈���g�債�Ă����Ƃ����ł������܂��āA���������݂�����3D�v�����e�B���O�̋Z�p�̏���ڂ₯�邩�Ȃƍl���Ă��܂��B
�ł��̂ŁA�v�͉ƒ��3D�v�����^�[�Ƃ����͍̂����̂��̂ł��āA�ǂ��炩�Ƃ����Ǝ��삪���S�̂Ƃ���ɂȂ�܂��āA�E���̎Y�Ɨp��3D�v�����^�[�Ƃ����̂́A����ł͂Ȃ��ŏI���i�̗̈�ɑg�ݍ��܂�Ă����Ƃ����Ƃ���ŁA�Q�͌���Ō����Ǝg�����A�ړI����Ⴄ�Ƃ����`�ɂȂ��Ă���܂��B
3D�v�����e�B���O�ł��̂�����Ƃ����Ƃ���Ȃ̂ł����A��������^�ł��Ƃ��؍�@�B�ł��̂���������͂邩�ɊȒP�ɂł���Ƃ����Ƃ��낪���������_�ł��āA�f�[�^������A���̃f�[�^��3D�v�����^�[�ɓ����Ƃ��̂��ł���Ƃ������Ƃł����A��{�I�ɂ�3D�f�[�^������A��������X���C�X���Ă����āA���ςݏグ�Ă����A�����鑫���Z�^�̋Z�p�Ƃ����̂�3D�v�����e�B���O�̗����̋Z�p�ɂȂ��Ă��܂��āA����������A���[�U�[��������A�n�����Ă�������Ƃ��낢��Ȏ�@���������܂��B
���A3D�v�����^�[�Ɋւ��ẮA�ƒ�p�̂��̂Ɋւ��Ă͎�Ƀv���X�`�b�N�����S�Ȃ̂ł����A�Y�Ɨp�̂��̂Ɋւ��Ă̓v���X�`�b�N�����łȂ��A������F���D�̃G���W���݂����Ȃ��̂̓`�^���ł����Ă�����Ƃ��A�q��F�����i�ɑς�����v���X�`�b�N�f�ނ��������܂����A���邢�͐��̂ɋz���ł���f�ނ��g���ƃC���v�����g�Ŏg����݂����Șb��������A���ɑf�ނ��o���G�[�V�����������A���A���낢��ȗ̈�Ŏg���Ă���Ƃ����ɂȂ�܂��B
���̗̈悪�Ȃ��������N����オ���Ă������Ƃ����Ƃ���ł����A����2009�N�ɉƒ�p��3D�v�����^�[�̓������ꂽ�Ƃ������ƂŁA���A�Ⴆ�Α��̗��ʂ���ȂǂɂR�`�T���~���炢�Ŕ����Ă���Ƃ����Ƃ���ł��B���́A�Y�Ɨp��3D�v�����^�[�Ƃ����̂�2014�N�P�����珙�X�ɓ�������n�߂܂��āA���ꂱ�����̓L���m������ł��Ƃ��A���ł���A���R�[����Ȃǂ̓��{���[�J�[���Q�����Ă���Ƃ����ɂȂ��Ă���܂��B
2014�N����Y�Ɨp��3D�v�����^�[�̓�������n�߂��Ƃ���ŁA�_�C���N�g�E�f�W�^���E�}�j�t�@�N�`���A�����O�Ƃ������ƂŁA�f�[�^����_�C���N�g�ɍŏI���i������Ƃ������ꂪ���X�ɋN������Ƃ����ł������܂��B�����A�܂��P���������Ƃ���ł͂���̂ŁA�O���[�o���Ō������ɍq��F���ł��Ƃ��A�R���A��Â����͑傫�ȂƂ�����߂Ă���`�ɂȂ�܂��B
������̃}�[�P�b�g�ł�����ǂ��A�o�Y�Ȃ���̃��|�[�g�ł����A2020�N�Ƀf�W�^���̂��̂Â���ɂ���đn�o�����}�[�P�b�g�Ƃ����̂��A������ŏI���i�s��Ƃ����̂�10���~���炢�N���邾�낤�ƌ����Ă���܂��B���̒��̂P�����A�����郁�[�J�[�Y���[�u�����g�̒��̌l����̂P���~���炢��S���̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���܂��B
���ƁA���܂ł͂����鎎��ł��Ƃ��A�C���_�X�g���[4.0�Ƃ������t���L�[���[�h�ɂȂ�܂�����ǂ��A�����������Ƃ����}�[�P�b�g��10���~����ƌ����Ă���܂��B3D�v�����^�[���̂̃}�[�P�b�g�́A���͏���C������ĂP���~����Q���~���炢�ɂȂ��Ă���̂ł�����ǂ��A���ꂮ�炢�̃C���p�N�g�ł���Ƃ����`�ɂȂ�܂��B
����̌�Љ�ɂȂ�̂ł����A��قnj�Љ���Ă��������܂������[�J�����[�^�[�Y�݂����ȁA������͎Ԕł̃����b�N�X�݂����Ȍ`�ŁA�I�[�v���ɐ��E���̃v���_�N�g�f�U�C�i�[�ł��Ƃ��@�\�A�G���W�j�A�A�d�C�n�̃G���W�j�A�Ƃ����̂��f�[�^�����L�������āA�F�ŃR���y���������ăt���b�g�ɎԂ������Ă����Ƃ������[�J�[�ł������܂��āA�������������ꂪ����Ƃ����Ƃ���ł������܂��B
���ƁA���낢��ȋZ�p�̗̈�Ō����ƁA��������n�߂Ĕ��ɑ��x���オ���Ă���Ƃ����Ƃ���ŁA����O�[�O�������������x���`���[�Ȃ̂ł�����ǂ��A����25�{����100�{�ɃO�b�Əオ��Ƃ������Ƃ��N�����Ă�����ł��Ƃ��A�d�q��H���v�����e�B���O����Ƃ����Ƃ��낪�C�X���G���̃x���`���[�ŏo�Ă�����A�n�[�o�[�h��w�̃x���`���[����o�Ă�����A�f�ފJ�����������L�тĂ���܂��āAMIT���K���X�f�ނ��J������Ƃ������Ƃ�����Ă�����A���A�ƒ�p�̃v�����^�[���f�ފJ�����������i��ł���܂��āA���傤�ǒ��߂ł����ƓS�Ƃ��u�����Y�A����Ƃ������悤�ȑf�ނ��ƒ�p�łł���Ƃ����`�ō���������܂��B
�����ŁA���C���e���ł��Ƃ��O�[�O�����A������X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�̒��̃��W���[����3D�X�L���������Ă����Ƃ������Ƃ�����Ă��܂��āA���ꂪ���N�ŃX�}�z�̒��ɓ����Ă����Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�N������3D�X�L���i�[�����Ƃ����`�ɂȂ�܂��āA�����Ȃ�Ƃ�����E�G�A���u���AIoT�݂����ȃf�o�C�X���A�Ⴆ�Ύ����̊ዾ�ł��Ƃ��A�����̕���C�̃C���\�[���������ɍ��������̂�����ƁB�悭�AEC�T�C�g�ŕ����̂��ʓ|�������A�����ɂ����Ƃ����̂��A�����łς��ƂƂ�����������̂������ōs����݂����Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B
���������̈�A�C���_�X�g���[4.0�ł��Ƃ��A�C���_�X�g���A���C���^�[�l�b�g�Ƃ����悤�Ȍ`�ō������Ă���܂��āA3D�v�����^�[�����ł͂Ȃ��A�f�W�^���̐���@�B�ł��Ƃ����{�b�g�Ȃǂ�g�ݍ��킹�āA�ŏI�I�Ƀ����N���b�N�ł��̂�������悤�Ȑ��E�Ɏ����Ă������Ƃ������ꂪ���A���E���ŋN�����Ă���܂��āA���{�ł����{�ŃC���_�X�g���[4.0�Ƃ����`�ł����������ꂪ�N�����Ă��܂��B
�f�W�^���̂��̂Â��肪�����炷�ω��Ƃ����Ƃ���Ŋ���s�b�N�A�b�v�����Ă���������Ǝv���̂ł����A�����鐶�Y�̎嗬���A�K�i�i����e�[���[���[�h�i�ɓ�����O�̂悤�ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ������Ă�����A���ƁA������J���̋@�B�������������Ȃ��Ă����B���A�ɂ��f�[�^���������Ă���ΓK�ʐ��Y���s����Ƃ����Ƃ��낪���ɑ傫�ȃ����b�g�ł���ƍl���Ă��܂��āA�v���X������I�[�v���ɂ��̂�����Ƃ�������ŁA�Ⴆ�A���ꂪ�l���������`�́A���傤�Ǎ���点�Ă��������Ă����ł�����ǂ��A�l�Ɛ����Ƃ��������Ă��̂�����Ƃ����悤�ȗ��ꂪ���܂��ɋN�{���Ƃ��Ă���Ǝv���܂��B
�����A���̒��Ƀ��X�N���������܂��āA�f�W�^���R�s�[�Ƃ����`��3D�X�L���i�[��3D�v�����^�[�A���ɃX�}�[�g�t�H����3D�f�[�^���ł���ƂȂ�A�{���ɂ��̂��ȒP�ɃR�s�[�ł���悤�ɂȂ�܂��āA���ɗ��p�҂̃����������߂���悤�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B
���A�R�s�[���C�g�̗̈���܂��ɂ��낢��ȃf�[�^�Ƃ��̂��ǂ��K�肷�邩�Ƃ����Ƃ���ɂ����āA���쌠�̖�肪�����邩�ȂƎv���Ă��܂��B
���傤�Ǖč���DIY�Ɋւ���悤�Ȗ@�����������܂��āA�Ⴆ�A�w���҂������Ԃ̐����H����50���ȏ�g��邱�ƂŏՓˎ����Ȃǂ̋K�����Ə������݂����Ȃ��̂�����܂��āA�����������Ƃ����ƃI�[�v���C�m�x�[�V�����^�A�I�[�v���^�ɂ��̂�����Ƃ������Ƃ����₷���Ȃ�̂��Ȃƍl���Ă��܂��B
���Ƃ́A�\�t�g�ƃn�[�h�̃I�[�v���Ȏd�g�݂Ƃ��܂��āA�Ⴆ�A�\�t�g�E�G�A�̐��E�ł��ƁA�I�[�v���R���e���c�ł��Ƃ��A�I�[�v���\�[�X�\�t�g�E�G�A�݂����Ȃ��̂�����܂�����ǂ��A�n�[�h�E�G�A�̐��E�Ɋւ��ẮA��قǂ�3D�f�U�C�i�[����������ŃI�[�v���Ƀf�U�C�����Ă����݂����Ȃ��Ƃł��Ƃ��A�I�[�v���\�[�X�n�[�h�E�G�A�݂����Ȃ��̂��o�Ă��܂��B��X�����l�Ɏg���Ă���̂ł�����ǂ��A�N���G�C�e�B�u�R�����Y�Ƃ����`�ŁA������R�s�[���C�g�ƃp�u���b�N�h���C���̊Ԃ�������ƋK�肷��Ƃ������Ƃ́A��X�̃v���b�g�t�H�[���Ƃ��Ă��K�肵�āA�f�[�^�̗��ʂ��Ǘ�����݂����Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��āA�ɂ₩�ȃ{�g���A�b�v�̎d�g�݂����A��X�Ƃ��Ă��������Ă���܂��B
���Ȃ݂ɁA���Ђ̂���Ă��邱�Ƃł����A���Ў��g�͍ŏI�I�Ƀf�[�^������Ή��ł����̂�����Ƃ����Ƃ����ڎw���Ă���܂��āA���̎��ɍ���X�Ƃ��Čl�̃}�[�P�b�g�v���[�X�ł��Ƃ��A�a to �a�̖@�l�l�̎��Ƃł��Ƃ��A�H������̎��Ƃ�����Ă��܂��B�����A��X������Ă��邱�Ƃ�3D�v�����^�[���[�J�[�ł��Ȃ��H��ł��Ȃ��ƁB��X������Ă���̂̓f�[�^��K�ɉ�͂��āA�œK�ȋZ�p��œK�Ȑ��Y�H���I�яo���Ƃ����悤�ȋZ�p�A���邢�̓f�[�^���\����͂��ĕϊ�����悤�ȋZ�p�����[���Ɏ������Ă��������Ă���܂��āA�����������Ƃ��낪�����`�[���ł�点�Ă��������Ă���܂��B
�����̍H�ꂳ�̂́A�S���E30�J���ȏ�ŃO���[�o���ȕ��U�����l�b�g���[�N�Ƃ����`�łȂ����Ă��������Ă���܂��āA�ނ�̗V�x���Ԃ����p�����Ă��������Ƃ����d�g�݂ł�点�Ă��������Ă���܂��B
���킹�āA�H��l�̐��Y���������グ��悤�ȃN���E�h�T�[�r�X������Ă��܂��āA�H��̎x��������ł��Ȃ���A�t�Ƀ��[�J�[����̎x���Ń}�X�J�X�^�}�C�[�[�V�������ȒP�ɂ���悤�ȃ\�����[�V���������B�����T�[�r�X�ƃ}�X�J�X�^�}�C�[�[�V�������ȒP�ɂł���A3D�f�[�^���ȒP�ɉ��҂ł���悤�ȃG���W���������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���点�Ă��������Ă��܂��B
���ꂪ�A���͎����Ԃ����ł͂Ȃ��āA�Ⴆ�A�Q�[���̃h���S���N�G�X�g�ŁA�����Ŏ�l���̃L��������Ă�ƁA���ꂪ�������Ă����̂ł�����ǂ��A���ꂪ����3D�f�[�^������Ă���̂ŁA�����N���b�N�ł��̂Â���̃f�[�^�ɕϊ����܂��āA�����Ńt�B�M���A������݂����Ȃ��Ƃł��Ƃ��A���邢��3D�L�O�ʐ^�ق݂����Ȃ��Ƃ��A���傤�Ǎ����t�g����̗L�y���X�Əa�J�X�Ɣ~�c�X�œW�J�����Ă��������Ă��܂��āA���̏ꏊ�ɍs���ƃX�L���i�[������܂��āA100���̂P�b�B��ƌ䎩�g�̃y�b�g�₨�q����3D�L�O�ʐ^�ɂȂ�Ƃ����悤�Ȏ��Ƃ���点�Ă��������Ă��܂��B����������̃v���b�g�t�H�[���A�����l�b�g���[�N��������Ă��������Ƃ����悤�Ȍ`�ł�点�Ă��������Ă���܂��B
��X�̃r�W�l�X���f���́A������IT�ł���A�����������Ƃł���Ƃ����`�ł������܂��B
�ȏ�ł������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�������ψ��� �X�}�z��3D�X�L���i�[������ƂȂ�ƁA���̎ʐ^���B������A�Ƃł��ꂪ�R�s�[�ł���Ƃ������Ƃł����B�Ƃ��Ă��֗��ł�����ǂ��A���낢������N���������Ƃ������ƂŁA�����A�ǂ�����Ƃ����킯�ł��B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
������܂�������Ȃǂ����܂��A�����ǂ���������������_�_�ɂ��ċc�_���������������Ǝv���܂��B���̋c�_�ɂ͈�c����ɂ��Q������������Ǝv���܂����A�F���玿��ł��R�����g�ł����ł����\�ł��̂ŁA������o������������Ǝv���܂��B�������ł��傤���B
���z����A�ǂ����B
�����z�ψ� �v���[���e�[�V�����ǂ������肪�Ƃ��������܂����B���������ł��̂ł������������̂ł�����ǂ��A�R�~���j�e�B�[�̒���3D�f�U�C�i�[�Ƃ��������������āA�{���̘_�_�ɂ����Ɋւ��Ǝv���̂ł����A���̕������̍��̒����Ƃ����܂����A�����鎩���̃f�[�^�Ɋւ���l�����A�܂��́A�����̋A�����ɂ��Ă̍l�����ł�����ǂ��A���̕���������U�f�U�C��������3D�f�[�^�Ƃ������̂́A��{�I�ɂ̓f�U�C�i�[�ɋA�����Ȃ�����̗��p��F�߂�Ƃ����̂���ʓI�ȍl�����Ȃ̂ł��傤���B���̂�����������Ă���������Ǝv���܂��B
����c�Q�l�l �䎿�₠�肪�Ƃ��������܂��B��{�I�ɂ́A������3D�̃N���G�C�^�[�̕��Ƃ����͔̂��ɋƊE�����L���A�傫��������3DCG��3DCAD�Ƃ������̂�����܂��āA3DCAD�̏ꍇ�͂����鐻���Ƃ̕��������A������C���_�X�g���A���f�U�C�i�[�̕��������ł��B3DCG�̕��́A������f��ƊE�ł��Ƃ��A�Q�[���ƊE�ł��Ƃ��A���z�ƊE�̂�����3DCG���f���[�Ƃ������������Ƃ����`�ŁA��{�I�ɂ͊F����̃f�[�^�͂��̕��X�ɋA������Ƃ����`�����̒ʗ�ɂȂ��Ă��܂��B
�����A������������ƁA������}�b�V���A�b�v�A���~�b�N�X�݂����Ȃ��Ƃ��������Ă���̂ŁA��قǂ���Љ���Ă����������A������N���G�C�e�B�u�R�����Y�I�ȗ���A�Ⴆ�A�x�[�X�̃f�[�^�����܂����҂��āA�W���x�[�X�̃f�[�^���g���Ȃ���Q�������҂���݂����ȗ��ꂪ����N�����Ă���ƍl���Ă���܂��B
������ł������ɂȂ��Ă��܂��ł��傤���B
�����z�ψ� �ǂ������肪�Ƃ��������܂��B
�������ψ��� �T��ψ��A���肢���܂��B
���T��ψ� ��������肪�Ƃ��������܂����B������Ǝ��₳���Ă������������̂ł����A�v���b�g�t�H�[�}�[�Ƃ��ăr�W�l�X�������Ƃ������Ƃł����A���̃v���b�g�t�H�[���̉���Ƃ����ׂ����Q���������̊Ԃ�3D�f�[�^�̗��ʂɂ����ẮA�����Z�p�I�ɉ�������A�N�Z�X�ł��Ȃ��悤�Ȍ`�ɂ���Ă���̂��A���邢�͂����ƃI�[�v���ȏ�Ńf�[�^�𗬂��Ă����āA�N���G�C�e�B�u�R�����Y�̃��C�Z���X�����Ŏg���Ă�������Ƃ����`�ł���Ă���̂��A�f�[�^���ʂɊւ��Ăǂ��������o�ŕی�����l���Ȃ̂��A������������������Ǝv���܂��B
����c�Q�l�l ���Ђ̏ꍇ�A��{�I�ɂ͗Ⴆ�A�}�[�P�b�g�v���[�X�ł������������h�P�[�X������܂��ƁB���ꂪ6,000�~�Ŕ����܂��Ƃ���̂ł����A���̃f�[�^�͊�{�I�ɂ͉�X�̃f�[�^�x�[�X�ŕێ����Ă��܂��āA�ʏ�ł���Γ���ł��Ȃ��悤�Ȋ��ɂȂ��Ă���܂��B���̂�����̃Z�L�����e�B�[�͔Րł�点�Ă��������Ă���ƁB
�����A���̕����A�����郊�~�b�N�X�𑣐i���邽�߂Ƀf�[�^�����J���Ă�������Ƃ����ꍇ�́A�Ⴆ�A����̓y�b�g�{�g���̃L���b�v�̃f�[�^�ł����A���������f�[�^�����~�b�N�X�������Č��J�������Ƃ������́A���������N���G�C�e�B�u�R�����Y��\�����܂��āA���p��OK�Ȃ̂��A�����łȂ��̂��݂����Ȃ��Ƃ����̕����ӎv�\�������āA�f�[�^�����J����Ƃ����A�[�L�e�N�`���[�����Ƃ��Ă���`�ɂȂ�܂��B
���T��ψ� �����Ō��J���ꂽ�f�[�^�ɂ́A���ɐ������͂������Ă��Ȃ��Ȃ̂ł����B
����c�Q�l�l ���́ADRM�͂����Ă��Ȃ��`�ɂ��Ă��܂��B
���T��ψ� ���肪�Ƃ��������܂����B
�������ψ��� ��������A�ǂ����B
�������ψ� ���ɋZ�p�̐i���łǂ�ǂ̒����ς���Ă����̂ł�����ǂ��A�������ł��낢��l���Ă���̂ł����A���̏�ŕK�v�Ȃ��ƁA�m���̐헪�I�ɉ��������ōl�����炢�����Ƃ����̂́A�������r�W�l�X���ǂ�ǂ�ł��܂��˂Ƃ����Ă��A�܂�����͂킩��Ȃ��킯�ł���ˁB���낢�뎎�s���낳��Ă���B�����A���̎d�g�݂̖{���͉����Ƃ����ƍl���Ă����̂ł�����ǂ��A��{�I�ɂ͍��܂ŕ��ʂ����R�s�[�ł��Ȃ��������̂����̂��R�s�[�ł���悤�ɂȂ�܂����B���̎��ɁA���̂�������Ă���ƃ����I�t�A���܂ō����āA�v����ɂP�i���삷��悤�Ȏ���i�݂����Ȃ��͍̂��������킯�ł���ˁB�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ������B���ꂪ���ɋC�y�ɂł���悤�ɂȂ��Ă������A���ɓI�ɂ͗Ⴆ�A���̂̈ꕔ���ł���Ƃ��A�l�̖{���ɂP�����v��Ȃ��悤�Ȃ��̂��C�y�ɂƌ����Ă͂��������ł����A���ɊȒP�ɂł���悤�ɂȂ��Ă����B�܂�A���̗��p�̖{���́A�l�Ԃ͑S�����Ⴄ�A�P���l��������P���l���Ⴄ�̂ł�����ǂ��A���̂P�l���ɂ҂�����K��������̂������Z�p�Ƃ��������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝ��͗���������ł��B�����ɗ��p�̈�Ԃ̗L�v��������̂��Ȃƍl���܂����B�ꉞ�������Ƃ���ƁA��{�I�ɂ��Ƃ̓X�L�����Ȃ�ł���ˁB���A���ȉ��炩�̃X�L�����B�Ⴆ�A�̓��f�[�^�̃X�L�����ł���Ƃ��A�������͎����ŃC���[�W�Ƃ��ăf�U�C�����Ă������̂ł�����ǂ��A���̃f�[�^���̂����ɏd�v�ŁA���ɌʓI�ő�ʂɂ���Ȃ����̂��������Ƃ��܂��B���ۂɂ���H�Ɛ��i�Ƃ����̂����ăR�s�[����Ƃ����̂́A���̋Z�p�̃j�[�Y�̒��ł͔�r�I�T�u�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B�܂�A���Ƃɂ�����̂�������g���Ă킴�킴�p�R�p�R����Ƃ����̂́A�P�Ɍ^������Ȃ��Ă͂����Ȃ����̂�����Ȃ��Ă����Ƃ���@�I�ɊȒP�ɂȂ邾���ł����āA���܂łƗ]��ς��Ȃ��Ǝv���܂����B
�Ƃ������Ƃ́A����X���l���Ȃ�������Ȃ��̂́A���A���̂��̂��X�L����������A�����ł�����3D�f�[�^���̂��ǂ�����ĕی삷�ׂ����A���ׂ��ł͂Ȃ��̂��Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł�����ǂ��A���͊�{�I�ɁA�X�L�����f�[�^�͒��쌠�ł͂Ȃ��Ǝv�����A�m���̒��ŗႦ�Γ����Ƃ��ӏ��o�^�Ƃ��������̂̒��ŁA���炩�ł��̃f�[�^��ی삷��ׂ����A�ی삷�ׂ��łȂ��̂��Ƃ����Ƃ��낪�A�����̕��������A��������サ�Ăǂ������`�Ő��i���Ă������Ƃ������Ƃ��A��������̐헪�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���������匳�̕������l���Ă����Ȃ��ƁA�ڂ̑O�̋Z�p�̂��炵���ɂƂ���Ă��܂ƁA�����Ă������悭�킩��Ȃ��Ȃ邵�A���̃R�s�[�͂����Ȃ��Ƃ��A�P���ɋ�̓I�������������Ă����Ă��A�킩��Ȃ��r�W�l�X���l���Ă����悤���Ȃ��̂ŁA�������l���Ă���̂́A�܂Ƃ߂Č����ƁA�ʐ���A���p�҂P�l���ɑΉ��ł���悤�Ȑ��i�������Ă����Ƃ����̂��A���̋Z�p�̕������Ƃ��炵���Ɨ��p���l�̒��S�ł���Ƃ���ƁA���̒��ŁA���ƂƂȂ�f�[�^���ǂ̂悤�ɐ������Ď��ׂ����A���Ȃ��ׂ����Ƃ������Ƃ��A�܂���X�͌��݂̒m���̐��x�ƏƂ炵���킹�čl���Ă݂�Ƃ����̂��菇�ł͂Ȃ��ł��傤���B�������Ȃ��ƁA���Ƃ��āA�����Ȃ肱������Ēm���łǂ�����̂ƌ����Ă����\����܂���ˁB�Ȃ̂ŁA���������ӂ��ɋc�_�̕������i���čl���Ă������Ƃ��A�܂������������ɂ͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B
�������ψ��� ���肪�Ƃ��������܂��B
�����A����͎����ǂƐ��������킯�ł͂Ȃ��̂ł�����ǂ��A�{�������ǂ���o���Ă��������Ă���̂́A�_�_�����Ă݂܂����Ƃ������̂ŁA��̉����{���ɉ�X���c�_���ׂ��_�_�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�����Ƃ����̂��A�܂����߂��Ă��邱�Ƃ��낤�Ǝ����v���܂��B���̂�����͊F����A�������ł��傤���B
����c�Q�l�l ���Ȃ݂ɁA�v���X���ł��b�������Ă��������Ă���낵���ł��傤���B
��قǂ̂��b�ł�����ǂ��A������}�X�J�X�^�}�C�[�[�V�����A�I�[�_�[���[�h��ÁA���̐l�P�l�ɍ������Ƃ���ɑ���\�����[�V�����Ƃ��āA���������f�W�^�����̂Â��肪�������j��͂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ƃ���ŁA���ނ��낻������Ԃ̋c�_�̃|�C���g�ł͂Ȃ����Ƃ������b�������Ǝv���܂�����ǂ��A���A��X�͐����Ƃ̕��X�A�Ⴆ�A���^���[�J�[����݂����ȂƂ���Ƃ��t�����������Ă��������Ă���܂��Ă�����������Ƃ���́A�v���_�N�g���C�t�T�C�N���Ƃ����Ƃ��낪���ɒZ���Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃł��B�Ƃ����̂́A�����҂��������ו������Ă���̂ŁA���܂ł̃v���_�N�g���C�t�T�C�N�����ƍl�����Ȃ��悤�ȒZ���T�C�N���ɂȂ��Ă��Ă��āA���ꂪ���܂ł�100�����b�g�A1,000�����b�g�݂����ȂƂ���ł�����^�ōς�ł����̂ł�����ǂ��A���͏����b�g�A�����b�g�Ƃ������̈悪���ɑ����Ă���B���ꂪ�����̋��^�̋Z�p���Ƃ����ǂ����Ȃ��B�ł��̂ŁA�������������i�����ɂ����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����悤�Ȕw�i������܂��āA��i�I�ȋ��^���[�J�[����Ȃǂ́A�����������f�W�^�������Z�p�����p���āA�v�͏����b�g�A�����b�g�ʎY�ɑΉ����Ă����Ƃ����Ƃ��낪���ɐL�тĂ���܂��B
�p�C�Ƃ��Ă��A����������̐����ɂ����Ă��������e�[���A�����b�g�A�����b�g�̂Ƃ���͔��ɐL�тĂ���Ƃ���ł������܂��āA���������Ƃ���͐�قǃI�[�v���C�m�x�[�V�����݂����Șb�ŁA�l����������ł����݂����Ȃ��Ƃ��������̂ł�����ǂ��A����͂ǂ��炩�Ƃ����ƃI�v�V�����̘b�ł��āA�ނ��냉�C�t�T�C�N�����������Z�����Ă����Ƃ����Ƃ���Ŏg���Ă���̂����̗���ł͂���Ƃ������Ƃ�⑫�����Ă������������Ǝv���܂��B
�������ψ��� �������ł��傤���B���z����A���肢���܂��B
�����z�ψ� �_�_�ɂ��Ė`���ɉ����ǒ����炨�b������܂�������ǂ��A3D�v�����e�B���O��IoT�ƁA���̂Ɋւ��Ƃ������Ƃœ��{�ɋ��݂Ƃ��Ă���������܂����A���ɏd�v�ȃe�[�}���ƍl���Ă���܂��B���̏�ŁA��قǂ̃v���[���e�[�V�����̒��ŃI�[�v���C�m�x�[�V�����Ƃ������b������܂������A�����ɂ�������������Ă����̂��Ƃ����Ƃ��낪�P�_�ڂ̎��_�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������Ă����ɓ������āA�P�ɂ́A�쐬�҂��ǂ��������ɐN�Q�s�ׂɂȂ邩���͂����肳����A���ɒ��앨����������̂�P�ɗ��̉������̂�������A����͒��쌠�N�Q�ł��ƁB����ȊO�ɂ͌����͕t�^���Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă���̂ł�����ǂ��A�Ƃɂ����N�Q�s�ׂ��͂����肳����B
�Q�ԖڂɁA�v���b�g�t�H�[�}�[�̐ӔC���͂����肳����B���̃��W�����̒��ɍ��̃v���o�C�_�ӔC�����@�̍l�����ŁA���̒��ɖ��炩�ȐN�Q��������������폜������A���������Ή�������K�v������ƁB�v���b�g�t�H�[�}�[�Ƃ����Ă����̃v���[���̒��ɂ���܂����悤�ɁA������͂�������A�I�ɗ��p����Ƃ������̂���A�P�ɗ����Ƃ������̂܂ł��낢�날��Ǝv���܂�����ǂ��A���̐ӔC�̂Ƃ���̊O�����͂����肳����B
�R�ڂɁA���p���p�Ƃ̋�ʂ��o�Ă��܂�����ǂ��A�֎q�̗Ⴊ�o�Ă��܂����A�ӏ��ŕی삳��Ȃ����̂ɂ��Ē��쌠�@�ŕی���g�傷��̂��Ƃ����Ƃ�����A���A���ƃf�[�^�A�܂����A���Ƃ����ӂ��ɍs�����藈���肷�鎞�ɁA�����̂��̂����̍H�Ə��L���ŕی삳��Ȃ��ꍇ�ɒ��쌠���g�債�ĕی������̂��Ƃ����_�́A�����肾�Ǝv���܂�����ǂ��A���������炩�ɂȂ�Ȃ��ƁA���ꂩ��3D�X�L���i�[���X�}�[�g�t�H���ɓ����Ă���Ƃ��A�N�ł��ł���Ƃ������ƂɂȂ������ɁA�ǂ��܂ł̃��A���̂��̂��f�[�^�����Ă����Ă����̂����͂����肳����Ƃ����̂��A��r�I�d��ȃe�[�}�ł͂Ȃ����Ǝv���āA�_�_�Ƃ����Ӗ��łR�v�����܂����̂ŋ��������Ă���������Ǝv���܂��B
�������ψ��� ���䂳��A���肢���܂��B
������ψ� �����A�G���̕����Ȃ�ł�����ǂ��A���A�F����̘b���f���Ă��āA��͂肱�̖����ꉭ�����M�ғI�ȎЉ�̕ω��̎��_���ɂ͌��Ȃ��悤�Ɏv���܂����B
��������̔����ɑ���⑫�̂悤�ɂȂ�܂����A�ǂ̂��炢�̊��Ԃŕ��y���邩�͂Ƃ������A�������������������Z�p�ɂ��s��̉\���͂R�_�ł��B�P�_�ڂ́A��������������J�X�^�}�C�Y�̗̈�ł��B�Q�_�ڂ́A�����ǂ������Ă��������Ă���f�b�h�X�g�b�N�A���Y�I���i�̗̈�ł��B�R�_�ڂ́A���ɂ߂ď����b�g�ō����ɔ̔�����Ă���悤�ȏ��i�̗̈�ł��B�����������̂́A�����Ė͕�̂��̂������āA�ቿ�i�Ŏ����̂��߂Ɏ�ɓ����Ƃ������v�����肻���ł�����A�r�W�l�X�`�����X������̂��ȂƂ����C�����܂����B
���̈Ӗ��łǂ̂��炢���Ԃ������邩�͂Ƃ������A�m���ɐL�тĂ����A���Ȃ��Ƃ����̉\���͏\������ȂƊ����܂����B�����Ȃ������ɁA����͋��炭�f�[�^�ɂ�����R�s�[���ʂ̗e�Ր��ƁA�قڃp�������ɓ����悤�Ȃ��Ƃ��N����̂ł͂Ȃ����B�܂�A�F�����M���e�ՂɂȂ�ƁA���Ȃ��Ƃ��f�[�^�����̉��l�Ƃ����̂͋����ߑ����N���܂�����A�ǂ����Ă��������Ă�������Ȃ��̂łȂ����Ƃ����C�����܂��B�܂�A�m�����ΏۂƂ���悤�ȃf�U�C���f�[�^�̕����Ƃ����̂́A�����ł���������A�b�v�������A��`�E�L��̂��߂ɃA�b�v�������A���邢�͎����̍s���̐��ʂ��݂�ȂɌ��Ă��炢��������A�b�v�������Ƃ����悤�Ȕ��M�҂����E�I�ɑ����Ă����ƁA�ǂ����Ă����i�����ɂ��炳��ĉ��i���������Ă����܂��̂ŁA�����������A�f�[�^�̕��������Ɍ����ō��ȏ�ɋ���������Ƃ��āA����ɂ������Ĕ����Ă����l���ǂ̂��炢���邩�ȂƂ�����肪�o�Ă���悤�ȋC�����܂��B�܂�A������^���邱�Ƃ̎������A��������ς�����̂Â���̃r�W�l�X���f�����ǂ��ς���Ă������Ƃ������Ɣ����ɂ��Ă͌��Ȃ��悤�ȋC�������̂ł��B
��������ƁA�������͂���̃R���e���c�Ɠ��l�ɁA��Ƃ������̂̉e�����ǂ����đ傫���Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B�܂��Ƀv���b�g�t�H�[�}�[�̕��ɖ{�����Ă��������܂�������ǂ��A�v���b�g�t�H�[���Ƃ����f�[�^�����Ƃ肳����͂����ƃ}�l�^�C�Y�ł��邾�낤�ȂƁB���������ꏊ�̉e���̋c�_�ƈꏏ�ɍl���Ă����Ƃ����̂��ȂƁA�G���ł����v���܂����B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� �ق��ɂ���܂��ł��傤���B�T�䂳��A���肢���܂��B
���T��ψ� �����ǂ����������������ꂽ�_�_�ɂ��āA�������q�ׂ����Ǝv���܂��B
�m���Ō���ی삳���ӏ����A���쌠��������̂��I���W�i���ɂ��ăf�[�^������Ƃ������Ƃɂ��ẮA���̌��������Ȃ肫������������Ƃ�������������Ă���Ǝv�����A�����͌����������Ȃ�����Ƃ����c�_���]��Ȃ��Ƃ����C�����܂��B
����ŁA������Ƒ���Ȃ������Ȃ̂��A12�y�[�W�ł��傤���A�ԐڐN�Q�ŏq�ׂ�ꂽ�A�u���v�ɖ{���Ƀf�[�^������̂��Ƃ����͔̂����ł��̂ŁA�����Ȃ�Γ����@�̂悤�Ɋm��I�ɉ����������Ƃ������Ƃɂ���A3D�f�[�^�̔Еz�s�ׂɑ���K���Ƃ������̂͌��\�ł���̂ł͂Ȃ����ƁB
����ŁA���쌠�@������@�A�ӏ��@������܂�����ǂ��A���쌠�@�ł���Ύ��I�̈�ōs�����ƁA�܂莩���ŃR�s�[�͂��Ă݂�����ǂ��ʂɔ̔��͂��Ȃ��Ƃ����s�ׂɂ��ẮA���������F�߂鉿�l�͂��邾�낤�ƁB�ӏ����A�������ɂȂ�ƁA�����͋ƂƂ��Ăł͂Ȃ����猠�����y�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����l����]�n������̂�������Ȃ��Ƃ������x�Ɏv���܂��B�����A���������̂��߂̎��{�Ƃ������͍̂��ł��F�߂��Ă��܂����A���l�ɏ��O�����悤�ȉ��l�ς��ێ����ׂ��A�܂�A���̖@�̌n�̒��Ō��\���镔���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂���ۂł��B
����ŁA�ی삳��Ă��Ȃ����̂��I���W�i���ɂ�����̂Ƃ����̂́A�܂��^��̈���o�Ȃ��̂ł����A�Ȃ��i�ʂ�3D�f�[�^���ƕی삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��P�B��̃f�[�^�̏�ԂƂ����͎̂g���Ă݂Ȃ��Ɖ������킩��Ȃ��̂ŁA�f�[�^�̏�Ԃłǂ�����̂��B�����������̂͌���A����͑�P��ڂ̎��ɂ��\���グ�܂�������ǂ��A�����l�ނ̔��W�̒��Ŋ�{�I�ɂ̓t���[�ɂ��Ă������̂������āA����m���Ƃ����`�ŕی삷�ׂ����̂��m�肵�Ă����Ƃ������Ƃ�����̂ł����A�������݂�3D�f�[�^���������ی�������^���邱�Ƃ��A���������Ă���̂��Ƃ��A���������C�����Ă���܂��B
�Ȃ��A�s�������h�~�@�̘b�ɂ��āA�����ł͒m���ŕی삳��Ă��Ȃ��ꍇ�Ə�����Ă���̂ł����A�s���@�͂ނ���m���̕ی�̈ꕔ���Ǝv���܂��̂ŁA�`�Ԗ͕킾�Ƃ��A���邢�͌`�Ԗ͕�ɂ�����Ȃ��悤�ȁA�Ⴆ�A�̂̂��̂��f�[�^�����čČ�����Ƃ����̂́A�ꍇ�ɂ���Ă͏��i���\���ɂ�����Ƃ��A������x�̂��̂͌���ł��ی삳�����̂�����̂��ȂƎv���܂��B
�ȏ�ł������܂��B
�������ψ��� ���ψ��ǂ����B
�����ψ� ���̘_�_�����̎����͂悭�܂Ƃ܂��Ă���Ǝv���Ă��āA����Řb�����Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł�����ǂ��A�܂��A3D�f�[�^��������藧�Ăĕی삷��K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B����ł�3D�v�����^�[���o�Ă����̂ŁA���������c�_���o�Ă����̂��Ǝv���܂�����ǂ��A3D�X�L���i�[���g�͊��S�ȃf�W�^�����A���ۂɂ�����̂��f�[�^�Ƃ��ăR�s�[����s�ׂł��̂ŁA���ꎩ�̂ʼn��炩�̌������lj����Ĕ�������Ƃ������ƂɊւ��ẮA�^���������͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���_���܂��P�_����܂��B
�f�[�^���̂ɉ��l��F�߂�Ƃ������ƂɊւ��ẮA�����ɂ�������Ă��܂�����ǂ��A����ł�3D�f�[�^�Ƃ����̂�3D�X�L���i�[�łƂ����f�[�^�A3D�v�����^�[�p�̃f�[�^�Ƃ����͍̂ŏI�I�ɂ��邠��ÓI�ȃf�[�^�Ȃ�ł��ˁB�Ƃ��낪�A���͑����d�v�ȃf�[�^�Ƃ������̂́A�����������X�L���������f�[�^�ł͂Ȃ��āA�Ⴆ�J�X�^�}�C�Y����悤�ȏꍇ�Ƃ����̂́ACAD�ł������悤�Ȃ�����x�ό`�\�ȃf�[�^��������Ƃ��A�Ⴆ�A�A�j���[�V����������ꍇ�Ȃǂ́A�����L�����N�^�[�Ƃ����͎̂��ۂ̊��W�߂����̂ł͂Ȃ��āA���������Ă����Ԃœ������āA���낢��Ȍ`�A�|�[�Y����������Ƃ��A�����������H�\�ȃf�[�^�������Ă����ł��B������̂ق����L������������̂Ȃ�ł��B�Ȃ̂ŁA�ی삷��̂ł���A���������������H���₷���A�ό`���₷��3D�f�[�^��ی삷�ׂ��ł����āA���̂悤�ȃf�W�^�C�Y���ꂽ�f�[�^���̂��̂Ɍ�������������Ƃ����l�����́A���͂��������ȂƎv���܂��B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� ��삳��A�ǂ����B
�����ψ� ��������A�����̘_�_�����钆�ŁA�{�������ǂɐ������Ă��������܂����m�I���Y���̊W�ɂ��Ă��b���������Ǝv���܂��B
�P�ڂ́A���ɒm�I���Y���̑ΏۂɂȂ��Ă�����̂ɂ��Ăł�����ǂ��A��قljƒ�p3D�v�����^�[�͗����Ă���Ƃ����b������܂�������ǂ��A�����A���ɍ��x�����ĉ��ł��_�E�����[�h���Ĕ����Ƃ������オ����̂�������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B�̂�CD��������ǂ��A���̓_�E�����[�h�ł�������Ȃ��Ƃ����l������킯�ŁA���ꂩ�炳�܂��܂Ȏ��p�i���܂߂ă_�E�����[�h���Ĕ����ƁB�����Ȃ�܂��ƁA���̃f�[�^�f�ŃA�b�v���Ă��܂��l�����邩������܂��A�����������̂��Ȃ��Ă��A�������̂悤��3D�X�L�������ăA�b�v����Ƃ����l���o�Ă��邩������Ȃ��B����3D�f�[�^�̎�舵�����ǂ����ׂ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂�����ǂ��A���앨�ƌ�����Β��쌠���y�т܂�����A���̃f�[�^�����邱�ƁA�A�b�v���[�h���邱�ƁA���M���邱�ƑS���Ɍ������y�Ԃƌ�����̂ł�����ǂ��A���앨�ƌ����邩�Ƃ����̂���͂������ŁA��قǂ������w�E������Ƃ��납�Ǝv���܂��B
�t�B�M���A�Ƃ��ł����璘�앨�̑ΏۂɂȂ���̂��Ǝv���܂����A���v�Ƃ��W���G���[�Ƃ������v���_�N�g�f�U�C���ɂ��Ă͉��p���p�̖��ɂȂ�܂��̂ŁA���͔��ɕs�����ȂƂ���ɂ���Ǝv���܂��BTRIPP TRAPP�����͔��ɉ���I�Ȃ̂ł�����ǂ��A�����ŋ߁A������Ɋւ��锻�����o���肵�܂��āA����͒��앨�łȂ��Ƃ������f�ł����̂ŁA��������X�L�������ăA�b�v���Ă����쌠�N�Q�ɂȂ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������ƁA����͈ӏ��@�ŕی삳��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł�����ǂ��A����������ǂ����Љ����܂����悤�ɁA�ԐڐN�Q�ɓ����邽�߂ɂ͂��̂ƌ����Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����ł͓����@��̂��̂Ƃ������Ƃ����p���܂��āA�v���O�������Ƃ������ƂŁA�v���O�����f�[�^�łȂ��Ă��u���v������킯�ł�����ǂ��A���̃v���O�������ɓ����邽�߂ɂ́A�����̂悤�ɋ�������ł����āA���A�v���O�����ɏ�������̂Ƃ������Ƃ��K�v�Ƃ���Ă��܂��B���̃v���O�����ɏ�������̂Ƃ����͉̂��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��傫�Ȗ��ɂȂ�킯�ł�����ǂ��A�P�ɏ��������Ƃ��������ł͂��߂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA����3D�f�[�^���v���O�������ɓ�����Ƃ͂�����Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂����A���̓_�͗��@�I�ȑΉ��̌��������Ȃ��Ƃ��K�v���낤�Ǝv���Ă���܂��B
�Q�_�ڂŁA�m�I���Y�łȂ����̂ɂ���3D�f�[�^��݂����쐬�҂̕ی�Ƃ������Ƃ��m���ɖ�肾�낤�Ǝv���܂��B����́A3D�f�[�^�̑��i�⊈�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA�����������̂��쐬�����l��ی삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����c�_�������ē��R���낤�Ǝv���܂��B�m���ɁA3D�f�[�^������Ƃ��X�L��������Ƃ����̂��f�l�ڂɂ̓X�L�������邾�����Ǝv������A�͂�肻�̍쐬�ɂ��܂��܂ȍH�v�Ⓤ����K�v�Ƃ�����̂����邩��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������ƁA�����قnj�Љ�������悤�ɁA���쌠�@��̐v�}�ƌ�����A�����ɌŗL�̑n�쐫�������Ē��쌠�ŕی삳���Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�Ǝv���܂�����ǂ��A�ߋ��̋c�_�ł��y���Ƃ����̂����y�ƕʂɑn�쐫�����邩�ƍl����ƁA�Ȃ��Ȃ�����Ƃ��낪����܂��B�������Ƃ��܂��ƁA��͂�ŗL�̌����Ƃ������ƂŁA������O��̑n�쐫�ɂȂ�Ȃ��悤�ȃf�[�^�x�[�X�ɂ��āAsui generis�Ƃ����`�ŐV��������������̂��Ƃ������Ƃ����ɂȂ�Ƃ������Ƃ͌�������悤���Ǝv���܂�����ǂ��A���������T�䂳��������������ƂƎ��Ă��܂����A�f�W�^�������Ɛ̂��猾���āA�f�W�^�����𑣐i���邽�߂Ƀf�W�^���������l�Ɍ�����^���邩�Ƃ����c�_���̂͂������킯�ł�����ǂ��A��͂肻��͂��Ȃ��Ă悩�����Ƃ������Ƃ�������܂���̂ŁA����͂��Ȃ�T�d�ɂȂ����ق��������̂�������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� ��������A�ǂ����B
�������ψ� ��قǂ̂�������^�≽�����Ƃ������������Ă��܂����ǁA�����b�g�łł���ƁB����͂܂��Ɉ����DTP�ƈꏏ�ł���ˁB�ł������Ă����ς����̂ɂ�����������������ǂ��A���̓f�W�^���̐i����100������ł���Ƃ��A10���ł��ł���ƁB����ɂ���Ĕ��ɂ悭�Ȃ��Ă����B�������Ƃ̗��̔łȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł�����ǂ��A����͏��サ�Ă��ꂩ��r�W�l�X���W�J���Ă�����낢����͋N���邩������Ȃ��ł�����ǂ��A��{�I�ɍ��̘g�g�݂ł��ꂪ�i�����Ă����Ƃ������ƂȂ̂ŁA�m���ʂ��炢���Ɛ��������Ă���قǖڐV���������Ƃ����̂͂Ȃ��B�������A���A���搶������������܂�������ǂ��A�B�ꂠ��Ƃ���ƁA���̕����X�L���������f�[�^�Ƃ����̂́A�P���Ɍv���A�������Z���`�A�d�����O�����ɗނ�����̂��ƁA����͒��쌠���Ȃ���ǂ��܂ŕی삷��̂Ƃ����b�͂��邯��ǂ��A�n�삵���f�[�^���������Ƃ��܂���ˁB�Ⴆ�A��������コ������������A������3D�A�j���̂��Ƃ����C�A�[�h����ĕ\�ʂ��������ꂽ�A�����邻�������f�W�^���f�[�^��̐l�������肷��ƁA���������f�[�^�ɂ��Ă̕ی���A����̓v���O�����̕ی�ƌ����đS�����쌠�ʼn������߂Ă��܂��Ƃ����̂́A��͂莄�͈�a���������āA���ꂱ�����̑O�b���o���V���������Ȃ̂��A�V��������������Ɛ��E�I�ɒʗp���Ȃ���������܂���ǂ��A���搶�̂��������悤�ɁA�אڌ��̒��ł��ꎩ�̂Ƃ������́A�����ŏI�I�Ȍ��ʂ邽�߂̈����O�Ȃ̂�����ǂ��A�����ɑn�쐫�ƑS�Ă̑n�앨�̍������������Ă���Ƃ��������ɂ��āA���炩�̌���������Ă����Ȃ��ƁA�܂��f�[�^�x�[�X�̌����̂悤�ɑS�����쌠�ɓ���Ă��āA�ŋ��̒��쌠�Ƃ��������Ŏ��Ƃ܂��j�Q���邱�ƂɂȂ�ƁA���������y���̍ق̌����Ƃ����̂́A�����ł��K�v�Ƃ���Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C����������Ƃ��܂��B���������`�ŏ����I�Ȃ��͍̂l����ɂ��Ă��A���̎��_�ŗ]�������Ȃ��ق����s��̌`���ɂ͗L�����ȂƂ������������܂��B
�������ψ��� ���ψ��ǂ����B
�����ψ� �v���O�����̘b���o�܂����̂ŁA�v���O���~���O�Ƃ��������f�[�^������Ƃ������ƂȂ̂ł�����ǂ��A����͂قڋ�ʂ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B���̃v���O���~���O�Ƃ����̂͑�̃r�W���A�������i��ł��āA���Ƃ��ƃv���O�����Ƃ����̂̓f�[�^�̕����ƃR�[�h�̕�����������Ă���̂ł�����ǂ��A���ꂪ��̂ƂȂ������̂��v���O�����ł��B���ꂪ�Ǝ��ɐi�����Ă��āA�f�[�^��������̂��v���O�����̂悤�Ȃ��̂�������悤�ɂȂ��Ă��邵�A�v���O�������̂��f�[�^�\���ƈ�̉�������������ł���悤�ɂȂ��Ă��āA�����v���O���~���O�ɑ��Ē��쌠���F�߂��Ă���Ƃ���������l����ƁA���ʂɍl����Ƃ���͔F�߂��Ȃ��Ƃ��������Ƃ����_�������͋N����Ǝv���܂��B�Ȃ̂ŁA���ꂪ���������ǂ����Ƃ����͕̂ʂɂ��āA���́A����͒��앨�ɂȂ�̂����R�̗��ꂾ�Ǝv���܂��B�ł��A�f�W�^��������s�ׂɑ��Ă��Ƃ����͑����Ⴄ�Ǝv���Ă��āA���ۂ�3D�v�����^�[�ł��{���ɗL�p�Ȃ��̂Ƃ����̂́A�R���s���[�^�[��ʼn��炩�̃c�[���������āA�����ƈꂩ����������̂��Ǝv���܂��B���̃c�[��������Ƃ����s�ׂ́A�v���O���~���O�Ɗ�{�I�ɂ͋�ʂ����Ȃ��悤�ɂȂ�܂����A�����_�ł��قڂ����Ȃ����܂��Ƃ����̂�����ł��B
�������ψ��� ���肪�Ƃ��������܂����B
���낢���ӌ������������܂����B3D�f�[�^�̂ݎ��グ�ĕی������Ó����͂ǂ����A�T�d�Ɉ����ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ�������܂������A����ŁA�����A���̕������������������͕K�v�ł��낤�ƁB���̂��߂ɕK�v�ȁA�Ⴆ�v���b�g�t�H�[���̐ӔC�̖��m���Ȃǂ̌����͏d�v�ł���Ƃ�����w�E�B�Ƃ͂����A�������������̂��i��ł����ƁA���̃R���e���c�Ɠ��l�Ƀv���b�g�t�H�[���̋c�_�ɂȂ��Ă����B�����������������������ẴV�X�e���̐v���K�v���Ƃ�����ӌ��������������Ƃ������ƂŁA�܂������ǂ̂ق��Ő��������������āA�_�_�̂Ƃ�����u���b�V���A�b�v���Ă��炦��Ǝv���܂����A����̉�ł������ςݎc���̂Ƃ��낪����A���̕���ɂ��Ă��c�_������`�����X�͂���Ǝv���܂��̂ŁA�ЂƂ܂����̌��ɂ��Ă͂��̂�����ɂ������Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B
�ł́A���̋c��ł���܂��uAI�ɂ���Đ��ݏo�����n�앨�̎�舵���v�̋c�_�Ɉڂ肽���Ǝv���܂��B
�����ŁA�J�u�N�̈�c�l�ɂ͑ސȂ����������Ƃ������Ƃł������܂��B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B�܂�����Ȃǂ���@����낤���Ǝv���܂��̂ŁA��낵�����肢�������܂��B
����c�Q�l�l ��낵�����肢���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�������ψ��� �ł́AAI�ɂ��Ď����ǂ���_�_�̐��������肢�ł��܂��ł��傤���B
������Q�����⍲ ����ł́A�����Q�ɉ����Č�����������Ă������������Ǝv���܂��B
�܂��A������������̍\���ł����A�R���\���ɂȂ��Ă���܂��B
�ŏ��ɁA�l�H�m�\���n�삷�邱�Ƃɂ��Ă̌���̌�����ł��B���ɁAAI�̑n�앨���m�����x�ɂǂ��e����^���邩�Ƃ������ƂɊւ��镪�́B�Ō�ɁA�m���V�X�e���Ƃ���AI�n�앨���ǂ������Ă������Ƃ����_�_�A����͂�����Ŏv�������̂�����������̂ŁA�S�Ăɂ��Č�c�_���������K�v������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��̎��_�Ƃ��čl��������̂����Ă������܂��B
����ł́A�����̐����������Ă��������܂����A�R�y�[�W����ł������܂��B�܂��u�l�H�m�\�̐i���ƎЉ�v�Ƃ������ƂŁA�P��ڂ�11���̉�̎��ɏo�������������H�������̂ł������܂��B
���A�l�H�m�\�͐l�̍�Ƃ̕⏕������Ƃ����Ƃ���Ɏg���Ă��Ă���킯�ł����A���ꂪ�����Ȃ��Ă��Ă��āA���͐l�Ԃ����������[���Ɋ�Â��ď������Ƃ����Ƃ��낪�A�����œ����𒊏o���ĕ��͂���Ƃ����悤�Ȓi�K�A����ɂ́A�����őn�삷��Ƃ����i�K�܂ł����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ������Ă��Ă���܂��B
�S�y�[�W�ȍ~������������Љ�Ă������܂��B�S�y�[�W�́A���y�̕���ł̐l�H�m�\���g�������g�݂̎���Ƃ������ƂŁA�X�y�C���̃}���K��w�Ƃ����Ƃ���ł����A����͊y�Ȃ����邱�Ƃ��ł���ƁB�y���̌`�ŃA�E�g�v�b�g���邱�Ƃ��ł���Ƃ������ƂŁA���ۂɃA�E�g�v�b�g�������́A�R���s���[�^�[���o���Ă����y�����I�[�P�X�g�������t����ƁB��������^����CD�ɂ��Ĕ���݂����Ȃ��Ƃ�����Ă���ƁB����CD�͔���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����Ă��܂����A�������������݂��Ȃ���Ă��Ă���܂��B
�T�y�[�W�́A���S�}�[�N�̃f�U�C��������Ƃ����l�H�m�\�̗�ŁA��������ۂɃr�W�l�X�Ƃ��Ďg���Ă�����̂ł������܂��B�A�����J�̉�Ђł������܂����A����͖����̂������ł���Ă݂����̂��ڂ��Ă��܂����A��Ж���ǂ�Ȏ��Ƃ�����Ă��邩�Ƃ��A�ǂ�ȃC���[�W�̂��̂��߂��ł����Ƃ������悤�ȑI������I��ł����ƁA�E���ɂ���悤�Ȋ���̃p�^�[���������Ă����ƁB���̉ߒ��ɂ����Đl�H�m�\�ł���Ă��܂��Ƃ������Ƃ���������Ă�����̂ł������܂��B
�U�y�[�W�́A�����������G�ȑn��̗�ŁA����͗L���Ȏ���ł����AAI�ɏ������������悤�Ƃ������̂ł������܂��BAI�����������������̂܂ܐl���S���ւ�炸�ɏo�Ă��Ă���Ƃ���܂ł͕������Ă��Ă���܂��A�֗^�����悤�Ȃ��̂����A�܂̕�W�ɂ��o���Ă���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��Ă���܂��B
�܂��A�V�y�[�W�́A�f�U�C���̕���Ɋւ��錤���Ƃ������ƂŁA��P�ł��ƁA�֎q�̃f�[�^���ʂɗ^���邱�ƂŁA�֎q�Ƃ͉�����l�H�m�\���w�K���āA��������ƂɈ֎q�Ƃ����̂͑�������A�r������A�w�����ꂪ����Ƃ����g�ݍ��킹�̒��Ńf�U�C���������Ă����Ƃ����悤�Ȍ������Ȃ���Ă���Ƃ�������ł������܂��B
�����܂ł͎���A����Ȍ����E���g�݂��Ȃ���Ă���Ƃ������̂ł������܂����A�����炱�������������܂��AAI�n�앨���m���ɂǂ������e����^����̂��Ƃ������͂��L�ڂ��Ă������܂��B
�X�y�[�W�A��������ω��ł������܂����A�l�Ԃ̑n�앨�ƌ������̂��Ȃ�����������ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƁB�ŏ��Ɍ����������Ȃ�����l�H�m�\�̏ꍇ�A��������̂܂܃I�[�P�X�g�����g���Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���܂��āA���̂܂g���Ƃ������Ƃ��\�B�ꍇ�ɂ���Ă͐l��������Ďg���Ƃ������Ƃ��\�Ƃ����ɂȂ��Ă��Ă���̂��Ȃƍl���Ă���܂��B
10�y�[�W�ł������܂��B�l�H�m�\�����������̂����̂܂g���Ƃ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���킯�ł����A�ł́A���ꂪ���s�@���x��ǂ����������ɂȂ邩���������̂ŁA�l�H�m�\�������I�ɂ��������̂ɂ��ẮA���̐��x�ł͌����̑Ώۂƍl�����Ă͂���܂���B����͒��쌠�ł���A�����E�f�U�C���ł���A���������s�ׂ�����̂͐l�Ԃł���Ƃ����O��ł����Ă��܂��̂ŁAAI���|�R���Əo���Ă������̂ɂ��ẮA�����͂Ȃ��Ƃ����̂����x��̐����ł������܂��B
���̐����͐����Ŗ��m�ł͂���̂ł����A�Ƃ͂����A���ԂƂ��Đl�ɂ��n�앨��AI�n�앨�Ƃ����̂́A����Ȃɐ���������������邩�Ƃ����ƁA�����͖��Ăł͂Ȃ�����������Ƃ������ƂŁA�ł͂ǂ��ɋ��E��������̂����ߋ��̌�������E���Ă������̂�11�y�[�W�ȍ~�ɂȂ�܂����A���쌠�̕���ʼnߋ�����������Ă���܂��āA�l�Ԃ̑n��s�ׂ����S�ɑ�ւ��Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�l������Ƃ��ăR���s���[�^�[���g���Ă���Ƃ������Ƃ����ԂȂ̂ŁA����͐l�ɂ��n�삾�낤�Ƃ������Ƃ������T�N�ɐ�������Ă���܂��B
12�y�[�W�A����Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ����̂͂ǂ��������ƂȂ̂��������Ă������܂����A�g�p����l�̈Ӑ}�A�n��̈Ӑ}�Ƒn��I��^�Ƃ������Ƃ�������Ă��邱�Ƃɂ���āA����Ƃ��Ďg���Ă���ƍl������Ƃ������Ƃ��A�ߋ��̕������̐R�c��Ő�������Ă�����̂ł������܂��B
���̕ӂ͕��͂������̂�13�y�[�W�ŁA���ǁA�l�ɂ��n�앨��AI�n�앨�͂ǂ������E���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��C���X�g�ɗ��Ƃ�����Ő������Ă݂܂����B�����������ƂȂ̂��ȂƂ��������ł������܂��B��̂ق��̐l�ɂ��n��́A��������������Ƃ����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�ƁBAI�ɂ��n��ɂ��Ă͌����͓��ɐ��܂�Ȃ��Ƃ������̂ŁA������AI��Ƃ��Ďg���Ƃ����l���Ӑ}�������āA���A�n��I�Ɋ�^������AI�ɓ������������ďo�Ă������̂ł���A���������܂��Ƃ����悤�ȍ\���ɗ�����͂Ȃ��Ă���ƁB
����ʼn�����肩�Ƃ������Ƃ͂����̂�14�y�[�W�ł��B�m�����x��N���蓾�錜�O�Ƃ������ƂŁAAI�n�앨�̓����Ƃ��āA�����������Ȃ��A�O����͂킩��Ȃ��ƁB��������ƁA�������Ƃ���Ɋ֗^�����l���������ƌ���Ȃ�����A�l�Ԃɂ��n�앨�Ɠ��l�Ɉ���꓾��ł��낤�ƁB���A�����������Ƃ������Ƃ�AI�͉\���Ƃ������Ƃł������܂��āA�����O��Ƃ��čl����ƁAAI�őn�앨���������l�����i�������Ƃ������Ƃ����������b�g���Ȃ���A���킸�ɐl�Ԃ����������̂��Ƃ����`�ɂ��ė��ʗ��p����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA��������ƁA�ꌩ����������n�앨�Ɍ�������̂������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB����������ɉ������d�˂��`�ɂ͂Ȃ�܂����A��������đ����Ă����Ɛl�H�m�\�𗘗p�ł���҂���ʂ̌����̂������Ɛ肷��ƁB�l�ł���N���G�C�^�[������������Ƃ��Ă��A���ɗގ��̂��̂͌��\�Ȃ�o�^�Ȃ肳��Ă��āA�l�̂��������͎̂g���Ȃ��Ȃ�Ƃ����悤�ȑz���������킯�ł������܂��āA�������������Ƃ��N����\�����l���A��������ƁAAI�n�앨�̒m�����x��̎�舵���Ƃ����̂́A���߂Č������K�v�ł͂Ȃ����Ƃ����̂����́E����N�ł������܂��B
���̂R���炪�A�ǂ������ӂ��ɐ��x��_�_�����邩�A������������ď����l�����Ƃ��Č�����Ă������������̂ł������܂��B
16�y�[�W�ł������܂����A���̐l�Ԃ�O��Ƃ��������ی�̎d�g�݂����̂܂ܓK�p����Ƃ܂������Ƃ����\��������킯�ł����A���ꂪ�{�����ǂ����A����������Č������Ă݂Ă͂ǂ����Ƃ������Ƃł������܂��B��������ߒ��Œ��앨�ɊY������A���쌠�ŕی삳��Ȃ����Ɣ����E�f�U�C���ƕ����Đ������Ă������܂��B
�܂��A��̒��앨�̏ꍇ�ł����A���쌠�Ɠ����̕ی��t�^����ƍl�����ꍇ�ɂ��ẮA�����̂���n�앨�������I�ɑ����邱�ƂɂȂ�̂��ȂƂ����Ƃ���B
�����ŁA���̈�ؒm�������������Ȃ��Ƃ����ꍇ�A���S�Ɏ��R�Ɏg���܂��傤�Ƃ݂�Ȃ����ӂ������ɉ����N���邩�Ƃ����̂��E���̘g�ɏ����Ă���Ƃ���ŁA���R�Ɏg���Ă��܂��Ƃ������ƂŁA�ی삪�K�v���Ƃ����l�ق�AI���������Ƃ͌���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA��������ƌ��ǁA��Ɠ����悤�ȁA�݂Ȃ��l�ԑn�앨�݂����Ȃ��̂���������o�Ă���Ƃ������ƂŁA���Ǒn�앨����ʂɑ�����Ƃ����A�ǂ���Ƃ��������_�ɂȂ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����ƁB��������ƁA�����������ԓI�ȂƂ������A�ʂ̎d�g�݂��l���邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����Ƃ����悤�Ȑ��𗧂ĂċL�ڂ��Ă������܂��B
17�y�[�W�́A�����E�f�U�C���̏ꍇ�ɉ����N���邩�Ƃ������Ƃ��V�~�����[�V�������Ă݂����̂ł������܂��B��̘g�́A���̐l�Ԃ̑n�앨�Ɠ����悤�ɓ������Ǝ����悤�Ȍ�����^����Ƃ������ꍇ�ɉ����N���邩�Ƃ������ƂŁA�������ɂ��Ă͐R���A�o�^�Ƃ����d�g�݂�����܂��̂ŁA��������̂܂ܓK�p����ƍl����ƁA�ʂ�AI���������S�Ă̂��̂ɂ��Č��������܂��킯�ł͂Ȃ��ƁB�o�^���ꂽ���̂ɂ��Đ��܂��Ƃ����Ӗ��ŁA���Ɛ�̌��O�͂����܂ő傫���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�ȍl�������ł��邩�Ǝv���܂��B
�����ŁA�o�^�܂�AI�������ł��Ƃ����Ƃ���܂ł����Ă��܂��ƁA�ł������̂��ǂ�ǂ�v���ɍ����Γo�^����Ƃ������ƂŌ������Ƃ��Ă����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��ƁA��͂茠���̂�����Ƃ����̂������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB�����̓o�^�E�ێ��ɗ����̖�肪����̂ŁA�����͌y�������\�������邩�ȂƎv���܂����A���ʂ̈Ⴂ�����ł����āA��͂�ی삪�����Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������͂����Ă������܂��B
18�y�[�W�A19�y�[�W�ȍ~�͂P�̃e�[�}�ŁA�����܂ł������ɉ����ɉ������炢���d�˂Ă���̂ŁA���낢���c�_�͂��낤���Ǝv���܂����A�˂��l�߂Ăǂ��܂ł������l���Ă݂����̂ł������܂��B�ǂ��������̐��x�̓��Ă͂߂��A�ی�����Ȃ��̂�����������ƂȂ������ɁA�V�����d�g�݂��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ����z�Ƃ��ďo�Ă��邩�ȂƂ������Ƃł������܂��B���ꂪ�����K�v���ƂȂ����ꍇ�ɁA����͉��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�����̗v���ɕ������Đ������Ă݂����̂ł������܂��B
�A)�Ƃ��āA��̂̉�����낤�Ƃ��Ă���̂��Ƃ����ی�@�v�Ƃ������ƂŁA�N�Ɍ������A��������̂��A����͂Ȃ��Ȃ̂��Ƃ����Ƃ��낪�ŏ��̘_�_�ɂȂ낤���Ǝv���܂��B���Ƃ��ẮA�v���O�����̊J���҂�AI�Ɋw�K���������f�[�^�̒ҁA���Ƃ͍ŏI�I��AI���g���đn��̎w���������l�Ƃ����Ƃ��낪�l������Ǝv���܂����A���ꂼ��ǂ̂悤�ɕ]�����邩�Ƃ������Ƃ����낤���Ǝv���܂��B
���ꂼ��̗�����Ⴄ�Ƃ������ƂŁA���̉��ɏ����Ă������܂����A�@�A�A�v���O�����Ɗw�K�p�f�[�^�Ƃ����Ƃ���͑n��̂��߂̃C���v�b�g�ł������܂��̂ŁA�������ɑ��Ă���^�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A��̂ƍl���邱�Ƃ��K�����ǂ����Ƃ����Ƃ���ł������܂��B
�w���������l�Ƃ����̂́A�w���̓x�����ɂ���Ă��֗^�̓x����������Ă���A���邢�͑g�ݍ��킹�ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�������܂����A������ǂ��]�����邩�Ƃ������Ƃł������܂��B
�n��ߒ��ւ̊֗^�Ƃ����Ӗ��ł́A�w�������Ăł������̂���I�ԂƂ����悤�Ȃ`�Ə����Ă���悤�ȏꍇ������A�w���͂���A�{�^���͉�������ǂ��A�o�Ă������̂��ǂꂪ�������Ƃ������Ƃ�AI���I��ł��܂��ďo�Ă��邮�炢�́A�P�ɒ������Ă��邾���݂����ȏ�ԂɂȂ�ꍇ������Ǝv���܂��B
�܂��A�n����ɓ����Ƃ������ƂŁA�l�H�m�\�����������p�\�ɂ��邽�߂ɊJ��������w������Ƃ������悤�ȍs�ׁA�����������Ƃ�����ǂ��]�����邩�Ƃ������ʂ����낤���Ǝv���܂��B
19�y�[�W�́A�����̓��e�Ƃ������ƂŁA���Ɍ�����t�^����ꍇ�ɁA���̗��v�ɏƂ炵�Ăǂ��������e�ɂ���̂��Ƃ������ƂŁA�ی���Ԃł��Ƃ����~�������̗L���ł��Ƃ��A�͈͂Ƃ��������Ƃ��_�_�ɂȂ낤���Ƃ������Ƃŋ����Ă������܂��B
�Ō�A20�y�[�W�ł������܂��B������AI�n�앨��ΏۂƂ����V�����m�����K�v���ƂȂ������ɁA����͂Ƃ����c�_�̑����ł����A�����̔����v���Ƃ������ƂŁA�ǂ������ӂ��Ɍ����̑Ώە�����肷��̂��Ƃ������Ƃł������܂��B����������̒m���̍l����������ƂQ�̃A�v���[�`�����蓾�邩�ȂƂ������ƂŁA�P�͋q�ϓI�v���Ƃ������ƂŁA�ł��オ�������̂ɑ��Ă̗v����݂���B�����ł͐V�K���A�i�����݂����ȗv�����������܂����A����Ɏ����悤�ȗv����݂���Ƃ����悤�ȍl�����B���Ƃ́A�葱�̂Ƃ���œo�^�������ĔF�߂�Ƃ����悤�ȁA���͂��̑g�ݍ��킹�Œm�����x�����藧���Ă���킯�ł������܂����A�����������A�v���[�`���ǂ��l���邩�Ƃ����Ƃ���ł������܂��B
�Ō�ɁA�G)�Ƃ������ƂŎ��R�l�̑n��ی�Ƃ̊W�ɂ��Ă��A���̋c�_��˂��l�߂Ă����Ǝv�l���y�ԂƂ����Ƃ���Ő������Ă������܂��B����AI�n�앨�ɂ��ĕ�����`�A�o�^��`�̂悤�Ȃ��̂��̗p����ƂȂ����ꍇ�ɒ��앨�ɂ��ẮA���R�l�̑n��͖������ŁAAI�̏ꍇ�͕����Ƃ����Ⴂ�����܂�邱�ƂɂȂ�Ƃ����Ƃ�����ǂ̂悤�ɍl���邩�Ƃ������Ƃł������܂��B���R�A���R�ɍl����ƁA�P�ӂɔC���Ă��������ł͕֗��Ȗ�������`�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����ƁBAI�n�앨�̕�����`�Ƃ����̂���������@�\���������A�Љ�ɃC���t���Ƃ��Ă�肽���Ƃ����Ƃ���܂ŋc�_�������̂ł���A����͉��炩�����ɗU������悤�ȃC���Z���e�B�u�v�A����͎��R�l�ɂ͑n��̎��������Ƃ������Ƃ��܂߂āA�������������Ƃ��l���Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����Ƃ�������N�������Ă��������Ă���܂��B�������ψ��� ���肪�Ƃ��������܂����B
�ł́A�c�_�Ɉڂ肽���Ǝv���܂����A���̘_�_�Ɋ֘A�������܂��āA�{���͐ԏ��ψ�����v���[�������肢�������Ǝv���Ă���܂��B�ԏ�����A��낵�����肢�������܂��B
���ԏ��ψ� �v���[���Ƃ����܂����A���̉�͏����^�ʖډ߂��܂��B��コ��A3D�v�����^�[�Ȃl�b�g�Ō��킹��ƁA�G�b�`�ȖG���t�B�M���A������@�B�ł���ˁB���͂��������F���ł��肪�Ƃ��������܂����Ƃ������\���グ���̂ł�����ǂ��A����̈ψ���Ŏ����ł��咣�������������悤�₭�o�Ă����ƁB����́A���{�ɍ��A���w���Ƃ������ς���������Ⴂ�܂�����ǂ��A�͉̂Ȋw�Z�p�Ƃ��w�тɗ������̂ł�����ǂ��A���̗��w���͊F����A���{�̖���E�A�j�����y���݂ɂ���Ă��邱�Ƃ������������ƁB
�֎q�Ƃ��t�H���g�Ƃ����S�Ƃ��������ł�����ǂ��AAI�ɂ���Đ��ݏo�����L�����N�^�[�̎�舵���������A���͓��{���ł����ӂƂ�����̂ŁA���E�ɐ�삯�ĕی�𐄐i������ǂ����Ƃ����咣�����̏�ł����Ă������������Ǝv���܂��B���_���Ɍ����܂�������ǂ��B
�܂��AAI�Ől�X�ɍD������A����͎��͍ŏ��̂��̉�Ō������̂ł�����ǂ��A�G���͖ڂƂ��@�Ƃ����Ƃ����낢��i�������݂����Ȃ��Ƃ��ł����ł��B�ŋ߂́A�@�Ȃǂ͓_�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂�����ǂ��A�̂͂����������������肵�܂��B���͈��g���C�ł��B�ڂȂǂ͉����Q�ŁA�c���P�ł��B�E�́A�܂ǂ��}�M�J�ł�����ǂ��A��̏c���Q�ŁA���P�ł��B���������`�ŁA�͂��̊G���Ƃ����̂̓p�����[�^�[�Ŋ��ƊǗ����Ă������ł��B�܂ǂ��}�M�J�̊�̉����x�͂������ł�����ǂ��A����悭���Ǝv���܂����A���킢���ł���ˁB���������悤�Ȍ`�ŁA�ǂ�ǂ�͂��p�肪�����āA���̌����Ƃ���A������O���t������ƁA�ǂ����ŋ߂͂���Ȋ����̊G���͂�肾�݂����Ȃ��̂�AI��������킩��悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB�����A�����������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�����A��X���ڎw���̂͐��E�I�ɍD����₷���G���L�����A�G���G����AI���쐻��������ƁB������L�����N�^�[���i�Ƃ��Đ��E�ɗA�o����B�G����\�z���āA������A�o���āA���{�̃t�@���������Ă������ƁB�����������Ƃ͊؍��̓h���}�Ƃ��ŃK���K������Ă���킯�ł���B����͍��O�ł��B
�����Ɋւ��ẮA�D����₷�����L�����A���L�������݂�Ȏ����悤�Ȃ��̂ł�����ǂ��A�����ɂ��D�����̂͌��܂��Ă��܂��B�����������̂�AI�ł����āA�����Ɉ������V���{���ɂ���ƁB����AI�����邩�Ƃ����ƁA�f�U�C�i�[������ƖG���L�����͌��\�ٔ��ɂȂ����肷�邱�Ƃ�����悤�Ȃ̂ŁA���ۓI�Ȃ��̂�AI���������炢���̂ł͂Ȃ����ƁB
�ł��}�l�^�C�Y���₷���̂̓L�����N�^�[�̌����A�L�����N�^�[��AI�ɂ��点��̂���ԗL���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���������l���v���f���[�T�[�A�����āu�o�v�ƌ����܂�����ǂ��A���͖���ƂȂ̂ł�����ǂ��A���v���O���}�[�Ȃ̂ł��B�f�U�C�����ł��ăv���O�������ł���N���G�C�^�[�A���݂����Ȏ҂���Ԗׂ��铹�Ƃ������̂����ꂩ���Ă����Ă������������Ǝv���܂��B
���̑O�ɁAAI�Ƃ͊W�Ȃ��̂ł�����ǂ��A��҂Ƒn�앨�̊W���ɂ��ĐV�����B����́A���̍�i�́u���u�Ђȁv�Ƃ������̂ŁA���w���̂������l�C�̂������L�����N�^�[�A�O�����̂Ԃ����ł��B���̂Ԃ����͍ŏ��A���Ȃ��ł��킢�������̂ł�����ǂ��A���������ɂ�ĉE���̂悤�ɁA�h��Ńo�^�o�^����悤�ȃL�����ɂȂ��Ă������̂ł����A�����O�邵�Č��\�ǂ��ł��悭�Ȃ������ɁA�`�̂Ƃ���Ɍ��\�ǂ��ł������Z���t�����Ă��܂�����ł���B����������ǎ҂�������܂��āA�t�@�����^�[�Łu���̂Ԃ����͂���ȕ������͂��܂���A�搶�v�ƌ���ꂽ��ł��B�����`�����̂����琳���ł���ˁB����́A���̂Ԃ����Ƃ����̂́A���̎��Ɋ��ɃL�����������Ă����ƁB�L������������Ƃ����̂́A���̃L�����N�^�[�̐��i��s���A�\��Ƃ�������ǎ҂݂�Ȃɒm��n���āA�P�l�̓Ɨ������l�i�Ƃ��ĔF������邱�Ƃł��B���̂��̂Ԃ���ǂ��������Ƃ��������A�ǂ��������������邩�Ƃ����̂́A�N�����z���ł���ƁB���́A����ɔ������Z���t�����Ă��܂����Ƃ������ƂȂ̂ł��B����͂������d�v�Ȃ��ƂŁA�L������������Ƃ����̂ƁA��҂ɑ��ĕ���������Ƃ����̂́A�o���Ă����Ă������������Ǝv���܂��B
�����ŁA�₢�Ȃ̂ł�����ǂ��A�����K���ɏ������Z���t�Ɠǎ҂�������L�����N�^�[�̈�ѐ��̂ǂ��炪���������ƁB���搶�A����́A�ǂ��炪�������̂ł����B���ł���ˁB
�����ψ� �͂��B
���ԏ��ψ� �@�I�ɂ͎�����������ł���B�����A���ƃx�[�X�ɏ��Ǝ��̎��R�����ǎ҂̍K���Ƃ���i�̕i�����D�悷��A�L�����N�^�[�̈�ѐ��������܂��B�����������K���ȃL�����ɂ��Ă��܂��ƁA��i�͔���Ȃ��Ď���ł��܂��Ƃ������Ƃł���ˁB�����������̂Ƃ����̂́A���̊Ԃ̃I�����s�b�N�̃��S�ŁA����͂ǂ������쌠�I�ɂ͂����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł�������ǂ��A���ۂɎg���͍̂����Ȃ̂ŁA�@���Ƃ��W�Ȃ��ŁA���������炻��͂���ς肾�߂ɂȂ��Ă��܂��ƁB
�����ʼn����ł�����ǂ��A�L�������������n��L�����N�^�[�A�����AI�ł����ł������ł�����ǂ��A���O�Ɏ���邽�߂ɍ�҂��������ƁB���p���O���́A�����L�[�p���`�搶�ł��E���܂����B�E�������ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂�����B���c�搶�����t�B���E���Ȃ��̂Ɠ������Ƃł�����ǂ��A�Y�ƂɂȂ��Ă��܂�����E���Ȃ��킯�ł���B
�����ŁA���ł̖₢�Ȃ̂ł�����ǂ��A����͕���搶�Ƃ悭�c�_���Ă���̂ł����A���炩�Ɍ���Ȃ̂�����ǂ��A��҂��C�ɓ����Ă��Ȃ��̂ŕ��ꂽ��i�`�Ƃ����̂�����܂��B�����������̂͌��\����̂ł����A��i�`�̍�҂Ƃ����͕̂���搶�A�������̂ł����B
������ψ� ���������쌠�I�ɂ͂ł��܂��ˁB
���ԏ��ψ� �ł���ˁB���̈ψ���Ƃ����̂���Ƃ̖{�ӎ����`�Ȃ̂��A��i�{�ӂȂ̂��Ƃ����̂��A���͂܂����\�킩�肩�˂Ă���̂ł����A���͍�҂ł͂���̂�����ǂ��A���ƍ�i�{�ӎ�`�Ȃ�ł���B���ۂɁA���◝�G�Ƃ����搶�̌��삪����̂ł����A���͊G���C�ɓ����Ă��Ȃ�����Ɠd�q�������Ȃ���ł���B���͂��������J���Ă��܂��B�S�R�W�Ȃ��b�ł��݂܂���B
���ɁA�n��L�����N�^�[�̗e�p�ł��B�����3D�L�����N�^�[��saya�����B���A�D���A����B����Ƃ��������f���̐l���͂��Ȃ������Ȃ̂ł�����ǂ��A���ۂɍ�҂̕��X�������Ă���̂ł����A���̃L�����N�^�[������ׂ点��A�������ƁB�����Ȃ����ꍇ�A�����������\���グ����ѐ��ŃL�������������ꍇ�ɁA�����A�ςȂ��Ƃ���������ATELYUKA����A�ΐ�v�Ȃ͔ᔻ�����\���������ł���ˁBsaya�����͂���Ȏq����Ȃ��ƁB
AI���e�p�������Đ��ƌ��������ăL������������ƁA�A�C�h���̂悤�ɍ����̎x�����闧��ɂȂ蓾��ƁB����͏������Ƃ��A�����֎~�Ƃ��A��X�A���ɃI�^�N�̗��z����������Ă���킯�ł���B���{�͓��ɁA�����~�N�������Ȃ̂ł�����ǂ��ACG�L�����ɋ��S�͂����鍑�ł��B�Ȃ����A�|�P�����̗�Ȃǂł����ƁA�|�P�����̊G���͑S���E�W�J�ł��Ă��܂��ƁB�G���Ƃ��i�D�����Ƃ������̂��ǂ�ǂE�ɔF�߂����āA�ǂ�ǂʂ̂��̂ɂȂ����Ƃ����̂����̔F���Ȃ�ł��B
�������炪�{��ŁA��قǂ̈֎q�A�����A�t�H���g�A���S�������ł�����ǂ��A��X���ڎw���ׂ��́A�ő�ɗL�p�Ȃ̂�AI���L�����N�^�[������A����Ɠ��ꉻ����ƁBAI���g���e�p�������āA��iPhone��Siri�����܂�����ǂ��ASiri�͗e�p���Ȃ��ł���ˁB������A���܂�������ړ��ł��Ȃ��ł��B���Ɛ��i�āA�������A�����Ƃ��炭�����悤�ȁA���p���O���������烋�p���̐��Ƃ����̂́A��X�͂����킩��ł͂Ȃ��ł����B�����~�N�̂悤�Ȍ`�ŁA��ѐ���ۂ������ăL�������������ƁB���̎��ɁA����AI�������ɋ�����ꂽ�悤�ȉ̂��̂�����A�V���[�g�V���[�g����������A�A�C�h��������������A���f��������������A�쎌��Ȃ���A�����������Ƃ��s���Ă����Ƃ������ɁA��قǐ\���グ���A�N�����m��Ȃ���ѐ��������Ă��������ɁA���͂���ɒ���Ґl�i���߂������̂�F�߂���悤�ɂ�����ǂ����Ƃ������Ƃ��Ă����킯�ł��B�������A���̑n�앨�̌������̂͐ԏ��o�����Ƃ������ƂŁA���̎��_�ł�AI�͓���̉����ƍl����B
����ŁA�������|�C���g�ł��BAI���o�^�������앨�͖ƐŁB����ƁA�o�ł��鎄���n�삷������L���Ȃ̂ŁA�ǂ�ǂ�AI�̃L�����N�^�[�̊J���ɐ�O����ƁB��قnj����܂�������ǂ��A�q�����]����悤�ȃL�������Ȃ����x��AI�̃o�[�W�����A�b�v�����Ă����ƁB���̒��ʼn̂⏬�����A�o���Ă��܂��̂ł�����ǂ��A����AI���̂��~�N�̂悤�ɂǂ�ǂ�A�o���āA����グ�Q�{�ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��l�����킯�ł��B
�����~�N�́A�V���Z�T�C�U�[�̈��ł��B�����A���ꂪ����I�������̂́A���̗e�p���������Ƃł��B����ɂ���ĉ�X�͌��\�����ɂȂ��Ă��܂��ƁB����͊���ړ����₷����̃V���{���Ȃ�ł��BAI�����鎞�ɂ́A�e�p�A���A���i�����Ă����Ƃ����������ł���B�����I�ɂo�ł��鎄��AI�̑n�슈���ɑS�����͂��Ȃ��Ă��悭�Ȃ����A���S�t���I�[�g�n��ɂȂ������ɂ́A�ޏ��ɉ��炩�̐l���߂������̂�F�߂Ă͂ǂ����ƁB���̎��ɓ���̉����ł͂Ȃ��ł���B�����Ƃ��ӏ���F�߂āA���쌠���F�߂�ƁB�������A��قǎ��������܂�������ǂ��A���̏ꍇ�͎�����AI�̕��������B�����Ƃ����ꍇ�ł��A����AI�����z�Õ���v���Ď��̂ɂȂ������ɂ́A���ɂ͐ӔC���Ȃ��Ƃ����ӂ��ɂ��Ăق����ȂƁB��҂�苭���Ȃ�������A�L�����͍�҂Ɍ����Ă��s�����ł���ˁB�������A���v�͑S�Ăo�ɂ��Ă��܂��ƁB����ő��^���āA���^�ł��������Ⴄ��݂����Ȍ`�łǂ����ȂƁB
����̌��_�Ȃ̂ł�����ǂ��A���̊Ԏ��̓t�����X�ɍs���Ă��܂����B�W���p���G�L�X�|�̃Q�X�g�ɏ����ꂽ�̂ł�����ǂ��A79�N�Ɂu�S���h���b�N�v�Ƃ����A�j��������Ă��܂��āA���{�ł͗v����Ɂu�O�����_�C�U�[�v�ł��B��������100����������ł���B37�N�O�ł�����ǂ��A�t�����X�͓��{���D���ɂȂ����A���A�����œ����Ă�����X�݂͂�ȓ��{���D���B����́u�S���h���b�N�v�̂��������Ǝ��͎v���Ă��܂��B
���������ӂ��ɂ��āA���{���D�����Ƃ������̂��ǂ�ǂ�AI�̕���ł����E�ɔ��M���Ă����āA���{���D���ɂȂ��Ă��炤�ƁB���̓��{�̐i�ޓ��́A�Ȋw�̕���͂�����ƊԂɍ���Ȃ��̂ŁA�\�t�g�E�G�A�A�l�H�m�\�Ȃǂ̕����œ��{�����E�����������Ă������ƁB���̂��߂ɂ̓L�����N�^�[����ł͂Ȃ����Ƃ����咣�������Ă��������܂����B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� ���肪�Ƃ��������܂����B
AI�������I�ɐ��ޒm���̈������ǂ�����̂��Ƃ����_�_�ƁAAI�A�L�����Ƃ��G���Ȃǂ�V�����Ă����ėA�o����헪���ǂ��l���邩�B�ق��ɂ����낢��_�_�����낤���Ǝv���܂�����ǂ��A�c�_�Ɉڂ肽���Ǝv���܂��B
���A�����ǂ�������̂������_�_�ł��Ƃ��A�ԏ�����̖���N�ɂ��Ď���A�R�����g�A��ӌ�������A���o������������Ǝv���܂��B
���䂳��B
������ψ� �ł́A�����܂��B�ԏ�����A���肪�Ƃ��ƌ����قǂ������낢�v���[���ł����B�܂��A�����ǂ̂܂Ƃ߂���ς��炵���āA���炭����ɂ��Ă̑����I�Ȑc��H�����c�_������ɂ́A�{���͎c�莞�Ԃ����Ȃ����ȋC�����܂��̂ŁA������z���Ȃ̂��ȂƂ������Ƃ͗\�z���A�����������Ƃ�������b�����܂��B
���A�ψ�����������������Ƃ���AAI�Ƃ����̂͗��_��̓|�e���V�����ɂ͔����I�ɃR���e���c�ݏo�����鑶�݂ł��B��Љ�������������X�͂W���łP�ȂƂ������ƂɂȂ��Ă��܂����A����͂������y���Ƃ��Đl���ǂ߂��Ԃɏo�͂���̂ɖ��Ɏ��Ԃ�������V�X�e���ŁA����E���傪�����Ă���I���t�F�E�X�́A�P��20�b�ł���܂��B���̃y�[�X�ł��葱����ƁA�P�V�X�e���ŔN��157���Ȃ���܂��B����͂ǂ�ȕ��ʂ��Ƃ����ƁA�Q�N�Ԃ�JASRAC���Ǘ����Ă���S���E�̃v���̊y�Ȑ��ɕC�G���܂��B�܂�A���Ȃ蔚���I�ɗ��_�I�ɂ͂��蓾��B����Ȃӂ��ɁA���Ȃ��Ƃ��S�b�z��{�V�����N���X�̓V�˂ɂ͋y�Ȃ���������Ȃ����A�}�[�P�e�B���O�����ɂ��܂����̂�����A�s�ꐫ�Ƃ������̂͏\�������߂�1,000���~�P�ʁA���P�ʂ̃R���e���c�����܂��悤�ȏ�z�肵�Đ��x�_��W�J����̂��B���邢�͍��A�ԏ����W�J�����A�ǂ��炩�Ƃ����Ƃ��Ȃ苭�����z�������������A��r�I���̌���ꂽAI�n�앨������A����������z�肷�邩�ŁA���炭���x�̋c�_�Ƃ����̂͑傫���ς���Ă���Ǝv����ł��B
�������������肵��������������A����̐l�ɂ�������o���Ȃ��悤�Ȃ��炵��AI�n�앨�ł���Ȃ�A���炭���̉ߒ��ɂ͂��̐l�̌��Ƃ������̂��\�����f����Ă���A����������i�͐������Ȃ��A�m�I���Y����^���Ă��\�����[�N���邾�낤�Ǝv���܂��B
����ŁA���l�����̃c�[���𗘗p����A���ł�����o����悤��AI�n�앨��z�肷��Ȃ�A����͖��l������ł��邪�䂦�ɐ��͋��炭���ӂ�邾�낤�Ǝv���܂��B��������ƁA�M�K�R���e���c�Ƃ����悤�Ȃ��ӂꂽ���̂ɉʂ����Ēm�I���Y����^���āA����̓C���Z���e�B�u������Ń��[�N����̂��A���邢�͎��v�ݏo����Ń��[�N����̂��B���̂��Ƃ��l���Ă݂�ׂ����낤�Ǝv���܂��B
�������A���l������o����悤��AI�n�앨��z�肷��Ȃ�A�������Őԏ����v���[���������̍�i�́A���炭���Ɏ����悤�ȃL�����N�^�[��AI�n��ɂ���Ă����Ă��鑼�l����i�����Ă��܂��āA�Ԃ���Ă��܂��\�����\���ɂ���܂��B�����āA�A�o���悤�Ƃ��Ă��A���l���ȒP�ɂ���o���Ă��܂����̂ł��邪�䂦�ɁA�A�o�����܂������Ȃ���������܂���B����������AI�n��̔����ʂ��ǂ��܂őz�肷�邩�A����Ȃ��Ƃ��c�_�ɂ͉e����^���邩�ȂƎv���܂����B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� �����ψ��ǂ����B
�������ψ� �ʐ^�ɂ��������Ă����ł���B�ʐ^�́A���Ƃ��ƃt�B��������S�������Ă��āA���ʂ̐l���g���Ȃ������B�����Ńt�B�����̈Î��������Ă�邩�獂�������̂ł�����ǂ��A���͌g�тł݂�ȎB��܂���ˁB�����A���ꂪ���y�ɕς���������ŁA�i���ɂ���ĒN�����ł���悤�ɂȂ�Ƃ����̂͂قړ����Ȃ�ł��B�����A�ʐ^�Ƃ����̂͐l���B���Ă���Ƃ������ƂŁA���͒��앨�Ƃ������ƂŒ��쌠������܂�����ǂ��A���̑O�̃f�[�^����������܂�����ǂ��A�l�i���Ȃ��킯�ł��B����͋@�B�����킯������A�v�z�܂��͊����\�����Ă��Ȃ��킯�ł���ˁB�I�y���[�g�����v���O����������l�ɂ̓v���O�����̒��쌠�����邾�낤����ǂ��B�������������ȁA�����Ȃ��ǂ�ǂV���Ă��钆�ŁA����ɑS�����쌠�Ƃ����̂́A�����A���쌠���z�肵�Ă������̂Ƃ͈Ⴄ�ړI�ɂȂ��Ă��܂��Ă���悤�ȋC�������ł��B������A����ɂ��Ă͉��炩�̌y���ی삪�v��̂��A�������͊�{�I�ɂ͂Ȃ�����ǂ��A����炩�̓o�^�������ɂ���Ď�������̂��B�ی삪�Ȃ��Ă����Ƃ͌����܂���B������ǂ��A���쌠�Ɛ蕪���Ă����Ȃ��Ɛl�i���Ȃ��A�v�z�܂��͊����\�����Ă��Ȃ��n�앨�ɂ��āA���Ȃ��Ƃ��אڌ��̉\���͂���Ǝv���܂�����ǂ��A���쌠���̂��̂Ă͂߂邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ����ȂƎv���܂��B
����Ƃ�����A�Ⴆ�A��قǂ̃��S�̘b������ł͂Ȃ��ł����B�����������Ƃ��܂��B�Ⴆ�A�����Q�̂T�y�[�W�A���̒i�̂e�͍g����FAUCHON�Ɏ��Ă���ȂƂ����邩������܂���B�Ⴆ�A���y�ł����ł����������������̂������̂��̂Ƃقړ������̂��ł��Ă��܂����ꍇ�ɁA����͒��쌠�N�Q�ɂȂ�̂ł��傤���B����ׂ�`���͒N�ɂ���̂ł��傤���B�����āA�����m��Ȃ��ŁA����͎�������������Ƃ������Ƃ��ؖ�������Ɛӂ��Ă����̂ł����������ǂ��A�g���Ă����쌠�N�Q�ői�����āA����͎����������Ƃ������Ƃ��ؖ��ł����疳�߁B�ł��A�N�Q�̎����͎c��܂���ˁB�����������Ƃ͓��ɃV���v���Ȃ��̂قǕ����������蓾���ł��B�Ⴆ�A���S�Ȃǂ�������A�܂��ɂǂ����̏��W�Ɛ�ɓ�����܂���ˁB����������A����͂ǂ�����̂ł����Ƃ�����肪����܂��B
�ł�����A��������������ɑ��i����ׂ��Ȃ̂��A����Ƃ����̘g���͂߂�ׂ��Ȃ̂��A�ی삷�ׂ��Ȃ̂��Ƃ������������̒��ł����ƁA���쌠�ȊO�̃V�X�e���ɂ���Ď��͕ی������ׂ����Ǝv������ǂ��A���������悤�ȐӔC������ł��傤���A�����̕�����������Ƃ��Ă����A���쌠�����������y���v���}�C�̐��x���Ȃ�����A����쌠�̓y�U�Ɏ����Ă�������N�Q�s�ׂ����ɖc��ł����A���낢��Ȃ��Ƃ��N����Ǝv���܂��B�������A����ɂ��Ă͑��i���Ă����ׂ��Ƃ����A�Z�p�̐i���𑽂��̐l�ɋ��Ă����ׂ��Ƃ������ʂ�����܂�����A�ǂ�����Đ��������ɂ��ẮA�������̖��ƈ���āA�m���̖ʂ���܂��悭�l���Đ��x�v�����Ȃ��ƁA�t�ɕςȃ��X�N��ł��܂����ƂɂȂ�̂ŁA���͂���ɂ��Ă͂悭���x���l���đ��i�ł���悤�ɍl�������������Ǝv���܂��B���X�N�͂��Ȃ荂���V�X�e�����ƍ��l���Ă��܂��B
�������ψ��� ���ψ��ǂ����B
�����ψ� ���A����������ꂽ���Ƃ͂������������납�����̂ł�����ǂ��A��������ƁA�����AAI�ɒ��쌠���F�߂�ꂽ�ꍇ�A�����������Ă����ꍇ�A�Q��AI���������ꍇ�ɂǂ��炪��ɂ��̃��S���������̂��݂����ȁA���������킯�̂킩��Ȃ��c�_�ɂȂ��Ă��܂��āA��{�͋@�B�ł��������̂ɒ��쌠��F�߂�Ƒ�ύ�������肪�N����Ƃ����̂́A����͔��ɂ悭�킩��b���Ǝv���܂�����ǂ��A���́A�_�_�����̂Ƃ���ɂ������Ă���܂�������ǂ��A�l�Ԃ����������̂Ƌ�ʂ����Ȃ��Ȃ�\���������B���������ꍇ�A����͎��������������̂��ƌ����������l�ɑ��Ăǂ��R����̂��Ƃ����̂͊�{�I�ɂ͂ł��Ȃ����낤�ƁB�ł́A���̒��ʼn����l����̂��Ƃ����ƁA���̒��œo�^���ɂ��ׂ��ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂�������ǂ��A���ǁA�l�Ԃ̋�ʂ��Ȃ��̂�������o�^���ɂ��Ă����ʓI�ɂ͓������ƂŁA���앨�ɏ���Ɍ������������Ă��܂��Ƃ�����Ԃ͔������Ȃ��B��������ƁA���s�̒��쌠���̂�o�^���ɕς��Ȃ��Ɛ��藧���Ȃ��Ƃ����̂��A�����Ă͂��Ȃ�����ǂ��A���̌��_���Ǝv����ł��B
��������ƁA����͂ǂ������Ȃ̂��Ƃ����ƁA�Ⴆ�A�����q�b�g�����A�q�b�g�A�j���A�q�b�g�f�������܂����ƁB��������ƁA�ǂ����̃T�[�o�[�ɃA�b�v����Ă���n�앨�ŁA����͉������������̂��ƁA�T�u�}�����R���e���c�݂����Ȃ��̂�����đi������݂����Ȃ��Ƃ��N���������ɂǂ�����̂��Ƃ����̂���Ԃ킩��₷���Ǝv���̂ł����A��������ƁA���쌠�Ƃ����͍̂���A���W���ɋ߂��悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����ƁB�܂�A��i���̂��̂������̌|�\�l�Ȃǂ��킩��₷���Ǝv���܂����A�Ⴆ�ASMAP�̌����͂ǂ��ɂ���̂��Ƃ����̂ŁA�����ڐЂ̎��ɖ��ɂȂ�܂�����ǂ��A��̖��O�̑����ɂȂ��ł��B�Ȃ����Ƃ����ƁA�|�\�l�̖��O�ɑ��Ď������͂����������A�}�[�P�e�B���O�R�X�g�������Ă���̂ŁA���������Ɏ����Ă������̂͂��邢�Ƃ����_�@�Ȃ̂ł�����ǂ��A�����A�������Ƃ��āA�@�B�̒��쌠����ʂɂ��ӂꂽ���̒��̏ꍇ�́A������������̂��N���Ƃ��������A������g���Đ��̒��ɍL�߂āA�v�����[�V�������ĔF�m���Ă�����āA�����ɉ��l�����܂��̂��Ǝv���܂��B�����ی삷��Ƃ����̂������ƌ����I�Șb�Ȃ̂��낤�ƁB��������ƁA�����Ă��邩�ǂ����ł͂Ȃ��āA���앨�����ۂɎg���Ă��Đ��̒��łǂꂾ���F�m����Ă���̂��Ƃ����Ƃ��낪�����Ƒ��_�ɂȂ�ƁA�����A�����ł͂����������Ƃ��N����̂��Ǝv���܂��B���ʓI�ɁA���o�^��`�Ƃ����͕̂ς��Ȃ��̂�������܂���ǂ��A���ۂ̐N�Q���f�ɂ����ẮA�������W���Ǝ����悤�ȋc�_�ʼn��߂����悤�ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B
�ԏ��������Ă���̂������A�����������E�ɋ߂��b���Ǝv���Ă��āA���ǂ��������̂����A���q���F�m���Ă���Ƃ���Ɏ��ۂ̉��l���\���̂��Ƃ������Ƃ��Ǝv����ł��B�����̉��l���ǂ�����ĕی삷��̂��Ƃ����c�_�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂��A���̊��������Ƃł��B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� �T��ψ��ǂ����B
���T��ψ� ���肪�Ƃ��������܂��B����A�s���ŏo���܂���̂ňꌾ�����\���グ�܂��B
�����ǂ��������ꂽ�悤�ɁA�����A�ꌩ���앨�Ƃ������̂�������̂�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�����A����ł��ꌩ���앨�Ƃ������̂͐��̒��ɑ�������Ǝv���܂��B������������������̂������悤�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B���ǁA�����セ��ʼn����N���Ă��邩�Ƃ����ƁA�����ɂ�������X�y�N�g���ĕی삷��`�Ő��̒��������Ă���ƁB�ی삪���闝�R�Ƃ����̂́A���炭���ɓI�Ƃ������A����͖@���̖ړI���Ǝv���܂�����ǂ��A�ʂɖڂ̑O�ɂ�����̂𗘗p�������ɁA�ٔ����ɍs���čٔ��łǂ����f����邩�Ƃ����Ӗ��ő����A�ی삪����̂��Ǝv���܂��̂ŁA�����������F�������@�_�ɍs���Ă���Ƃ���ɂ�����ƒE�͓I�Ȃ̂ł�����ǂ��A�ٔ��ɔC��������̂ł͂Ȃ��̂Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B���ǁA���쌠�@�őn�쐫�����邩�Ȃ����Ƃ����̂́A�ʂ�AI�Ɍ��炸�A���������`�ŏ�������Ă���킯�ł��̂ŁA���炭�ς˂�����̂ł͂Ȃ����ƁB���ɓo�^��������Ƃ��Ă��A�o�^���鎞�ɔ��f�ł���̂��Ƃ������������̖�肪�����āA�{�l�̌����Ȃ�ł��킯�Ȃ̂ŁA�]��ς��Ȃ����ȂƂ����C���������܂��B���������āA������Ɛ��̒��̐��ڂɍ������čl����ƁB
���ꂩ��A���A��コ��̂�����������_�A���邢�͐ԏ����v���[���e�[�V�������ꂽ�悤�ȁA�v���f���[�T�[�I�Ȓn�ʂɂ���l������ŗ��v���グ�Ă��鎞�ɁA����ɑ��Ăǂ��ی삷�邩�Ƃ����̂́A�������̑̑��̒��ł���̂�������܂���ǂ��A����͈�ؒ��쌠�Ƃ͊ւ�肪�Ȃ��A�������ǂ���邩�Ƃ����ϓ_�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� ���z�ψ��ǂ����B
�����z�ψ� ���̋T�䂳��̍ٔ��ɔC��������Ƃ����Ƃ���ŁA�S�Ă̂��̂��������Ƃ������Ƃɂ͂܂����Ԃ�������ł��傤����A���̉ߒ��őn�쐫�Ƃ����Ƃ���̎�舵���ŁA���A�n��҂Ƃ����l�Ԃ��������Ƃ��납��b�������Ă���킯�ł�����ǂ��A�������l��L����Ƃ��A�G���L�����Ƃ����܂߂ĐV������@�ŐV�������l��L����Ƃ��A�n�쐫�Ƃ������̂ɂ���AI���֗^�������͎������������Ƃ��Ă��A�l�Ԃ��������Ƃ��Ă��n�쐫��F�߂�ꍇ�Ƃ����̂͂ǂ��������l�������Ă���̂��Ƃ�����������K�v�ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ƁA��قǐ�コ��̂��b�ŁA���W�̎g�p��`�I�Ȏg�p�ƌ��т����悤�Șb���������̂ł�����ǂ��A��i�ɂ��čl���Ă݂�ƁA�Ⴆ�Ύ���ł��܂��Ă��甄���Ƃ��A�l�Ԃ̉\���Ƃ��Čォ��C�Â����|�p�Ƃ������������̂�����̂ŁA���ꂩ��AI���앨�Ɛl�Ԃ̂��������̂ŁA�������A�������V�������l�������Ă�����̂ƁA�������ȒP�Ȃ��̂����݂���Ƃ���̖�肾�Ǝv���܂��̂ŁA���̒��Ől�Ԃ����������̂ł��邪�䂦�Ɍ|�p�����ォ��F�߂���Ƃ������������Ƃ�����Ǝv���̂ŁA���쌠�@�ł͏����߂Ș_�_��������܂���ǂ��A�⑫���K�v���ȂƎv���܂��B
�R�ڂ��A���낢��ȉ��l�̂����������A��ʂ̒��앨���ł��Ă������ɁA���~��S�ĔF�߂�̂��Ƃ��A�Љ��������قǗ��p�I�ȏƂ������̂�������悤�ł�������A����ɂ��Ă͎蓖���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����̂ŁA�v�������R�ɂ��ďq�ׂ����Ă��������܂����B
�������ψ��� ���ψ��ǂ����B
�����ψ� �ԏ��搶�����قǔ��ɋ����[�����b�����f�����܂��āAAI�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�A�����Ă݂���o�[�`�����L�����N�^�[�݂����Ȃ��̂̐l�i�A���S�Ƃ��̕ی�AAI������o�������́A���ꎩ�̂Ƃ���������o�����L�����̕ی�Ƃ������ƂŔ��ɋ����[���̂ł����A�܂����̒��ł��܂������ł��܂���̂ŁAAI�ɂ���č쐬���ꂽ���̂ɂ��Ă̕ی�Ɋւ��ď����R�����g�������Ǝv���܂��B
��߂�����������l�́AAI�Ƃ��ʂ�20�N�O�A30�N�O���炠�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA�{���Ɏ��I�ȈႢ������̂��Ƃ������Ƃ������邩������Ȃ��Ǝv���Ƃ��������܂��āA�m���ɖc��ȗʂ������������Ȃ��ł͂Ȃ����Ƃ����w�E������Ƃ��Ă��A�Ⴆ�A���A�ɓ���������ɔ������͗l���ǂɂ����āA����������ċA�����l������킯�ł��B���邢�͏ߓ����ɓ���������ɔ����������݂̂����Ȃ��̂������āA����������ċA�����炻�̐l���������̂�������Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��킯�ł�����ǂ��A�����������̂͒��쌠���Ȃ��ƍl���Ă����킯�ł��B�����A�����������̂����ɖc��ɂȂ��Ă��āA�ʓI�Ȃ��̂����I�ȈႢ�ɂȂ��Ă���Ƃ��܂��ƁA���߂Č������K�v�ł͂Ȃ����Ƃ��������ǂ̂��l���Ɏ��͎^�����܂��B
�����A���쌠�̐��E�̏]���̍l���ɂ��܂��ƁA��������Ă���Ƃ���ł�����ǂ��A�l�Ԃ����������̂��ی�̑ΏۂɂȂ��Ă��܂��̂ŁAAI������ƌ��������ɂ����܂��ẮA�l�Ԃ����������̂ɂȂ�܂�����ی삳��܂�����ǂ��A�����ł͂Ȃ��ƒm���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂���B�m���ɁA�s��I�ȉ��l�Ƃ����̂͂���킯�ł����A�]���̒m���@�̎�|�Ƃ����̂́A���������s��I�ɉ��l���������f�[�^��ی삷��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�N���G�C�^�[�ɂ���Đl���������Ƃ����s�ׁA���邢�͐l��ی삷��Ƃ������Ƃł��̂ŁA�����炱���������������̂ɂ��Ă��ی�͗^�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B�����A��������ƁAAI�����������̂ɂ��Ă͑S�R�R�s�[���Ă��t���[���C�h�A���R�ł����̂��Ƃ������Ƃɂ͊m���ɂȂ�Ƃ���ŁA���炩�̕ی삪�K�v�ł͂Ȃ����Ƃ����Ƃ���͎�����������Ƃ���ł��B�����ł͑I��������������܂��̂ŁA����͐�قǐ����ψ���������b������܂����悤�ɁA���܂��܂Ȃ��̂����蓾��Ǝv���܂��B
sui generis�Ƃ��אڌ��Ƃ������́A�ʂɑn��ƊW�Ȃ��Ă�����������Ƃ��������ł��ی�̗��R�ɂȂ�܂��̂ŁA�C���Z���e�B�u�ɂƂ��Ė{���ɕK�v���Ƃ������Ƃł���A�����������̂��I�����̈�ɂ͂Ȃ낤���Ǝv���܂��B�����A����������A���̕K�v�������݂���̂��ȂƂ����Ƃ���́A�l�I�ɂ͏����^��Ɏv���Ă���Ƃ��낪����܂����A�܂��AAI���쐬�������̂Ƃ����̂́A�Ⴆ�Ύ����|�ꂽ���̂Ƃ��A���܂������悤�Ȃ��̂�����܂��̂ŁA��ʂł���̂��ȂƂ͎v���Ă���܂��B
�ȏ�̘b�́AAI�ɂ���č쐬���ꂽ���̂̕ی�Ƃ������ƂȂ̂ł�����ǂ��A���낢�남�b���Ă�����ƐS�z�ɂȂ�̂́AAI�ɐV���ȑn�앨�����点��Ƃ������ɁA�����̗Ⴆ�Ώ����Ȃǂ�S�����͂��Ă�������\���Ƃ��A���邢�͊����̖����S������āA���ɗ��s����̂����点��Ƃ������ɁA��͂Ƃ�������ł͌���̒��쌠�@�A���s�@�̘b�ɂȂ��Ă��܂��܂�����ǂ��A��47���̂V�Ȃǂ����e�����Ƃ��납�Ǝv���܂����A�ł��オ����AI�쐬�������̂�������r�b�O�f�[�^�Ƃ��ē��͂������̂̑n��I��^���c���Ă��܂��Ă���ƁA�f�Ђł����Ă����쌠�N�Q�ɂȂ肩�˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���S�ɏ������Ă���Ƃ����̂ŏ����Ă��܂��Ă�������킯�ł�����ǂ��A������ƐS�z���c��Ƃ���ł��B
����́A�O�ɋT��ψ�������ʂ̈ψ���ŁA�V���������|��ȂǂŁA�����̓��͂������͂��ꕔ�o�Ă��Ă��܂��āA���ꂪ���쌠�N�Q�ɓ�����ƂȂ�Ɩ��ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E���������킯�ł�����ǂ��A�����悤�Ȃ��Ƃ������ł������ۑ�ɂ͂Ȃ蓾�邩�ȂƎv���܂��B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� �R���ψ��ǂ����B
���R���ψ� ������͂��ЁA�ԏ��搶�Ɍ䎿��\���グ�����̂ł�����ǂ��A���̑O��Ƃ��āA�������̍l�����q�ׂ����Ă���������Ƒ����܂��B�{���̃Z�b�V�����ɂ�����3D�v�����e�B���O�̘b������AI�̘b���A��{�I�ɂ́A�����őn������̂�֘A����n�앨���ɂ��ẮA���s�@�̘g�g�݂Ɋ�Â��ā\�\�m���Ȃ������쌠�݂̂őΉ����邩�ǂ����͕ʂɂ��Ă��\�\�A������x�͑Ή��ł��������Ƃ����̂��A�����炭�@���ƂƂ��Ă̗����Ȋ��o�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��قǂ́A�R���s���[�^�[���n�������̂Ɋւ���30�N�O�̋c�_�Ɖ����ǂ��Ⴄ�̂��Ƃ����_�_������܂����A�{�ψ���ł̋c�_�̎�|�Ƃ��ẮA������̒m���̃V�X�e���ɂ��āA�����V�������x�Â��肪�ł��Ȃ����A�Ȃ����̓C�m�x�C�e�B�u�Ȃ��Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ�ڎw���āA���̋c�_�̏ꂪ�ݒ肳��Ă���Ǝv���܂��̂ŁA���s�@�̘g�g�݂��x�[�X�ɂ����A�����ď������̐��ڐ����ĉ����ł��邩�Ƃ����ϓ_����A�䎿�₵�����Ǝv���܂��B
�ԏ��搶�Ɍ�p�ӂ��������������R�̍Ōォ��Q�y�[�W���ɂ��āA�䎿��̑O�ɁA�����������̍l�����q�ׂ܂��B���Ȃ݂ɁA���̋c�_�Ɋւ��āA�{�ψ���̍ŏ��̕��̃Z�b�V�����ɂ����āA�����Ń^�[�Q�b�g�ɂ���c�_�̃^�C���X�p�����ǂ̂悤�ɐݒ肷�邩���߂����āA��r�I���݂̉�������ōl����̂��A����Ƃ��A�Ⴆ��AI�ł����̎��������v�����Ȃ��悤�Ȑ�̎���\�\�ԏ��搶�������Ă����������悤�ɁA����Ӗ��Ől�i���������w��SF�̂悤�Ȃ��̂��܂߂đ傫�Șb������̂��ɂ��āA�ӌ������������Ƃ���ł��B�����ŁA�^�C���X�p���ŋc�_���āA�܂��͔�r�I���݂̘b�Ƃ��Č��s�@�̊�{�����Ȃǂ��K�p�����ݒ�ōl���Ă݂܂��ƁA�����ɏ�����Ă���悤��AI���l�i�����i�K�ɂȂ����Ƃ��Ă��A���̎����ł́u�o�v�Ȃ����u��������l�v��v���O���~���O�������l����Ɂu���������v�v��������Ƃ����b�ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂����A����قǁu�o�v�����܂��ׂ���b�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�Ƃ����܂��̂��A�Ⴆ�AAI�̍s�ׂɂ���āA�Ȃ�����AI������o�����n�앨�̍s�ׂɂ���āA���炩�̖@�I�ȋA���������炳�ꂽ�ꍇ�ɁA���Ƀv���X�ʂƂ��Ă̌����◘�v������̂��u�o�v�ł���A���̃}�C�i�X�ʂƂ��Ă���ɔ����ӔC�������͂��Ƃ������ƂɂȂ�A�K��������̂ƐӔC��̂��Z�b�g�ɂȂ��Ę_������Ƃ����̂��A��͂�t�F�A�ł���悤�Ɏv���܂��B
�����Ď��ɁA�����_�ł͂ƂĂ��l�����Ȃ������̎�����V�X�e���̉��ŁA���̐ݒ�ł̘b�ł����A�l�Ԃ̋@�\���ꕔ�ǂ��납�S����ւ���悤��AI���o�ꂵ�āA����AI�����ꑊ���́u�l���v�\�\�m���̗̈�ł̌����̘b�݂̂Ȃ炸�A���@��̊�{�I�l���������\�\��F�߂����̂ƂȂ����ꍇ�ɁA��������AI�ɐ�قǂ́u�o�v�������Ƃ��Ă��A�Ⴆ�Ύg�p�ҐӔC�̂悤�ȉ��炩�̌`�Ń}�C�i�X�ʂł̋A���������邱�ƂɂȂ�\���͔ۂ߂܂���̂ŁA��Ɂu�o�v�������u���������v�v��������Ƃ����̂́A��͂萧�x�_�Ƃ��Ă̓t�F�A�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B������ɂ��Ă��A���̂悤�ȁu�o�v�́u���������v�c�_�́A�@���x�Ƃ��ăo�b�N�A�b�v����͓̂���C�����܂��B
���āA�����ŁA��قǂ̖{�ψ���ł̋c�_�̎�|�ɗ����߂��čl���Ă݂܂��ƁA���̂悤�Ȍ��s�̖@���x�_�̘g���ŏ�����_���Ă���ƁA�Z�p�̐i���ƂƂ��ɁA������������������x�v���N���G�C�e�B�u���C�m�x�C�e�B�u�ɍs�����Ƃ��Ă��A�c�_���Ȃ��Ȃ��O�ɐi�܂Ȃ��Ȃ�A���@�_�Ƃ��Ă̂悢�A�C�f�A���o�Ă��Ȃ��A�Ƃ��������ƂɂȂ肩�˂܂���BAI�̌����Ȃ����ӔC�̎�̂Ƃ����_�_�Ɋւ��Ă��A����AAI�̑n�앨�ɂ��}�C�i�X�ʂƂ��āA�m���W�̑��ɂ��A�Ⴆ�A�ꍇ�ɂ���Ă͑��l�̖��_��ʑ����邩�����ꂸ�A�l���̎戵���Ŗ�肪���邩�����ꂸ�A�܂��A�����Ǒ��ɔ�����悤�Ȃ��̂��ł��Ă��邩������Ȃ��Ƃ����ɂ����āA�����āA��قǂ̐��x�v�ɂ����āA�}�C�i�X�ʂł̋A���͂��Ă����āA�v���X�ʂ��d�����ĎЉ�ɂƂ��Ė]�܂������̂�����o����C���Z���e�B�u��^����悤�Ȗ@���x��V���ɐv����ƂȂ�A�Ⴆ�ǂ��������̂��l������̂��Ƃ�����̓I�ȃA�C�f�A���A�K�v�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����܂ł��Ⴆ�Ƃ������Ƃł�����ǂ��A�m���̗̈�̘b�ł͂���܂��A�A�����J�ɂ�����1996�N�ʐM�i�ʖ@��230���̉��ł̂�����ISP�Ȃ������Ԕ}��҂̖Ɛӂ̂�����́A�W�̃X�e�[�N�z���_�[�̌������v��ӔC���ǂ̂悤�ɋK�肷�邩���߂����āA����Ӗ��ł͑����ɂ͌����Ȃ��悤�Ȍ`�ł̐��x�̐v�Ɖ^�p���s���Ă������Ƃɂ���āA�������c�_������Ƃ���ł����A�����̃v���b�g�t�H�[�}�[�̃r�W�l�X���܂ރl�b�g��̏������ɁA���Ȃ���ʉe���Ȃ����̓C���v���P�[�V�����������炵�Ă����悤�Ɏv���܂��B���������ʐM�i�ʖ@�̉��ł�ISP�Ɛӂ́A���쌠�@�Ɋ�Â��ƐӂƂ͂܂��ʂ̑[�u�ł����āA�m���̘b�ƈ�T�Ƀp�������ɂ͘_�����܂��A���ɍ����AI�̘b�Ɨ��߂āA�O���[�o�������̒��ł̍���̓��{�̐��x�v�Ƃ��ĉ����ł��邩�Ƃ����挩�I�ȃA�C�f�A�ɂ��āA�R���e���c�E�N���G�[�V�����̒��S�Ŋv�V�I�Ȏ��݂�����Ă���ԏ��搶�̂��b���A���ЁA���f���ł���Ǝv���܂����A�������ł��傤���B
���ԏ��ψ� ���́A���̈ψ���ɎQ���������ɁA�F�����̃A�C�f�A���o��������Ǝv���Ă����̂ł����B���ƌ����I�Ȃ��b�����Ă����̂ŁB���낢��l���Ă͂��܂�����ǂ��A����Ƃ͊W�Ȃ��ɁA���A�����ƂɂȂ낤�Ƃ��ADeNA�̂d�G�u���X�^�Ƃ��ɏ�����20���Ƃ�30���Ƃ��オ���Ă����ł���B���ɏ����ƂɂȂ낤�Ƃ����T�C�g�́A��X�I�^�N�݂����Ȓj���ِ��E�ɓ]�����Ċ���̂��قƂ�ǂȂ̂ł�����ǂ��A�����A�A�j���������邵�A�ǎ҂������]��ł�����ʂɂ�����ł���B������������20���Ƃ�30���̏��������ۂɂ���A�����������̂�AI������܂ł��Ȃ��ʍ�������킯�ł��B�����݁A���ɑn�앨�̗ʎY�������ɂ���ƁB������������Ă݂�Ƒ�Ȃǂ��킩�邩������Ȃ��B���ۖ��ł����Ƒ�͂��Ȃ��Ă����B�Ƃ����̂́A���\�����̏����������Ă��ǂ܂�Ȃ��̂Ŗ��ɂȂ�Ȃ��悤�ł��ˁB
�V�����A�C�f�A�͊F����o���Ă��������B���͖��łɂ���̂������Ǝv���������ł��B
�������ψ��� �ق��ɂ������ł��傤���B�ǂ����B
�������ψ� ��������ł��Ă��g��ꂽ��A�q�b�g������A�����ɂȂ�Ƃ͑S�R����܂���B�t�ɁA��������ł���ł���قǃr�b�O�q�b�g�͓���Ȃ��Ă��āA�������̂��o�Ă��Ă��܂��̂ŁA���ʂƂ����͔̂�Ⴗ��̂ł�����ǂ��A�����Ɛ����̒��ŁA�Ⴆ�A�����̃z�[���y�[�W������Ƃ��A�{���Ɏ����̌y���ȂƂ���ł���������������̂��낢��Ȏ�ނ̒��앨���g���₷���Ȃ�B������A�����͖L���ɂȂ�܂����A���ꂪ�����ς������Ă�����Ƃ����ăr�b�O�q�b�g�ŃK���Ƃ����̂́A����͐ԏ����悭�킩��ł��傤�B�������K���Ɖ҂�����̂�����Ƃ����̂́A���낢��Ȃ��Ƃ���������ŁA���܂��܂���킯�ł����āA��������AI�łł�������Ƃ����Ă��r�b�O�q�b�g�͂Ȃ��B�t�ɁA�����قǂ̈�c����ł͂Ȃ�����ǂ��A�v���f���[�T�[�̂悤�ɂ���������������̂̒����牽���E���o���āA�ǂ��g�ݍ��킹�āA�ǂ���悷�邩�Ƃ����l�̎�ɂ��r�W�l�X�̂ق����r�W�l�X�ɂȂ�Ǝ��͂������v���܂��B
�ł��̂ŁA����̑�ʂɂȂ�Ƃ������̂̒��ł��A���ʂɗ��v����肽���Ƃ������Ƃ��������ꍇ�̕��K�v�Ȃ̂ł����āA�S�����쌠�Ŏ��܂��傤�Ƃ����c�_�ɂȂ�Ȃ���A����ɂ���Ă��Ȃ�F����̐������L���ɂȂ邵�A���̒��ł��낢��ȐV�����r�W�l�X�`�����X�̓x���`���[�������Ă����ׂ�������A�����}�����Ȃ��悤�Ȍ`�ɂ���A��r�I�����̂ł͂Ȃ����ƁB�����A���������i����ǂ����邩�͓���B�t�Ɍ����ƁA������A�C�f�A�Ƃ��r�W�l�X�X�L�[�����ǂ�����Ă������Ƃ������ƂȂ̂ŁA�ԏ����������܂ł���Ă��Ă��ꔭ�Ŗׂ�����̂͂Ȃ��킯������A����͖��ԂɔC���Ă��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁB�����ł�邱�Ƃ͕ςɗ}�~���Ȃ��悤�Ȑ��x�ɂ��邱�ƂƁA���ƁA������ƒ��쌠�Ɛ蕪���Ă������ƂƂ��A�����K�v�ł���Ή��炩�̕ی�̐�����Ƃ�ׂ��Ƃ��A���Ƃ͐헪�I�ɂ������������Ƃɑ��ăC���Z���e�B�u�ɂȂ�A���łł���������ǂ��A�����������Ő��̗D���Ƃ����炩�̃C���Z���e�B�u��^���āA�ǂ�����đ��i����̂��Ƃ��������I�Ȏ{����l���Ă����̂ł����āA�m�����x�̖ʂ����邱�ƂƂ����̂͌���I�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁA���͂��̂悤�Ɏv���Ă��܂��B
�Ƃ�������������o�đ�ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂����Ƃ͓��ʗ]��Ȃ��Ƃ����̂��A���̊�{�I�ȍl���ł��B
�������ψ��� �ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
�r�W�l�X��L�����N�^�[�Ȃǂ��ǂ̂悤�ɐL���Ă����̂��A����𐧓x�ɂ��ی삠�邢�͐Ő����܂߂Ă����Ǝv���̂ł�����ǂ��A�������������̂łǂ̂悤�ɐ������Ă����̂��B���ꂩ��A�����I�ɑ����Ă���R���e���c�ɂ�鍬�����ǂ���������̂��Ƃ��������Ƃ��ɉ����_�_�ł��Ƃ��A���������ǂ��ݒ肷��̂��Ƃ������Ƃ�����Ă���̂��Ǝv���܂�����ǂ��A�����������c�_�Ƃ����̂͂���܂ň��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�������ł������Ƃ������������o���͔̂��ɓ���Ǝv���܂��B���ꂼ��̃e�[�}���ǂ��܂ŋً}�̉ۑ�Ȃ̂��Ƃ����X�s�[�h�����������čl���Ȃ�������Ȃ��Ǝv���̂ł����A��قǂ�����������悤�ɁA���낢��ȃ^�C���X�p��������Ǝv���܂��B�ڂ̑O�̖����������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������̂�����A10�N��̏���������Ƃ��A���邢��AI�ł�����2045�N�ƌ�����V���M�������e�B�̂����z�肵�ē����߂��点�čl���铙���낢�날��Ǝv���̂ł�����ǂ��A�Ђ���Ƃ���Ƌc�_�̌��ʁA�����@�Ƃ��Ă͍ٔ��ɔC����̂���Ԃ����Ƃ������ƂɂȂ邩������܂���B
���Ȃ��Ƃ�����Ȃ��낢��ȋc�_�����̏�ŊF����ɏo���Ă��������āA�m�b���i���Ă��������āA���������\��������Ƃ��A���������_�_������Ƃ������Ƃ͉�X�Ƃ��Ă͖��L���Ă��������Ǝv���Ă���܂��̂ŁA����́A�܂��P��ڂƂ��Ă̋c�_�����Ă��������܂�������ǂ��A�����������E���h���炢�`�����X�͂���Ǝv���܂��̂ŁA������i�̐[�@������炢�ɂ��Ă���������Ƃ������ƂŁA�{�����o�������������R�����g�������ǂɂ�����x�������Ă������������Ǝv���܂��B
�Ƃ������ƂŁA�\�肵�Ă������ԂɂȂ�܂����̂ŁA�{���͂��̂�����Ƃ��邱�Ƃɂ������Ǝv���܂��B
�{�������낢��ȋc�_������܂����B�����ǒ�����ꌾ�������������Ǝv���܂��B
�������ǒ� �{�������낢��ȋc�_�����肪�Ƃ��������܂����B�O����3D�v�����e�B���O�̘b�́A�V�������̂Â������{�̋��݂Ƃ��āA��������������Ă������Ƃ����������̂��Ƃłǂ����邩���l����̂��Ǝv���܂��B���̂Ƃ��ɁA�L���Ӗ��ł̒m���ōl����ƁA�v���b�g�t�H�[�}�[�̉e���͂��������Ƃ��ǂ��l���邩�Ƃ����̂͂���̂ł����A3D�v�����e�B���O�̏o������藧�ĂĐV�����ł͂Ȃ��̂��낤�ȂƁB�����������ŁA���̒m���̖@�̌n�̒��ł̂����̐������Ƃ������o�����X�ŁA�{���o�����̂��̂ɒm��������Ƃ���A�ł��オ�����f�[�^�����̎Y�ƍ��Y���@��̂��̂ɓǂ߂�̂��ǂ����Ƃ��A���̂��̂��Ȃ��ꍇ�ł��A�n�쐫�̂���f�[�^�����������ɁA�v���O�����͒��앨������ǂ��A�قړ����̃f�[�^�����앨�łȂ��Ƃ��邱�Ƃ̃o�����X���ǂ��l���邩�B���Ƙ_�_�͍i���Ă��邩�ȂƂ����C�����܂��B������������Ď���ɂ�����x�c�_�������Ǝv���Ă��܂��B
AI�̂ق��́A���������Ӗ��ł͍��A�����ψ������炠�����悤�ɁA�����Ȃ̂ł�����ǂ��A�^�C���X�p�����ǂ��l���邩�Ƃ����̂����邾�낤�Ǝv���܂�����ǂ��A���s�̒��쌠�@���炷��Α������炩�ŁA�v�z�E����̕\���͐l�̕\��������AAI�����������̂͒��앨�ł͂Ȃ��Ƃ���Ӗ����m�Ȃ�ł��B���������Ӗ��ł́A�T��ψ������������悤�ɁA�����ł͂Ȃ����Ƃ����̂���̗L��l���Ǝv���܂�����ǂ��A���ӂǂ�ǂ��Ă������ɁA��̂����AI�̑n�앨�ł��ƒN�������ƌ���Ȃ��ł��傤����A�O���㒘�쌠��������̂��ǂ�ǂ��Ă����ꍇ�ɂǂ�����̂��B�����ʂ̂��Ƃ��l���Ă����Ȃ��ƁA�{������ׂ��łȂ����쌠�Ƃ��������������������Ă��܂��̂��ٔ��C���Ă������Ƃ����A�܂��ɏ��ψ���������������ʂ����ɓ]������̂͑��ӗ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂����ӎ��ł͂���̂ŁA�����͂�����x�������ċc�_�������Ǝv���Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA���̓A�����J�ł��̋c�_�������Ƃ���悩�����Ȃƍ����Ȃ��Ă���̂ł�����ǂ��A�ǂ����ł��Ɖ�����Ă���̂ƕ����ꂽ�̂ŁAAI������n�앨�̒��앨���Ƃ������m���̈������c�_���Ă����ƌ�������A�u�ւ��A�������낢�ˁv�Ƃ��������ė]�蔽�����Ă���Ȃ�������ł��B���ł��ȂƋA���Ă��炢�낢��l������A�P�́A�A�����J�̒��쌠�@�͓��{�̂悤�ɖ��m�Ɏv�z�E����̕\���݂����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA���̃A�����J�̒��쌠�@��A�܂��ɖ{������ψ��̃l�b�g�̂����ǂ�ł����̂ł����A�����A�����J�̃v���b�g�t�H�[�}�[��AI�n�앨�ɒ��쌠���咣����̂ł��傤����ǂ��A����͊��Ƃ݂̂₷���̂�������Ȃ��ƁB�����ŁA����Ńo�����X�����ꂽ��A�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�Ńt�F�A���[�X�̍l���������邵�Ƃ����A�����̃v���N�e�B�J���ȕ��@�Ȃ̂�������Ȃ��B���{�̒��쌠�@�́A���������Ӗ��ł͒��앨�̒�`���A���o�����X����Ƃ�����A����قǂ���Ӗ��_����Ȃ��Ƃ������A�������ǂ��l���邩�Ƃ����̂��Z�b�g���ȂƂ����C�����Ă��܂��B���������Ӗ��ł́A���̕ӂ��܂߂Ď���ɂ�����x���̓_�͋c�_�������Ă������������Ǝv���܂��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢�������Ǝv���܂��B
�������ψ��� �ł́A����ȍ~�̉�ɂ��Ď����ǂ��炨�肢���܂��B
������Q�����⍲ �����S�Ƃ������ƂŁA�X�P�W���[�������z�肵�Ă���܂��B����ɂ��Ă͂Q���W���Ƃ������ƂŁA�{���̋c�_�̑����ƁA������̃e�[�}�u�C���^�[�l�b�g��̒m���N�Q�ւ̑Ή��v���c�_���Ă��������Ǝv���܂��B
�ȏ�ł��B
�������ψ��� ����ł́A�{���̉�͕�����܂��B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B