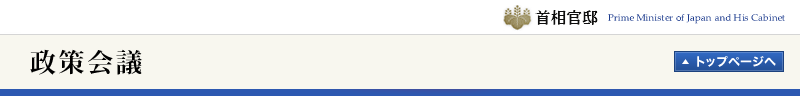�m�����������V�X�e�������ψ���i��3��j
�c �� �^
���@���F����27�N12��15��(��)10:00�`12:00
��@���F�����������ɂW���قU�K�@623��c��
�o�ȎҁF
- �y�ρ@���z
-
�ɓ��ψ����A�����ψ��A��R�ψ��A�����ψ��A���C�шψ��A���шψ��A
�L�c�ψ��A���J��ψ��A�ψ��A�ʏ��ψ��A�X�c�ψ��A�����ψ��A
�R�{�i�a�j�ψ��A�R�{�i�h�j�ψ��A����c�ψ� - �y�W�@�ցz
-
�@���ȁ@�@�@�@�@�@�@��؏��m�Q����
�������@�@�@�@�@�@�@�m�ȉ�O��撲����
�ō��ٔ����������ǁ@�i�c�K�j�s���Ǒ��ے�
- �y�W�c�́z
- ���{�m�I���Y����@�@�@�@�ʋ{�q���햱����
- �y�����ǁz
- �����ǒ��A���c�����A�c��Q�����A�k���Q����
- �J�@��
- �����̈��萫�ɂ���
- �e�@�ցA�c�̓�����̃v���[��
- �@��
���ɓ��ψ����@���͂悤�������܂��B
�@�������܂���u�m�����������V�X�e�������ψ���v�̑�R�����J�Â����������Ƒ����܂��B
�@�䑽�Z�̂Ƃ���A��Q�����������܂��āA���肪�Ƃ��������܂��B
�@���߂ɁA���������ǒ�����䈥�A�����肢�������܂��B
�������ǒ��@�m�������ǂ̉����ł������܂��B���͂悤�������܂��B
�@�����͂R��ڂɂȂ�܂����A�����͑O��̑����ŁA�����̈��萫���A�V���Ș_�_���܂߂Ĉ�ʂ�s������A�ɓ��ψ����Ƃ��䑊�k���������܂��āA���̓I�Ȍ����̘b����A���ꂩ��؋����W�葱�A���Q�����ƁA���葱�I�Șb�Ɉڂ��Ă����܂��̂ŁA���̐�ڂƂ������ƂŁA�v���[�����O�̒c�̂̕����܂߂Ă��肢�����āA�I�[�o�[�I�[���ɘb�����������āA�c�_�̑�ނɂ������Ǝv���Ă��܂��B
�@�O�獡���̊ԂɁA���́A�����A�Q�l�����ł��z������Ă���܂����ATPP�̍����Ή��ɂ��āA�Ƃ������ƂŁA�Q�l�����P�̒m�I���Y����ɂ�����TPP�ւ̐����Ή��Ƃ����̂��A�m�I���Y�헪�{���̊J�Â�11��24���Ɍ��肵�Ă���܂��B
�@�����ɐ��{�S�̂�TPP�̊֘A������j�����肳��Ă���܂��āA�m���p�[�g�͂��̂܂ܗv�_�����f���ꂽ�Ƃ������Ƃł������܂��B
�@���̒��ɂ́A���͓��ψ���̌����ɂ��ւ��܂������荞��ł������܂��āA�Ō�̃y�[�W�u�m�����������V�X�e���̑����I�Ȍ����v�Ƃ������ڂ��P���ڐ��荞�܂�Ă���܂��āATPP����̎��{�̂��߂ɕK�v�Ȓm�����x�̐����̏��܂��A��ē��̂Ƃ���A���W�ƒ��쌠�ɂ��Ă�TPP�̍��ӂɊ�Â��āA�@�葹�Q�������͒lj��I���Q����������Ƃ����̂����܂��Ă���܂��B����͑O�̕��ɐ��荞�܂�Ă���܂����A�����������Ƃ����܂��A�m�����������V�X�e���̈�w�̋@�\�����Ɍ����������I�Ȍ�����i�߂�Ƃ������Ƃ��A���߂Ė{������ŏ����Ă������܂��̂ŁA���̃~�b�V���������̈ψ���ɂ������܂��̂ŁA��낵�����肢�������Ǝv���܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂���
�@�O��܂ł̉���䌇�Ȃł�������Ⴂ�܂����A�ʏ��O�a�ψ��y�юR�{�h�O�ψ��́A�{���̉����̌�o�ȂɂȂ�܂��B
���ʏ��ψ��@�F����A���͂悤�������܂��B�{�c�Z���̕ʏ��ł������܂��B
�@�{�ψ���ł͑�ϊ��҂��Ă���Ƃ�����������܂����A�����ҊԂ̎����̖ʂłǂ̂悤�ɎQ�����Ă������Ƃ������������܂߂āA�ӌ����o���邩�ȂƎv���Ă���܂��B
�@�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
���R�{�i�h�j�ψ��@���s��w�̎R�{�h�O�Ɛ\���܂��B���͖��@�ł��B
�@�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�܂��A�n���r��ψ��ɂ��܂��ẮA�{���͏��v�̂��ߌ䌇�Ȃł������܂��B
�@���ꂩ��A�W�@�ւƂ������܂��āA�@���ȋy�ѓ��������тɍō��ٔ�������A�W�c�̂Ƃ������܂��āA���{�m�I���Y�����A�ʋ{�q���l�Ɍ�o�Ȃ��������Ă���܂��B
���ʋ{�Q�l�l�@���͂悤�������܂��B��Љ�������܂����A�m�I���Y����ŏ햱�����߂Ă���܂��A���Y�����Ԃ̕ʋ{�Ɛ\���܂��B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
���ɓ��ψ����@��낵�����肢�\���グ�܂��B
�@����ł́A�c��ɓ��肽���Ǝv���܂��B
�@�܂��A�O���c�_���������܂��������̈��萫�ɂ��܂��āA�����ǂɋc�_�����Ă��炢�܂����̂ŁA�����ǂ�����������肢�������܂��B
���k���Q�����@���茳�̎����P���䗗���������B�u�����̈��萫�Ɋւ��鐮���i�f�āj�v�Ə����Ă������܂��B
�@������́A�O��̌�c�_�܂��܂��āA�����ǂŐ����ł���Ƃ���͐��������Ă��������āA�܂��A�{������������c�_���������Ƃ���̓y���f�B���O�Ƃ������ƂŁA�b��I�Ȃ��̂Ƃ��č쐬�������̂ł������܂��B
�@�߂����Ă��������܂��ĂQ�y�[�W�u�i�Q�j���������i�K�ɂ��āv���������\���グ�܂��B
�@�u�@�������̗L������M�����҂̕ی�ɂ��āv�A������ɂ��Č�c�_���������܂����B��̓I�ȈĂƂ��܂��ẮA�R�y�[�W�̖`���ɂ���܂��悤�ɁA�������R�ɏ��ˊ��Ԃ�ݒ肷��Ƃ��A�������R�𐧌�����Ƃ����A�C�f�A�ł������܂�������ǂ��A��͂�Ď����S���傫���Ƃ��A�C�m�x�[�V�������i���ނ���j�Q����ł��낤�Ƃ������ƂŁA�K���ł͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�ꉞ�̐����������Ă��������Ă���܂��B
�@���́u�A�����R���y�і����̍R�ق݂̍���̌������ɂ��āv�ł�����ǂ��A�R�y�[�W�̉��̕��ɂ���܂����A�A�|�P�A�����̍R�ق����������ƂƂ��A�A�|�Q�A�N�Q�i�ׂɂ�����Z�p�I��含���X�ɍ��߂邽�߂̑[�u���u����A�����������Ƃ��낪�c�_�ƂȂ����Ƃ���ł������܂��B
�@���������ڂ������Ă����܂��B�S�y�[�W�ڂ̖`���u�A�|�P�@�����̍R�ق̌������ɂ��āv�ł������܂��B
�@�O��́A���̊ϓ_�ɂ��܂��āA�i���j����i���j�A�i���j�����̍R�ق̔p�~�A�i���j�����̍R�قŗ��p�ł��閳�����R�̐����A�i���j�u���炩�v���v�Ȃ����L��������K��̓����Ƃ������Ƃɂ��Č�c�_�����������܂����B
�@�O�҂Q�A�i���j�����̍R�ق̔p�~�Ɓi���j�������R�̐����ɂ��܂��ẮA�S�y�[�W�ڂ���T�y�[�W�ڂɋL�ڂ����Ă��������Ă���܂����A��͂蕴���̈��I�����Ƃ����ϓ_����A���[�U�[�j�[�Y�ɓK���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA�����̈Ă͓K���ł͂Ȃ��ƍl������Ƃ������ƂŁA�ꉞ�̐����������Ă��������Ă���܂��B
�@������́i���j�́u���炩�v���v���邢�͗L��������K��̓����ɂ��܂��ẮA�T�y�[�W�ɏ����������Ă��������Ă���܂��B
�@�u���炩�v���v�ƌ����܂��Ă��A���ꂼ��C���[�W����Ƃ��낪��Ⴄ�悤�ȋC���������܂����̂ŁA�����ǂŏ��������������܂��āA�ic1�j�N�Q�i�ׂƖ����R���ɂ��������قȂ邱�Ƃ�O��Ƃ���A�u��d��ƂȂ�w���炩�v���x�v�ƕX��Ă��Ă��������Ă��܂����A�����������l�����ƁA���R�A�L���������肳���̂ŁA�m�F�I�ɋK�肷��Ƃ����A�u�m�F�I�ȁw���炩�v���x�v�Ƃ������ƂŁA�Q�ɕX�㕪�������Ă��������Ă���܂��B
�@�{���́A�����ɂ��܂��āA�X�Ȃ��c�_������������Ǝv���Ă���܂����A�T�y�[�W�̒��قǁu�ic1�j��d��ƂȂ�w���炩�v���x�v�Ƃ������܂��B�O��̋c�_�ł́A�������������f����قȂ�Ƃ������Ƃ͗��_�I�ɂ͂��蓾��Ƃ�����ӌ����������ŁA�������ƍٔ����̔��f����قȂ�Ǝg���ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E�������������Ƃ���ł��B������ɂ��ẮA���_�͋L�ڂ����Ƀy���f�B���O�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B
�@���ƁA���̘_�_���l����ɂ�����܂��ẮA�����@��104���̂S�A�ĐR�̐����K��ɂ��Ă��l������K�v�����낤�Ƃ������ƂŁA�T�y�[�W����U�y�[�W�ɂ����ĊȒP�ɋL�ڂ������Ă��������Ă���܂��B
�@���Ƃ�����́u�ic2�j�m�F�I�ȁw���炩�v���x�v�A�U�y�[�W�̒��قǂɂȂ�܂����A������ɂ��Ă͑O��̌�c�_�ł́A�����̗L�����̐�������邱�ƂɈӖ�������Ƃ�����w�E���������ŁA�s�������ɂ���ĕt�^���ꂽ�������ɗL���������肳��邱�Ƃ͓��R�ł���̂ŁA�]��Ӗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����A�����̌�ӌ��������������Ƃ���ł��B������ɂ��Ă��y���f�B���O�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B
�@�U�y�[�W�̉��A�u�i���j�����̍čR�قɂ��āv�ł������܂��B������͑O���I�ɂ͋����Ă������܂���ł������A������������ӌ������������Ƃ����܂��āA����A�V���Ș_�_�Ƃ��Ē������Ă��������Ă���܂��B
�@������ł�����ǂ��A���݁A�N�Q�i�ׂɂ����āA�����̍čR�ق��s���Ƃ��ɂ́A�K�@�Ȓ����R�����͒����������������ɑ��čs���Ă��邱�Ƃ��v���ɂȂ��Ă���B����������ٔ��Ⴊ���������āA�����Ƃ��ẮA���̒����R�������s�킸�ɐN�Q�i�ׂŒ����̍čR�ق��s�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����^�p���Ȃ���Ă��܂��B������ɂ��āA�U���h��̃o�����X�̊ϓ_����A�����R�����𐿋����Ȃ��Ă��A�ٔ����Œ����̍čR�ق��ł���悤�ɂ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ�_�_�Ƃ��ċ����āA��c�_���������������ƍl���Ă���܂��B
�@���ƁA�Q�ڂ̑傫�ȉ�ł����A�V�y�[�W�̒��قǁu�A�|�Q�@�N�Q�i�ׂɂ�����Z�p�I��含���X�ɍ��߂邽�߂̑[�u�v�ł������܂��B����ɂ��Ă͑O��A�i���j�i���j�i���j�Ƃ������ƂŁA�i���j���ψ����邢�͒������̍X�Ȃ�[���Ƃ����l�����A�i���j�l���𗬂̊g��A�ӌ�������Ȃǂ����{����Ƃ����l�����A�i���j�������ɂ��L�����m�F�Ȃ�A���ӌ��Ȃ�Ƃ������r���[�@��̊g��Ƃ����葱��݂���Ƃ����l�������o����Ă��������Ǝv���܂��B������ɂ��ẮA�S�ʓI�Ƀy���f�B���O�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B�i���j�̋Z�p�I��含�̌���ł���Ƃ��A�i���j�̘A�g�����A������̂Q�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɖ^�p���x���̘b�ɂȂ��Ă������܂����A���̂W�y�[�W�̖`���ɂ���܂��i���j�̃��r���[�@��̊g��ɂ��ẮA�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�L���A�����̂Ƃ��낾�����劯���ł���������ɔ��f���Ă��炤�Ƃ����A�������x�I�ȗv�f�������Ă���Ƃ������A�C�f�A�ł��낤���Ǝv���Ă���܂��B
�@���̎��A�A�|�R�ł����A�����R�����x�̏_��Ƃ����b������܂����̂ŁA������ɂ��Ă��_�_�Ƃ��Ĉ������������Ă������܂��B
�@�u�i�R�j�����t�^�i�K�ɂ��āv�A������ɂ��Ă����낢���ӌ��������������Ƃ���ł����A�{���̃��C���̂Ƃ���Ƃ͂����Ă��������Ă���܂���B
�@�Ō�A�������̂Ƃ���̓y���f�B���O�Ƃ������ƂŁA�f�ĂƂ����`�Œ������Ă��������Ă���܂��B
�@�y���f�B���O�̂Ƃ���ɂ��܂��ẮA�{���̎傽��c��Ƃ������ƂŁA�����Q�̕��ɏ����Ă������܂��B�����Q���䗗���������B�u�����̈��萫�Ɋւ��čX�Ɍ������ׂ��_�_�����i�āj�v�ł������܂��B
�@�P���߂����Ă��������܂��B�X�Ɍ������ׂ��_�_�Ƃ������ƂŁA�ŏ��̕��̘_�_�ł������܂��u���炩�v���v�̓����ł���Ƃ��A���ꂪ��d����邢�͓��ꂵ���v���ł���Ƃ����l�����B���ƁA�����R���̐�������Ȃ������̍čR�قɂ��ĂƂ����_�ł������܂��B
�@�_�_�\�͂Q�y�[�W�ڂɏ����Ă������܂��B�܂��A��ԏ�́A��d��ƂȂ�u���炩�v���v�ł������܂����A������͊��҂������ʂƂ��ẮA�N�Q�i�ׂɂ����Č��������Ƃ���郊�X�N���y���ł���Ƃ�������ŁA���ӓ_�Ƃ��ẮA�����̈��I�����Ƃ������[�U�[�j�[�Y���ނݎ��Ȃ��ꍇ������Ƃ����Ƃ��납�Ǝv���܂��B
�@���̉��̇@�|�Q�A�m�F�I�ȁu���炩�v���v�ł�����ǂ��A����͓��������ɂ��邱�Ƃɂ��āA���T�d�Ȕ��f���s���邱�Ƃ����҂ł������ŁA����ł��L���������肳��Ă��邱�Ƃ���A�V���ȋK���݂��邱�Ƃ̎��������^��ł���Ƃ����Ƃ���͗��ӓ_�ł��낤���ƍl���Ă���܂��B
�@��ԉ��A�@�|�R�A�����̍čR�ق̖@�艻�ł�����ǂ��A������ł����A�N�Q�i�ׂɂ����āA�����̉ۂɂ��Ă����f�����@��g�傷��̂ŁA�����̈��I�����Ɏ�����Ƃ������Ƃł���܂��Ƃ��A���A�����R�������Ȃ��Ă������̍R�ق��ł���Ƃ������Ƃł��̂ŁA���l�ɁA���̒����R�������Ȃ��Ă������̍čR�ق��ł���Ƃ������Ƃł���A�葱�I�ɋύt����̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ƃ�����l�����܂��B�����A���ӓ_�Ƃ��܂��ẮA�E���ł����A�����̍čR�ق����p����邨���ꂪ����Ƃ������ƁB���邢�́A���Ɍ����҂������R���𐿋����Ȃ��Ȃ�ƁA�����҈ȊO�̑�O�҂ɂƂ��Ē����͈̔͂�������Â炭�Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ƃ��낪�������邩�Ǝv���Ă���܂��B
�@�����̍čR�قɂ��ẮA����������o�Ă������܂��B�T�y�[�W�ɂ�����܂Ƃ߂Ă���܂��B
�@�����̍čR�قɊւ���ٔ��ᓙ�T����܂�����ǂ��A��S�͂قړ������e�������Ă���܂��B��ԏ�̓����n�ق̔������ɐ\���グ�܂��ƁA�����̍čR�ق��F�߂���v���Ƃ��āA�����ɇ@����C�Ə����Ă������܂��B����A�_�_�ƂȂ�̂́u�@���Y�������ɂ��Ē����R�������Ȃ��������������������Ɓv�Ƃ����A���ɂ��������������Ȃ���Ă���Ƃ������Ƃ��A�i�ׂɂ����Ē����̍čR�ق��F�߂���v���Ƃ������ƂŁA�������������������o����Ă���Ƃ����ł������܂��B
�@�����A��ԉ��A�ō��ق̍ٔ����̌�ӌ��ł�����ǂ��A�����R���̐����́A�����̍čR�قɓ������ĕs�v�ł���Ƃ�����ӌ�������܂��āA�����������l����������Ƃ������Ƃ��A�Q�l�܂łɒ������Ă��������Ă���܂��B
�@�Q�ڂ̑傫�Ș_�_�ł������܂��̂��V�y�[�W�A�W�y�[�W�ڂɂ���N�Q�i�ׂɂ�����Z�p�I��含�̊֘A�̂Ƃ���ł��B
�@���̂W�y�[�W�̕\�ł����A������A�|�P�ƇA�|�Q�͑O�l�ł��̂ŁA�����͏ȗ��������܂��B
�@��ԉ��̇A�|�R�A�N�Q�i�ׂɂ����鋁�ӌ����邢�͗L�������m�F���邽�߂̎葱�ł�����ǂ��A���������ꍇ�ɂ́A���ɐi�������f���ɂ��āA��劯���ɂ�郌�r���[��������̂ŁA���[�U�[�̔[���������܂�ł��낤�ƁA���ɖ����R������������Ȃ��悤�ȏꍇ�ɂ́A���܂ł����������j�[�Y���~���グ��X�L�[�����Ȃ������Ƃ������ƂŁA�����������̃j�[�Y���ނގ葱�ɂȂ낤���Ǝv���܂��B�����ŗ��ӓ_�ł����A���̎葱�̂���悤�ɂ���ẮA�N�Q�i�ׂ̒x������������A���x�̍��ɂ���Ă͕��G������Ƃ��A��������������x�Ƃ̖������S�̐����Ƃ������̂����낤���Ǝv���܂��B
�@������A���x�̍��͂��낢�날�낤���Ǝv���܂�����ǂ��A�Ⴆ�ΗL�����̔��f�ɂ��āA�i�ׂ̏�Ř_�_�ƂȂ�����A�K���������ɍs���Ă��炤���A���邢�͓����҂��]�ꍇ�ɂ������邩�Ƃ��A�����������͂���܂����A�������̒��łǂ������葱�ōs�����Ƃ����Ƃ�����������܂��B���ƁA��劯���̕��Ŕ��f���ꂽ���ʂ��ٔ����ɂǂ������ӂ��ɎQ�Ƃ����̂��ƁA�����������Ƃ���̍����ł����Ȑv�����낤���ƍl���Ă���܂��B
�@���̈ӌ������߂�Ƃ������x�ł����A�O��A�Ƌ֖@�̒��ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ψ��̌�w�E���������܂����B�Q�l�܂ł�14�y�[�W�ɂ�����L�ڂ����Ă��������Ă���܂��B�Ƌ֖@�Ɋւ��鍷�~�����i�ׂɂ����āA�ٔ��������̑ΏۂƂȂ��Ă���s�ׂ��Ƌ֖@�Ɉᔽ���邩�ǂ����Ƃ������̂���������ψ���Ɉӌ������߂�Ƃ����̂����x�Ƃ��ċK�肳��Ă���Ƃ������Ƃ��A�Q�l�܂łɂ��`�������Ă��������܂��B
�@�Ō�A15�y�[�W�A16�y�[�W�ł�����ǂ��A��E�������ɂ��Ēi�K�I�����Ƃ��A�v���̊ɘa�Ƃ��_��Ƃ����Ƃ�����p��Ƃ��ďo�Ă������܂��̂ŁA16�y�[�W�̕��ɕ\�Ƃ��Ă܂Ƃ߂����Ă��������Ă���܂��B
�@�ȒP�ł͂���܂����A�����ǂ���͈ȏ�ł��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂���
�@�O��̋c�_�������ǂŐ��������āA�����Ă��ꂼ��̒�Ăɂ��āA���҂������ʂ◯�ӓ_�ɂ��Đ������Ă��炢�܂����B
�@�������܁A���������������Ă�������̂悤�ɁA���S�ɂȂ�܂��̂́i�Q�j�̕��������i�K�ɂ��܂��āA���ɖ����̍R�ق̊W�ȂǁA�{���̎����ł́i�o�j�A�y���f�B���O�Ƃ����\��������Ă��邠���肩�Ƒ����܂��̂ŁA���̂�����𒆐S�ɂ��Č�ӌ��Ղł���Ǝv���܂��B
�@�ǂȂ�����ł��䎩�R�Ɍ䔭�����������B
�@�����ψ��B
�������ψ��@��ɂ��̐����̑f�Ăɂ��āA����͍ŏI�i�K�Ŏ���C�����̋c�_���Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł�����ǂ��A�����͂��̂��Ƃɂ��ĉ����R�����g�����ł͂Ȃ��̂��ǂ�������������Ɗm�F�������̂ł��B�����A���ł��D���Ȃ��Ƃ������Ƃ������ƂȂ�A����w�E�����Ă������������Ǝv���̂ł����B
���ɓ��ψ����@��낵�����肢�������܂��B
�������ψ��@�P���ڂ̏o�����̂Ƃ���ɂ����Ȃ�u���啨��蓙�ɂ�茴�n�I�Ɍ������擾�v�Ə����Ă���܂��āA�����A���Ɉ�a�����������܂��B�L�̕��Ɩ��̕��Ƃ��ĂƂ����Ӗ��ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł�����ǂ��A����ɂ��Ă͉��l���ٌ�m���ɕ����Ă݂��̂ł����A��͂�݂�Ȉ�a��������ƁB������ƌ䌟��������������B
�@������_�A�R�y�[�W�̇A�́i�B�j�̃o�����X�̂Ƃ���ł����u�������҂͒��ړI�ɂ͔��_�݂̂��\�ł��낤���A�ԐړI�ɂ͖�������h�����߂̒����R���̐������\�ł���v�ƁA����͐������킯�ł�����ǂ��A������͐N�Q�i�ׂő啔���������R��������Ă��āA���������őΉ����Ă����Ƃ��������̍čR�ق������c�_�ɂȂ�Ƃ������Ԃ��������܂��̂ŁA�e�ɂ���Ƃ����_�ł́A�����R�������ł͂Ȃ��āA�����R���ɂ�������������������Ă����������Ƃ��䌟��������������B
�@�������e���V�y�[�W�Ƃ��W�y�[�W�̂Ƃ���ɂ��o�Ă܂���܂��̂ŁA������������͂̕������������܂��̂ŁA�䌟��������������Ƃ������Ƃł������܂��B
�@�Ƃ肠�����͌`���I�ɁB���݂܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�������܂̏����ψ�����̌�w�E�ɂ��ẮA�����ǂŌ���������Ƃ������Ƃł�낵���ł��ˁB
�@����ł́A�����������肢�������܂��B
�������ψ��@���g�̘b�������Ă��������܂��B
�@�����͘_�_���������낤���Ǝv���̂ł�����ǂ��A�������Ă��������Ă���܂��A�ŏ��Ɍ������ׂ��_�_�̇@�ł�����ǂ��A������@�|�P�Ƈ@�|�Q�Ƈ@�|�R�Ƃ������܂��B�@�|�P�ɂ��ẮA�ĐR������P�p����Ƃ������Ƃɂ�����ł���킯�ł������܂�����ǂ��A�V�������x���������Ă����v���Z�X�ŁA�����钩�ߕ���͋���邱�ƂȂ��Ƃ������Ƃł͂����Ǝv���̂ł�����ǂ��A��͂�ĐR���������̂悤�ɓ���Ă��������āA��ɉ���������̂��A��ŕԂ��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ԃ́A�����̈��萫�Ƃ����Ƃ���ō��{�I�ɖ�肾�Ƃ������ƂŁA�����@��104���̂S���ł����킯�ł������܂��̂ŁA�����������_���炵�Ă��A�@�|�P�Ƃ����ĐR�����̂Ƃ���́A������Ƃ������Ȃ��̂��ȂƂ����ӌ��������Ă���܂��B
�@�@�|�Q�����Ɍ������ׂ��ۑ�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B�u���炩�v���v�ɂ��ẮA�O��A�R�{�a�F�ψ������w�E���������܂����A���{�̗����x�����؋��̗D�z���čl�����Ă���̂ŁA�X�ɖ��炩�ƌ�������ǂ��Ȃ�̂Ƃ�����w�E���������܂����̂ł�����ǂ��A���̌�A������Ƃ��낢��l���Ă�����A�Ⴆ�s�������̎�������Ƃ����c�_���s���@�̐��E�ł������܂�����ǂ��A�䏳�m�̂Ƃ���A�ō��ق̏��a31�N�V��18�������ȍ~�Ȃ̂ł�����ǂ��A�ō��ٔ����́A�s�����������r���d�傩�����ł���A�����̎咣���ł���Ƃ������Ƃ��������܂��B���������āA���ؐӔC�̃��x���̖��ł͂Ȃ��āA�R�ٓI�Ȃ��̂ɂ��Ĉ��̃��x����v�����Ă����̂́A���@�I�ɂ����蓾��̂ł͂Ȃ����ƁB�͂Ȃ��̂ł�����ǂ��A�ō��قł͂��������̂͂����ʐ��E����ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�����������_�ł́A���ؐӔC�̃��x�����āA�u���炩�v���v�I�Ȃ��̂����邱�Ƃ́A���͗ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B
�@�č������@��282���ɗL�����̐���K�肪����̂ŁA�����t���Ƃ��ẮA�L�����̐���Ƃ������̂����Ă����ق����ǂ��̂��ȂƁB�L�����̐�������ċK�肵�Ă����ƁA�S�̂Ƃ��Đ����ł���悤�Ȋ������������Ă���܂��B
�@�����̍čR�ق̖@�艻�A�@�|�R�ɂ��ẮA������Ƃ��������ō��ق̕���20�N�S��24�������́A�T��������R�������āA�R���̒x�����������Ƃ�����������̂ŁA���ɂ��������Ƃ�����A���Ȃ莞�@�����Ƃ����������Ă������_���K�v�ł͂Ȃ����B
�@�Ƃ肠�����A����Ȋ��z�������Ă���܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�������܁A�����ψ�����́A������@�|�P�Ȃ����@�|�R�ɂ��܂��Ă��ꂼ��A�@�|�P�ɂ��Ă͏��ɓI�Ȍ�ӌ��A�@�|�Q�́u���炩�v���v�̊W�ł͗L�����̐���K����܂߂ĐϋɓI�Ɍ������ׂ����R������̂ł͂Ȃ����B�@�|�R�̒����̍čR�قɂ��܂��ẮA������������ׂ��ł͂��邯��ǂ��A���낢���肪�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E���������܂������A�����ψ�����䔭���������������Ɋ֘A���āA���̈ψ��̕��X�����ӌ������肢�����������Ƒ����܂��B�������ł��傤���B
�@�ǂ����A���шψ��B
�����шψ��@������Ɗm�F�������̂ł����A���̌�����@�|�Q�ł�����ǂ��A�����͕\�����܂��Ɓu�N�Q�i�ׂƖ����R���ɂ����ē��ꂵ���w���炩�v���x���m�F�I�ȋK��Ƃ��ē�������v�Ƃ������܂��B
�@�������܂̏����ψ��̌䔭���́A�N�Q�i�ׂɂ����Č����̗L��������K�肪����悤�ȏŁA�u���炩�v���v�����āA�����̖����𐧌��I�ɉ��߂���Ƃ������b�͗����ł��܂������A�܂��A�A�����J�ł����̂悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ͑O��̂��b�ł����B
�@�������A�����R���ɂ����ẮA�A�����J�ɂ����Ă��܂�������ݒ肵���@�ւ�������������Ƃ������Ƃł�����Apreponderance of evidence�Ƃ������Ƃł����āA�ʏ�̔��f��Ō������Ă���킯�ł��B
�@���̎����ǂ̒�Ă̎�|�́A�����R���ɂ����Ă����炩�łȂ���Ζ����ɂł��Ȃ��Ƃ����悤�Ɏd�������Ă���̂����A������Ɗm�F�������Ǝv���܂��B
���ɓ��ψ����@���肢���܂��B
���k���Q�����@���̌䎿��ł�����ǂ��A���ꂵ���v���Ƃ������Ƃ�˂��l�߂Ă����ƁA�i�ׂ݂̂Ȃ炸�A�R���ɂ����Ă����������v�����ۂ��Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA�ꉞ�̒�ĂƂ��ď������Ă��������Ă���܂��B
�@�����A����ɂ��āA�R���ɂ��Ă͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����Ƃ�����ӌ��Ƃ������Ƃł���A�����������Ƃ�����܂߂Ă��낢����Ă���������ƍl���Ă��܂��B
���ɓ��ψ����@��낵���ł��傤���B
�@���������l���������蓾��Ƃ������Ƃ�O��ɂ��āA��c�_����������Ƒ����܂��B
�@�������ł��傤���B
�@�ǂ����A��R�ψ��B
����R�ψ��@����������@�|�Q���Ó��ł���ƍl���Ă���܂��B
�@�����LjĂ̂悤�ɁA����͐V�����l�������Ƃ͎v���܂�����ǂ��A�����R���ƃ��x�������킹�邱�Ƃ́A��������ɏd�v�ȃ|�C���g���ƍl���Ă���܂��B�u���炩�v���v�����Ă��A���ɍō����x���̏ؖ����v������Ă��邩��A�Ӗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�ɂ��ẮA�O����\���グ�Ă���悤�ɁA���ۏ�̌��ʂ�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��āA���̋�̗�Ƃ��āA�T�y�[�W�̂R�Ԗڂ̒m�����ق̕���26�N�X��17�������A����͒����̍čR�ق��F�߂��邽�߂ɂ́A���ۂɒ����R���������Ȃ���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ������Ƃ��������̂ł�����ǂ��A���̗��R�t���Ƃ��āA�����̂Q�i���ڂ̂Q�s�ځA�������R�̉ۂ��m���ɗ\������邽�߂ɂ͒����R�����������Ă���K�v������Ƃ���Ă��܂��B�čR�ق��ؖ��̈�ɒB���Ă���ƌ����邽�߂ɂ͂����������n�[�h�����ۂ����ƂɂȂ�̂͏\���ɔ[���ł���̂ł����A�����ɖ����ł���ꍇ�Ɍ����Ė������f���ł���Ƃ������Ƃɂ���A�����R�����������Ă��Ȃ��Ă������ƂȂ�Ȃ��Ɣ��f������]�n�������܂��B�ł��̂ŁA�����ɂƂ����v�������邱�Ƃ��S���Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA��͂������A�Ӗ����o�Ă��镔�������X����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@�ȏ�ł��B
���ɓ��ψ����@�������̗v�����������邱�ƂɁA���ۏ�̈Ӗ�������Ƃ�����ӌ������������q�ׂ��Ă���܂�����ǂ��A�������ł��傤���B
�@����c�ψ��A�ǂ����B
������c�ψ��@���͌�����̒��ł͇@�|�Q���������Ă����ׂ����ȂƎv���Ă���̂ł����A���́u���炩�v���v�̂Ƃ���Ȃ̂ł����A�܂��A�����ŐR���������āA���̌�A�R���Ƃ������ƂŁA�R���̏ꍇ�͐R����������l�ŁA���̌�A�R�����Ƃ����Ƃ���ŁA�����̐R���̂Ƃ���ł��u���炩�v���v���K�v�Ƃ����̂́A��ǂ����ȂƂ����C���������܂��B�R�擙�ɂȂ�܂��ƁA�܂��s������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����Ȃ̂��ȂƎv���Ă��܂��āA���A�����ǂ̕��ŁA�R������Ƃ������b�������̂ł�����ǂ��A�����̂Ƃ���͂ǂ��Ȃ̂��ȂƂ����Ƃ��낪��������܂��B
�@���ꂩ��A��قǂ̏�R�ψ��̖����ɂ�����ƁA���ۏ�A���Ȃ�ς���Ă���Ƃ������b�Ȃ̂ł����A�O���������Ɛ\���グ�܂����悤�ɁA�ٔ����̐S�ۓI�ɂ͂��Ȃ����Ă���̂��ȂƎv���̂ł����A�����ɂƂ����ꍇ�ɁA�����̍R�قł悭�F�߂��Ă���̂��A�Ⴆ�ΐV�����؋����o�Ă����ꍇ�͔F�߂₷�����ȂƂ����C�����Ă���̂ł����A����ȊO�ɁA�Ⴆ�Ζ����ɂƂ����̂́A�ǂ��������Ƃ����l���ɂȂ��Ă���̂��A������Ƌ����Ă���������Ǝv���̂ł����B
���ɓ��ψ����@�������܂̑���c�ψ��̌䎿��́A��R�ψ��⏬���ψ�������ɉ��������A�z�肳���悤�Ȃ��̂�����Ƃ������ƂŁA�������l���͂������܂����B
�@�ł́A�L�c�ψ����炨�肢���܂��傤
���L�c�ψ��@�z�肳��邩�ǂ����A������ƕ�����܂���ǂ��A�������ŋߎ������ŁA���������Ă��܂��̂ŁA�����]�肱���Ŏ���ɂ���̂͗ǂ��͂Ȃ��Ǝv���̂ł�����ǂ��A�O����������b�������Ă����������̂ł�����ǂ��A�R���Ƃ��A�R������i�ׂƂŁA�ꉞ�ō��ق܂ōs���āA�ꉞ�L���͊m�F���ꂽ�B������Ɩ{���ɐG��܂�����ǂ��A�R���̕��́A�܂��悪�������܂��̂ŁA�����ɂ킴�킴���炩�v����t���Ȃ��Ă��A���낢���X���R�قł��邵�A�퍐�������낢��R������i�ׂɍs���A���낢��b�͂ł���Ƃ������ƂŁA����͂Ȃ��̂ł�����ǂ��A�ٔ��̕��ɍs���ƁA�����]��Ȃ��킯�ł��B�n�ق����ق��B�����m�����قŏI���ŁA�ō��ق͍s�����Ƃ��Ă��Ȃ��Ȃ�����B����A����������́A�ꉞ�L�������ō��ق܂Ŋm�F����āA�n�قł��ꉞ�L�����͊m�F����܂����B���قɍs�����Ƃ��ɁA�퍐���͈ꉞ�������������͂���܂���Ƃ������Ƃ͌����Ă���̂ł�����ǂ��A���̎������ǂ��g�ݍ��킹�āA����͖������Ƃ܂������Ă��Ȃ��̂ł���B������ٔ������킴�킴�䒚�J�ɁA�`�a�b�c�d��g�ݍ��킹�āA��������Ƃ����V���Ȕ��f��������āA�ŏI�I�ɂ͓��������ɂȂ����̂ł��B
�@�����������Ƃ��A��ɂł͂Ȃ��Ǝv���܂�����ǂ��A��͂�N���蓾��\��������Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB������A���̂Ƃ��ɁA��X�Ƃ��ẮA����f����̂�������A���������_���I�ȃo�b�N�O���E���h���Ȃ��ƑʖڂȂ̂ł��B�����͔�щz���Ă���킯�ł���B�`�C�R�[���a�A�a�C�R�[���b�A�b�C�R�[���c�A�c�C�R�[���d�A������A�`�Ƃd�Ƃ͈ꏏ�ł���Ƃ����_���\���Ɍ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B
�@����͓����ґ��̘b�Ȃ̂ŁA�퍐�����炵����Ⴄ�Ƃ��A������ꉞ�������̂ŁA�Z�J���h�I�s�j�I�����Ƃ��āA�ǂ��ł����ƌ�������A�����ӌ��ł��Ƃ������Ƃł������̂ŁA������Ƙb�͂��Ă���̂ł�����ǂ��A�����������Ƃ���ɂ͂Ȃ��Ǝv���܂����A�ٔ������^���ɂ��낢�딻�f�����Ă��������Ă���Ǝv���̂ł�����ǂ��A��͂�\���Ƃ��Ă͋N���蓾�邩���킩��Ȃ��B���̎��Ɉ��̃n�[�h��������Ƃ������Ƃ́A�Ӗ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA���炩�Ƃ��A�����Ƃ����̂�t���Ă��������Ƃ����̂́A��A��Ƒ��Ƃ��Ă͌����̈��萫�Ƃ����Ӗ��ł́A�Ӗ�������̂ł͂Ȃ����ƁA���̂悤�Ɏv���Ă���Ƃ���ł������܂��B���Ȃ��Ƃ����͂����v���Ă��܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�������ł��傤���B
�@�X�c�ψ����肢���܂��B
���X�c�ψ��@���͐���ƊE�ɂ���܂��̂ŁA���������ϓ_�����\���グ�܂��B�O��A�x��ł��܂��܂����̂ŁA�ꌾ�����\���グ�܂��B
�@���~�������Ɋւ��ẮA����ƁA��͂�ł��d�v�Ȍ����Ǝv���Ă���܂��̂ŁA���̓_�Ɋւ��ẮA����A��������K�v���Ȃ��Ƃ����A���̐����Ƃ������Ƃ����ꂽ�Ǝv���̂ł�����ǂ��A���̓_�Ɋւ��ẮA�A�O���[�ł������܂��B
�@�����̘_�_�ł������܂�����ǂ��A�u���炩�v���v�Ɋւ��܂��ẮA��قǖL�c�ψ���������������悤�ɁA�������҂Ƃ��Ă͑������肪�����v�����ȂƊ����Ă���܂��B����ŁA�u���炩�v���v�Ƃ������̂������Ă���ƁA�������炩�Ȃ̂��Ƃ�����������A�䎿�₪�C�V���[�Ƃ��ē��R�オ���Ă���̂ŁA��������ē��ȂƂ����̂͂�����Ƌ^�₪����Ƃ���ł������܂��B
�@���{�̍ٔ����́A�i�ׂ�����Ă��Ă��A���{�̔�������͔��ɗD�G���Ǝv���܂��̂ŁA�䎩�g�Ŗ�����ǂ�ŁA�S�،`�������̂��Ǝv���̂ł��B���̎��_�œ����̗L�����Ƃ����̂�������x���f����Ă���̂��Ǝv���܂��̂ŁA�]��]�v�ȃC�V���[���������ނ��A����ł��\�����f����Ă���̂��A�Ó��Ȕ͈͂Ŕ��f����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���܂��B
�@������A�����̘_�_�̇@�|�R�̒����̍čR�قɊւ��Ăł�����ǂ��A���̓_�Ɋւ��Ă��A���ꎩ�̂�ے肷����̂ł͂������܂���ǂ��A���̒����R���Ɋւ��āA��~���������Ƃ������A�����҂Ƃ��Ď�g���Â炢�`�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂������܂��B���̂��߂ɁA�������҂Ƃ��Ă��A��͂莖�O�ɒ������Ă������Ƃ���������̃��`�x�[�V�������������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���܂��B
�@����́A���������Ƃ����̂��A���������͈̔͂��A�������Ƃ��Ă̈ʒu�t���������Ă���Ƃ����̂͗������Ă���Ƃ���Ȃ̂ł�����ǂ��A�]��ɂ��A�]���̃v���N�e�B�X�͂悭�������Ă���̂ł�����ǂ��A�����I�Ɋg�����͕ύX�Ƃ���������̔��f���A���Ƀn�[�h���������Ȃ��Ă���悤�Ȋ��������܂��B
�@�����S�̂̋L�ڂ��l�����āA����������Ƃǂ����������肪�����Ƃ��ĔF�߂��Ă�����ׂ����̂��A�ۂ��Ƃ����̂f���Ă���������A�����̍čR�ق��A����������Ɖ^�p�̗Z�ʂ��Ƃ������A���̂�������������Ă�����������Ηǂ��̂��ȂƂ������������Ă���܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�X�c�ψ�����́A�����̍čR�قɂ��ẮA�����R�����̂��̂̍����I�^�p�̖��̕����ނ���d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�u���炩�v���v�Ɋւ��ẮA����ɏƂ炵�Ă��A�ʂ����Ď��ۏ�A���������v�����������邱�ƂɈӖ�������̂��낤�Ƃ��������Ƃ�����܂������A����ȊO�̓_�ł����\�ł������܂����A�������ł��傤���B
�@��قǂ̊W�ł��ˁB�킩��܂����B�ł́A��R�ψ��ɐ�ɂ��肢���܂��B
����R�ψ��@�����A�䎿��͎��ɑ��Ă��Ǝv���܂��̂ŁB
�@�O���ɂ���̂́A�i�������f�̕����Ȃ̂ł��B�V�K���ł��Ƃ��A�L�ڗv���s���Ɋւ��ẮA���������邩�Ȃ����A�������F�߂��邩�ۂ��ł��̂ŁA�����͖������v�������낤�ƂȂ��낤�ƁA���f���ς�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂��B����ŁA�i�����ɂ��Ă͑g�ݍ��킹���e�Ղƌ����邩�ǂ����Ƃ����A�{���I�Ɏ�ϓI�ȕ]���̖��ł����A���x�̖��ł���Ƃ����_�ŁA�����̗L���Ƃ͐������قɂ��Ă���ƌ�����Ǝv���܂��B
�@���̈�ۂɔ��Ɏc���Ă���̂��A��m�b�r���̔������o�鏭���O�ɁA����ٔ������u���ŁA�ȑO�̓j���[�g�����ȃX�^���X�Ői�����̔��f�����Ă����B�����A���͌����̈��萫���d�v���Ƃ������F���������Ă���̂ŁA�����Ƃ��Ȃ����R�t�����ł���̂ł���A�ɗ͂������������Ŕ��f����悤�ɂ��Ă���Ƃ����䔭���ł��B����ɏے�����Ă���悤�ɁA�i�������f�Ƃ����̂́A�ؖ���v������Ƃ͂����Ă��A��ϓI���l���x�̖��ł���Ƃ������ƂŁA�����I�ɂ͖������Ƃ����v�����ۂ���邱�ƂŁA���Ȃ���ʂɈႢ���o�Ă��镔��������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@���C�шψ��A���肢���܂��B
�����C�шψ��@���A��R�ψ�����������������Ƃ��܂߂āA������̇@�|�Q�ɂ��܂��āA���낢�남�b�����������Ă���܂����A�L�c�ψ��������������w�E���������܂�������ǂ��A�ٔ����̃}�C���h�������b�������Ă����������Ǝv���Ă���܂��B
�@�u���炩�v���v�����邩����Ȃ����Ƃ������Ƃɂ��āA���ɔ�����Ƃ��A�����������Ƃł͂������܂��A�O��ɂ����b���o�܂����悤�ɁA�N�Q�i�ׂɂ����Ė����̍R�ق��o���Ƃ��̍ٔ����Ƃ������܂��ẮA�u���炩�v���v�������Ă��邩�A�����Ă��Ȃ����ɂ�����炸�A���Ȃ�T�d�ɐR�����Ă������ł���Ƃ������Ƃ͌䗝������������Ǝv���Ă��܂��B
�@�O������b���o�܂�������ǂ��A�ǂ������ꍇ�ɖ����̍R�ق�F�߂邩�Ƃ����_�ɂ��܂��ẮA�ʏ�l���^����������܂Ȃ����x�̍��x�̊W�R���A�������͂悭�m�M�Ɏ���Ƃ������t���g�����Ƃ��������܂�����ǂ��A�ؖ��ӔC�̊W���������܂��̂ŁA��͂肩�Ȃ肻���̂Ƃ���ɂ��ẮA���Ƃ��ƍٔ����̃}�C���h�Ƃ��ăn�[�h���̍������̂��Ǝv���Ă���Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B
�@������́A�����̍R�قł�����A���R�A���������ɂ����āA�퍐���i�A�퍐���@�������̋Z�p�I�͈͂ɑ����Ă��邩�ǂ����Ƃ������f�������Ă��Ă��܂��B�������A�Z�p�I�͈͂ɑ����Ȃ��Ƃ����悤�ȐS�������Ă���Ƃ��ɁA�Ȃ��������ɂ��邩�Ƃ��������������܂�����ǂ��A�����������ɐT�d�ɂȂ�̂́A��͂�Z�p�I�͈͂ɂ͓����Ă���Ƃ������f�ɂȂ����Ƃ��ɁA�ʂ����Ă���͖����ɂ��Ă悢�̂��Ƃ������Ƃ́A��͂�d�v�Ȗ��ł������܂��̂ŁA���炩�v���������Ă��邩�A�����Ă��Ȃ����ɂ�����炸�A�����͐T�d�ɔ��f���Ă���Ƃ����̂��ٔ����̃}�C���h�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�����ψ��A���肢���܂��B
�������ψ��@�ٗ��m�Ƃ��Ĉꌾ�\���グ�����Ǝv���܂��B
�@��قǁA�����R���̗v�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��o�܂�������ǂ��A�^���ł������܂��B
�@���A�����͈̔͂����ȂƂ������������ɋ����āA�Ⴆ�Ή��ł��悢�̂ł�����ǂ��A��̍H����������A���炩�ȓ��������o��B���x�̗v����������A�������͏o��Ƃ����ꍇ�ł��A���k�ɓ�����Ȃ��A�ύX�ɓ�����Ƃ������ƂŁA�F�߂Ă��������Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂��B�ł�����A�N�Q�i�ׂɐ悾���āA�����̈��萫�����߂đi�ׂ���Ƃ��A�������������Ƃ�����Ƃ��ɁA��ϕs���R�������Ă���Ƃ���ł��B
�@�������A�V���ȃT�[�`�������Ȃ�������Ȃ��Ƃ��A�����ȗv�f�����������ɂ�����̂͗������܂�����ǂ��A���̕ӂ̂��Ƃ����������_��ȉ^�p�����Ă���������ƁA���Ȃ�g���₷���Ȃ�Ƃ������Ƃ��v���Ă���܂��B
�@�ȏ�ł������܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�u���炩�v���v�ɑ��܂��ẮA�����̗��ꂩ��̌�ӌ����������܂������A�w���I�ȕ��ʂ���R�{�a�F�ψ���R�{�h�O�ψ��A�䔭���������܂�����A���肢�������܂��B
�@�܂��A�R�{�a�F�ψ����炨�肢�������܂��B
���R�{�i�a�j�ψ��@�w���I�ƌ����邩�ǂ������M�͂���܂��A�܂��A�����P���Ɓic1�j�ŁA�����Q���Ƈ@�|�P�ł����B���̓_�ɂ��܂��āA�O��A��������b���������Ƃ���������Ă��邱�ƂƂ̊W�ŁA�ĐR�Ƃ̊W�ɂ��܂��ẮA���̑O��̔����A�܂�A�����@��104���̂S�Ƃ����̂́A�����i�ז@��338���Ɛ����I�ł͂Ȃ��Ɛ\���グ���̂́A��{�I�ɂ͂��̂Q�̎葱�ɁA�N�Q�i�ׂƖ����R���Ƒi�ׂƂ̊������ł��邱�Ƃ�O��ɂ��āA�N�Q�i�ׂŊ��Ɉ��U���h��������̂ŁA�ĐR�͔F�߂�K�v�͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA��������Ɛ\���グ���̂ŁA���̇@�|�P�̍l�����̂悤�ɁA�_�u���X�^���_�[�h���Ƃ�̂ł���A����͓��R�ĐR�͕K�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���Ă��܂��B���������Ӗ��ł́A�@�|�P�̐����A���̔��f����قɂ����ꍇ�ɂ͍ĐR�������������Ƃ���Ă��邱�Ƃ́A���͂������낤�Ǝv���܂��B
�@�@�|�P�̍l�������̂ɂ��ẮA����͉��l���̕��̌�w�E������܂��āA�����O��A��̌��O��\���グ�܂����B
�@���̕��S�̂̐������Ƃ����ϓ_���炵�Ă��A�Q�̎葱�̊��ς���Ƃ����Ӗ��ł́A�@�|�P�̍l�����Ƃ����̂́A�����P�̕��ɏo�Ă���a�̍l�����A�܂�A�����̍R�قŗ��p�ł��閳�����R�𐧌�����Ƃ����l�����Ɠ����̂��̂��Ɨ��������Ă��܂��B
�@�����A���݂̐����ł́A�i���j�ɂ��Ă͓K���łȂ��Ƃ�������������Ă��邱�Ƃ��炷��A�����猩���Ƃ���A�����悤�ȗ��R�����́ic1�j�̍l�����ɂ��Ó�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���ꂩ��A�ic2�j�A�����Q�ł͌�����@�|�Q�Ƃ������ꂵ���u���炩�v���v�Ƃ����_�ɂ��܂��ẮA����͐�قǏ����ψ�����A�ؖ��x�̖��Ƃ͍l�����ɐ����ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E������܂����B�����ł���A�����g�A�����i�ׂ̖��łȂ��Ƃ���A�R�����g�͓��ɂȂ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�̂ł����A�s���i�ׂ̈�ʘ_����A�v���[�`����Ƃ����l�������Ƃ�Ƃ���A�s���i�ח��_�Ƃ̐������͍l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�Ǝv���܂��B
�@�����ψ��́A�s�������̖����i�ׂɂ��Ă̏d�喾���̔�����������܂����B������������Ƃ���ł́A����͗v����ɁA�s����������i�ׂɂ������i�̊��Ԑ����ł���Ƃ��A���邢�́A����i�ׂ̔r���I�NJ��A���Ă͌���͂ƌ����Ă������̂��A���̕������N���A���邽�߂ɁA�����i�ׂƂ����T�O������A�����Ŏ���i�ׂƂ͈قȂ�d�喾�����Ƃ����v�������ɕt������Ă�����̂Ɨ������Ă���܂��B
�@���������Ӗ��ŁA���̋ǖʂ�����Ɠ����Ɛ����ł���̂��ǂ����Ƃ����̂́A�T�d�Ȍ������K�v���Ǝv���܂����A�s�������A���邢�͂���ɑ������̒i�K�ŁA�s�����̑��ŐT�d�ȐR���葱������Ă���̂ŁA�ٔ����̐R���͈͂𐧌�����Ƃ����l�����́A������̍s�������̏ꍇ�ɂ�����܂��B����������I�؋��@���ƌ�������̂��F�߂���s�������A��������ψ���̐R���Ƃ��A���������ނ̂��̂ɑ���ٔ����̐R���͈͂𐧌�����A�����������x�͑��ɂ���Ǝv���܂��B
�@�����������̂ƁA����A���ɂ��́u���炩�v���v����ꂽ�ꍇ�ɁA���炩���Ƃ����̂���̉���\���Ă���̂��Ƃ������Ƃ́A�s���i�ׂ̈�ʘ_�̒��ŐT�d�Ɍ�������邱�Ƃ��낤�Ǝv���܂��B
�@�����A�����g�͍s���@�̐��Ƃł͂���܂���̂ŁA����ȏ�̃R�����g�͂ł��Ȃ��̂ł�����ǂ��A���̓_�̌����͕s���ɂȂ邾�낤�Ƃ������Ƃ����\���グ�����Ǝv���܂��B
�@������͈ȏ�ł��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�������܂̎R�{�a�F�ψ��̌䔭���ɂ�����܂������A�u���炩�v���v�́A�ٔ����̖����ɂ��Ă̐S�̓x�����ɊW����Ɠ����ɁA�ʂ̌���������ƁA�����ɂ��Ă̎��̖@��̗v���Ɛ\���܂����A������l�������Ƃ�����������܂����A�R�{�h�O�ψ��A�������܂̂�����ɂ��āA�䔭���������܂�����A���肢�ł��܂��ł��傤���B
���R�{�i�h�j�ψ��@�O��A���Ȃ��Ă��܂��āA�c�_���Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ������̂ł����A�����A�u���炩�v�Ƃ������Ƃɂ���ĉ�������Ă���̂��Ƃ������Ƃ��m�F�������ƍl���Ă��܂����B
�@�ؖ��x�̖��ł͂Ȃ��A���̋K��Ƃ��āu���炩�v������ƁA���̓I�Ȋ���ς���Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂����B���̈Ӗ��ł́A���A�R�{�a�F�ψ����������Ⴂ�܂����悤�ɁA�����̔��f��A�����̗��R�����͈̔͂Ɍ��肷�邱�ƂɂȂ���̂��ȂƎv���Ă��܂������A�����A�ǂ������̏�ł́A���̂悤�ȍl�����͍̗p���Ȃ����Ƃ��O��ɂȂ��Ă���Ƃ��܂��ƁA�u���炩�v�ɂ���Ĉ�̉�������Ă���̂��Ƃ������Ƃ����������m�F������ŁA���f���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv��������ł��B
�@�قړ�����|�ł����A�ȏ�̂Ƃ���ł��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�������܂̓_���܂߂܂��āA���Ɍ䔭���������܂��ł��傤���B
�@�����ψ��A���肢�������܂�
�������ψ��@���͍s�������̖����̗�����������Ă����������̂́A����������������Ƃ����b�����ł��āA���_�I�ȓ���b�͊w�҂̐搶�ɂ��C���������Ǝv���܂��B
�@�����A���̈ψ���������Ȃ̂ł�����ǂ��A�v����ɁA�v���p�e���g�����ɂ����Ǝ������X�����Ȃ����A���������ڂł����ȉ����������܂߂Č������悤�Ƃ������Ƃł��̂ŁA���鐧�x���Ƃ����Ƃ��ɁA�����ɐ��l�I�Ɏ��������o�Ă���Ƃ������_�����ł͂Ȃ��āA��X�����̐��E�ł悭�����Ă���̂ł����A�P���Ɍ��C�ɂȂ�A���������������厖�ł͂Ȃ����B������A�u���炩�v���v����k�Łu���邢�v���v�ɂ��悤�Ƃ����A��͂薾�炩�Ƃ����͓̂��邾���ŁA�i�ׂ̏�ʂ����ł͂Ȃ��āA���������͓��{�ł͓��ɑi�O�ł�������������s���Ă���Ƃ������Ƃ��������܂��B���������Ƃ��ɁA�㖾�炩���邢�͐���Ƃ����̂������Ă���ƁA�Ȃ��Ȃ��������������Ȃ��ł͂Ȃ��ł����Ƃ������ƂŁA�����Ȍ����̈��萫�����ۂɍl������āA���������Ɍ������Ă����Ƃ������Ƃ͂���Ǝv���܂��B
�@�]������������邩�Ȃ����̋c�_�𑱂��Ă��܂��ƁA�����Ă��}�C�i�X�C���[�W�Ɋׂ��Ă��܂��B���������傫�Ȏ��_�ł܂����l�������������炠�肪�����Ƃ������ƂŁA�⑫�����Ă������������Ǝv���܂��B
���ɓ��ψ����@�ǂ����A���шψ��B
�����шψ��@��قǏ�R�ψ�����A�i�����̔��f�͐����I�Ȕ��f�ł��邩��A���ꂪ���炩�łȂ�����A�����ɂ��Ȃ��Ƃ��ׂ��ł���Ƃ����b���o�܂������A����́A�݂͖݉��Ō����Ȃ�A�����I�Ȕ��f���\�ȓ��������i�����̔��f�����ׂ��ł���Ƃ�����ӌ��̂悤�Ɏ��͎f���܂����B
�@��قǁA�R�{�ψ���������b������܂������A�s�������̖����Ƃ����̂ƁA����i�ׂƂ͈Ⴄ�̂ł����āA�����̖����R���Ƃ������̂́A���������ݒ肵�����������I�Ɍ������Ƃ������Ƃł�����A�����ɍs�������̖����̏ꍇ�Ɠ��l�Ɂu���炩�v���v������Ƃ����ӌ��ɑ��ẮA���͂ƂĂ���a��������܂��B
�@�ł�����A�قȂ锻�f��ł͂Ȃ��A�m�F�I�ȈӖ��ł́u���炩�v���v�Ƃ��ׂ��ł���Ƃ�����ӌ��ƁA�i�����ɂ��Ắu���炩�v���v�Ƃ�����������x�������f��ŐR�����ׂ����Ƃ�����ӌ��́A�������ɂ����锻�f���T�d�ɂ��Ƃ������|�������̂��A������Ƃ��������f���������Ǝv���܂��B
���ɓ��ψ����@�ǂ����A��R�ψ��A���肢���܂��B
����R�ψ��@�������ɂ����Ă��T�d�ɂƂ����l�����ł���܂��B
���ɓ��ψ����@�������ł��傤���B
�@�ǂ����A�ʏ��ψ��B
���ʏ��ψ��@���炩�Ƃ����悤�Ȃ��ƁA���邢�͗L�����̐���Ƃ����̂��A���t�������āA��قnj�ӌ����������悤�ɁA���C�ɂȂ�Ƃ����̂́A����͂��邩�ȂƎv���̂ł����A�����܂ł������ґ��̘b�ł����āA�����ŗ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂́ANPE���̂�����p�e���g�g���[���̂悤�Ȃ��̂ɑ��āA�{���ƌ����܂����A��X�A�i������A��悳��鑤���炷��A�{�������ƂȂ�悤�Ȃ��̂ɂ��Ă��������肪�������Ƃɂ���āA�����ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ԃ��A��������̂��Ƃ���A���̂悤�Ȍ��C�͂���Ȃ��ȂƎv���܂��B
�@�T�d�ɂƏo�Ă���܂����A���A�\���������ł����f������Ă���Ƃ������ƁB��X�������O��ɁA�����҉������Ă��܂��̂ŁA����ȏ�K�v�Ȃ̂��ȂƂ������O�͂������܂��B
���ɓ��ψ����@������܂����B
�@�u���炩�v���v�Ɋւ��܂��ẮA�_�_������������܂��āA����I�Ȃ��̂��A����Ƃ��A�N�Q�i�ׂɌ��肵�����̂��Ƃ����_�A���邢�́A�ؖ��x�̘b�Ȃ̂��A���̏�̖����̎咣���̂��̂Ɋւ���c�_�Ȃ̂��A����ɑi�ׁA�ٔ��̐��E��������Δg�y���ʓI�Ȃ��̂��ǂ��]�����邩�A���ꂼ��Ɍ�ӌ���������Ă���܂��āA�Ȃ��Ȃ�������܂Ƃ߂�͓̂���Ǝv���܂����A���Ԃ̊W���������܂��̂ŁA��قǂ̒����̍čR�ق⋁�ӌ����x�ɂ��܂��Ă��A��ӌ������肽���Ƒ����܂��B
�@�ǂ����A���C�шψ��B
�����C�шψ��@�����R����������Ȃ������̍čR�قɂ��܂��āA�������^�p���Ă��闧�ꂩ��ꌾ�\���グ�����Ǝv���܂��B
�@�ٔ������ɂ����āA�����̍čR�ق͂ǂ̂悤�Ɉ����邩�Ƃ������Ƃł������܂����A�����̒��ɂ�����܂��ٔ��Ⴊ�w�E���Ă���܂��Ƃ���A���̔F���������A��{�I�ɂ͒����R�����͒������������Ă��炤���Ƃ�v���̈�Ƃ��Ă���̂��ٔ��������Ǝv���܂��B
�@���ꂪ�ǂ����ǂ����Ƃ����͕̂ʂł����A�����̎����ɂ��������܂��ō��ٔ����A����20�N�S��24���̂�����i�C�t���H���u�����ɂ����܂���ٔ����̌�ӌ����������܂����A�ł́A�Ȃ������ɂ����Ă����v���Ƃ��ėv�����Ă��邩�Ɛ\���܂��ƁA�����̎����ɂ��������܂��A�m�����ٕ���26�N�X��17���������w�E���Ă���Ƃ���A�������R�̉�����m���ɗ\�������K�v������Ƃ����̂����������̉^�p�ɂ����銴�o���Ǝv���܂��B����͂Ȃ����Ɛ\���܂��ƁA�����g�������̍čR�ق��o���Ƃ����b�ɂȂ����Ƃ��ɂ́A�����̏ꍇ�A�u�������������Ă��܂����A����\��ł����B�v�Ƃ������Ƃ��m�F�������܂��B
�@���ꂪ�Ȃ��Ƃǂ��������ƂɂȂ邩�Ƃ������Ƃł����A�����A�{���ɒ�����������肪����̂ł���A�����R���Ƃ��A�������������邱�Ƃɂǂꂾ����Q������̂��Ƃ������Ƃł��B�v����ɁA�ߋ��ɂ܂��L���r�[�R�ق��������̌o���Ȃ̂ł�����ǂ��A���̎���������̍čR�ق͔F�߂���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�����ɂȂ肻���ɂȂ�ƁA�������������̍čR�ق��o�����ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A�������Ƃ��������R�����͒������������Ă��Ȃ��ƁA�R����������Ƌc�_���Ă��ĕ��������ɂȂ�ƁA����͓P�܂��Ƃ������ƂŁA�܂��Ⴄ�`�ł̒����̍čR�ق��o�����Ƃ����x���o�����Ă��܂��B���ɂ͎�ʓI�Ȓ����čR�فA�\���I�����čR�قƂ����āA����Ȃ��������Ƃ��������܂����B
�@�Ƃ��낪�A���̍ٔ���ɂ��������܂��悤�ɁA�����̍čR�ق��o���ȏ�́A���̋Z�p�I�͈́A���������͈̔͂��ꉞ������̂��̂Ƃ��Ċm�肵�����Ƃ�O��ɂ��āA����ɂ��Ē����v�������邩�A�����̗��R���������邩�A�����āA�퍐���i�A�퍐���@���Z�p�I�͈͂ɓ��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��A���i�ɐR�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�ł�����A���������ӂ�ӂ炵���咣�ɂȂ�ƁA�������đi�ׂ̒x���������Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B�����������Ƃ������āA�����炭�����ł́A�����͂�⌵�i�ɒ����R�����͒������������Ă��邱�Ƃ�v�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A����͉��ߏ�̖��ł��̂ŁA���ɒ����R���A����������Ȃ������̍čR�ق�F�߂邱�Ƃɔ��Ƃ������Ƃł͂������܂���ǂ��A�����A������͂���������������Ƃ������Ƃ͈�c�_�̗��R�̒��ɕt�����������Ă�����������ǂ����Ǝv���Ă���܂��B
�@�ȏ�ł��B
���ɓ��ψ����@�ǂ����A�����ψ��A���肢���܂��B
�������ψ��@���͉��w�̗��ꂩ��Q�_�\���グ�܂��B
�@�P�́A���������̍čR�ق̓_�ł��B��قǐX�c�ψ���������������悤�ɁA�������������Ȃ��Ƃł��܂���B������A�������������Ȃ��Ă�����悤�ɂ����炢���ł͂Ȃ����B����͖����̍R�قł͂ł���̂Ɠ����悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���悤�ɕ�������̂ł�����ǂ��A�������ǂ͈̔͂ɂ��邩�Ƃ����̂́A������Ƃ��Ȃ��Ƌc�_�͂ł��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����ɂ��Ă͋c�_���ł���悤�ɂ���悢�Ǝv���܂��B���������Ӗ��Œ��������͕K���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝ����I�ɂ͎v���܂��B
�@�������A�����������s�����Ƃ��O��ł���Ƃ����̂ł���A��قǐX�c�ψ���������������悤�ɁA����������]��ɂ����i�ɉ^�p����邱�ƂȂ��Ƃ������A���������ɘa�����悤�Ȍ`�ł���Ă������������Ǝv���܂��B��X�������͈̔͂��k�߂悤�Ƃ��Ă������Ȃ̂ł�����ǂ��A����͌����ɂ���Ă͗v�|�ύX�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����悤�ȂƂ��낪����܂��̂ŁA�^�p���ɘa���Ă��������Ď����I�ɑΉ��ł���̂�������悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B���ꂪ�P�_�ł��B
�@�Q�_�ڂ͐�قǂ́u���炩�v���v�ł��B�F����̂��낢��ȋc�_�����Ă����������̂ł����A�i�ׂɓ���Ƃ����悤�ȂƂ���̒i�K�Ƃ����̂́A��X�̂悤�ȉ��w�̉�Ђł͂���Ȃɑ����̑i�ׂ����邱�Ƃ��Ȃ��A�x����̂��Ƃ�̒i�K�ł��B�x����̂����͐�琅�ʉ��ł�邩�Ƃ����̂��唼�ł������܂��B��͂�i�ׂɓ���ƂȂ�ƁA����Ȃ�̊o��Ȃ�A��Ђ̒��ł����_�Ƃ������A����Ӗ��ł����ƁA���ق����K�v���������܂��B���̈Ӗ��Ō����ƁA��͂茠���咣������Ă��鑤�Ƃ��ẮA������Ƒi�ׂ̉ߒ��Ō������m�肳��Ă���A����I�Ȃ��̂��Ƃ������̂�S�ۂ��Ȃ����肽���Ƃ����̂��A�����A�v���Ă���܂��B
�@���������Ӗ��Ō����ƁA�u���炩�v�v���̖��炩������邱�Ƃ͂��낢��ȋc�_�����낤�Ƃ������Ƃ͕�����܂����A�g������̖ʂł͑i�ׂ����邽�߂ɂ͂����ȒP�ɂׂ͒�Ȃ���Ƃ����Ƃ���̐S�̒S�ۂƌ����̂ł����A���������K�v������̂ŁA��͂�u���炩�v�v�������Ă�����������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B
�@����A�N�Q��i�����邩�Ƃ������A�퍐���ɗ��Ɣ��ɓ����肪����܂����A�m�I���Y�̉��l�Ƃ����Ӗ��Ō����ƁA�����������Č������p���ł��邱�Ƃ��厖�ł���̂ŁA���{�̍��ۋ����͂̋����Ƃ������Ƃ��l����ƁA�ٔ����鑤�Ƃ��������A�s�����̗��ꂪ�l�����Ƃ��ɂ��̗v�����ǂ̂悤�ɍl���邩�Ƃ�����������낵���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͊����Ă��܂��B
�@�ȏ�ł������܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�ǂ����A��R�ψ��B
����R�ψ��@��قǓ��C�шψ�����䔭���̂���܂����A�����R�����������邽�߂ɂǂ�������V������̂��Ƃ������Ƃł�����ǂ��A�����ґ����炷��Ƃ��Ȃ�n�[�h���������ꍇ������܂��B���̂��Ƃ����ƁA�܂��A�n�قŖ����̐S���J�����ꂽ�ꍇ�A���̎��_�ő��₩�ɒ����R�����������ׂ����ۂ��̔��f�𔗂���ꍇ������܂��B�������A��U�����R�����������܂��ƁA������P�J���A�ʏ�ł��R�J���ȓ��ɒ����R�����肪�o�Ă��܂��܂��B��������ƁA���������ɖ߂�Ȃ��B
�@����ŁA�����̐S���J�����ꂽ�����҂̗��ꂩ�炷��ƁA�T�i����T�i�ٔ����͋t�̔��f���o��\�����\������ƍl������P�[�X������܂��B
�@���������\���܂���ƁA�����҂Ƃ��ĉ\�Ȍ��茠�����m��I�Ɍ��k���鎞�������ɂ��炵�����B�ł������A���k���Ȃ��I�������c�����܂ܐ킢�����A�Ƃ���������܂��B���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ۂɒ����R�����������邱�Ƃ�����ł��闝�R�̈�B
�@������́A�����R���������ł���Ƃ����́A��������܂������R�����������Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ̂ł����A�����R�����������܂��ƁA�R��i�Ƃ��Ė����R���������Ȃ���邱�Ƃ������Ƃ����܂��B��������ƁA�^�p��A�����R�������̐R���̓X�g�b�v����āA�����R���̒��Œ������������āA�����R���̒��Ŕ��f���Ȃ���邱�ƂɂȂ�̂ŁA���ǐR������i�ׂ܂Ŋ܂߂�Ɛ��N�Ԃ̎��Ԃ��|�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�����҂Ƃ��ẮA�Ȃ�ׂ������������������A�������������ƍl���đi�ׂ𐋍s���Ă����āA�����R������������Ă��Ȃ�����A����������������Ƃ������҂̉��ői�גǍs���Ă��钆�ŁA�����Ē���������悤�ȍs�ׂ�����Ƃ����_�ł��A�n�[�h��������B���ꂪ�Ȃ��Ȃ������R�����������ɂ������R�ł��B
���ɓ��ψ����@�����R���������o�Ȃ������̍čR�ق�F�߂邱�Ƃɍ����������邩�C����ɂ��܂��Ă��A���_�̌�ӌ�������悤�ɏ���܂����̂ŁA������������ŁA�܂��c�_�����肢�������Ǝv���܂��B
�@������A���ӌ����x�ɂ��ĉ����䔭���͂������܂����B
�@�ǂ����A�����ψ��B
�������ψ��@��́A��������������A�����@��180���̂Q�ňӌ���������Ƃ����A�ٔ�������ł͂Ȃ��āB���̌����͂�����Ǝ��͒m��Ȃ��̂ł���������������肢�����̂ł����A���Ȃ��Ƃ����{�Ƃ��Č��s�̓����@�̒��ɂ����������������S�Ƃ����ӌ��̐��x������B���ꂩ��A�����̒��ŁA��قnj�w�E�������܂�������̊W�A���ɒ��ׂ܂��ƁA�Ŗ@�ł���69���̂V�Ƃ�17�ŁA�Ŋ֒��������������ցA����͋Z�p�I�͈͂ł�����ǂ��A���ӌ����ł���B
�@���ꂩ��A���Q���������@�̑�42����32�Ƃ����̂ŁA�����ψ�������ْ�̏������ł���Ƃ��A�Ƌ֖@�����܂߂Ă����Ȃ��̂�����܂��B���������āA�厖�Ȃ��Ƃ͋��ӌ������߂āA�����Ŏ������Q�Ă��܂��̂������܂���̂ŁA�������ƂQ�J���ȓ��Ȃ�Q�J���ȓ��ŁA����Ȃ��Ƃ��������瑁�����ƌ��_���o���ƁA��������Ă���Ă��������B�o�Ă������ʂɂ��ẮA�S�������̂ł͂Ȃ��āA���͎Q�l�ɂ���Ƃ������Ƃł���낵���낤���Ǝv���܂��B�`���I�ɂ��̂��ǂ����ɂ��ẮA�����҂���]������Ƃ����t�@�N�^�[������̂͗ǂ��Ǝv���̂ł�����ǂ��A���Ȃ��Ƃ��C�ӂłƂ����C���[�W����낵���낤���ƍl���Ă���܂��B
���ɓ��ψ����@���ɋ��ӌ����x�ɂ��Ă͌�ӌ��������܂����B
���m�Ȓ������@�������̊�撲�����A�m�Ȃł������܂��B
�@���A�����ψ������w�E�����������܂������ӌ����x�ł������܂����A�����@�̑�180���̂Q�ɋK�肪�������܂��B������́A�����̗L�����Ɋւ��ďƉ��Ƃ������x�ł͂���܂���ŁA�@���̓K�p�Ɋւ��鎖���ɂ��܂��āA�ٔ�����������������Ɉӌ������߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����K��ɂȂ��Ă���܂��B
�@������ɂ��܂��āA�ߋ��ɉ������Ⴊ����܂������Ɛ\���グ�܂��ƁA�@�����肳��Ă���A�R���̓K�p���Ⴊ�������܂��B
���ɓ��ψ����@�����v���܂��ƁA���ӌ����x�ɂ��܂��ẮA���̕K�v���̔��f���K�ɂȂ���邩�A���邢�́A����ɑ�����K���ɍs���邩�Ƃ����悤�Ȗ����������Ȃ�������Ȃ��Ƃ͑����܂����A���̏�ł̊F����ł́A�K�v������ꍇ�ƍٔ��������f���čs�����Ǝ��̂Ɋւ��Ă͌����ɒl���邾�낤�Ƃ����F�������������Ɨ������Ă���낵�イ�������܂����B
�@�ǂ����A���C�шψ��B
�����C�шψ��@��قǁA�������̕���������b������܂������A�ǂ̂��炢���p����Ă��邩�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂�����ǂ��A�m�����قł͉ߋ��ɐ������x�����������ɑ��Ĉӌ������߂����Ƃ��������܂��B�L���Ȃ̂́A�v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���̑升�c�����Ɠ����ɐi�s�����R������i�ׂɂ����āA�m�����ق̕���������������ɑ��āA�v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���̉��߁A�^�p���ɂ��Ă̈ӌ������߂����Ƃ��������܂��B���̈ӌ��͔����̒��ɂ��L�ڂ���Ă���܂��B�ٔ����ɂ͂��������������܂����A���ψ�������܂����A��͂�ٔ����Ƃ��ẮA�X�̎���ɂ����Đi���������邩�Ȃ����Ƃ������f���́A���A�\���グ���悤�ȁA�w���������Ă���悤�Ȗ@�����߂ɂ��Ĉӌ������߂邱�Ƃɂ���āA���������̉^�p���܂߂Ĕ��f�̎Q�l�ɂ����Ă����������Ƃɂ��ẮA���ɗL�p���Ǝv���Ă��܂��B
�@�����A����ȏ�ɋ`�������邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����A��ӌ������������āA����ɍS���͂̂悤�Ȃ��̂���������悤�Ȃ��Ƃ����蓾�Ȃ��Ǝv���܂��B�ٔ����̔��f�̎Q�l�ɂ����Ă��������Ƃ������Ƃł����낵���Ƃ͎v���̂ł�����ǂ��B
�@�ȏ�ł��B
���ɓ��ψ����@����ł́A�{���̌�c�_�͂܂������ǂŐ���������ŁA�F�l���ɒ������Ƒ����܂��B
�@�����ŁA���̋c��ł������܂��u�e�@�ցA�c�̓�����̃v���[���v�Ɉڂ肽���Ƒ����܂��B
�@�܂��A��ɑ��Ƃ��\���闧�ꂩ��A���{�m�I���Y����̕ʋ{�l������������肢�\���グ�܂��B
���ʋ{�Q�l�l�@����ł́A���{�m�I���Y����̕ʋ{������������Ă��������܂��B
�@���茳�̎����R�ɂȂ�܂��B�u�m�����������V�X�e�������ɂ��Ă̎Y�ƊE��?�v�Ƒ肵�Ă���܂��B
�@�܂��u�P�D���_�v�ł������܂��B
�@�u�i�P�j�m�����������V�X�e���̌���ɂ��āv�A�i���������Ȃ��A���i�����Ⴂ����m�������p�ł����A�Ђ��Ă͒m�����Y�Ɣ��B�ɏ\���v���ł��Ă��Ȃ��Ƃ̘_���͒Z���I�ł��낤�ƍl���Ă���܂��B�������i�ɒl����a�������Ă���A�����ł���������҂̌����咣���F�߂�ꂽ�P�[�X�͂S?�T���ɒB����Ƃ̕��������܂��B�����N�Q�i�ׂ͊��p��?��i�ɂ����Ȃ��B�����ҊԂ̌��ʼn�������X���̋����ƊE���������܂��B�����A�̈ӐN�Q�ғ��A���ɂ��������]�߂Ȃ��ꍇ�́A�ٔ��ɂ������Ȍ��肪���₩�ɉ�����邱�Ƃ��]�܂�܂��B
�@���Q�����z�ɂ��܂��Ă͐N�Q�s�ׂ̋K�͂ɉ����ĎZ�肳��邱�Ƃ��炷��A�s��K�͂̈قȂ鏔���Ԃő��Q�����z�̍��Ⴊ������͎̂��R�ł���A�N�Q�s�ׂ̎��Ԃ�s��K�͂��l�������ɁA�P�ɑ��Q�����z�̍�����莋����̂͊댯�ł͂Ȃ��낤���ƍl���Ă���܂��B
�@�����܂��āu�i�Q�j�m�����������V�X�e�������̕������v�ł��B
�@�m�����������V�X�e���̉��v�́A���{�̎Y�Ƃ̔��B�Ɋ�^������̂ł���ׂ��B�č��̃p�e���g�g���[���ɐV���Ȏs������悤�ȃV�X�e���́A���{��Ƃ�敾�����A���ۋ����͂̒ቺ�����������Ŗ{���]�|�ł��낤�Ǝv���܂��B
�@�����܂��āu�Q�D�e�_�v�Ɉڂ�܂��B
�@�u�i�P�j�؋����W�v�B
�@�؋����W�͂��������邽�߂ɕč��̃f�B�X�J�o���[�̂悤�Ȑ��x������ƁA���{�ł̃p�e���g�g���[���̊��������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��Ǝv���܂��B�����Ă���܂œ��{�ɂȂ��V���ȏ؋����W���x�����邱�Ƃ́A�i�׃��X�N�傳�����˂Ȃ����Ƃ���A�T�d�ł���ׂ����ƍl���܂��B�F����A�\���䑶���Ǝv���܂�����ǂ��A�č������i�ׂł́A�؋��J���葱�Ŗc��Ȏ��ԂƔ�p�����|�����Ă���܂��B�p�e���g�g���[���̒��ɂ́A�؋��J���葱�̔�p�Ɠ����x�̋��z�Řa�����Ă��Ă���҂����Ȃ��������܂���B�퍐�ł��鎖�Ɖ�Ђ́A���Ƃ���N�Q����������̍R�ق��\�ł����Ă��A�i�o�ς̊ϓ_����A���������p�e���g�g���[���̘a���Ăɉ����Ă��܂��P�[�X���������܂��B�p�e���g�g���[���́A�a�����������ɐV���ȕW�I�i���Ɖ�Ёj�ɑ��āA�����N�Q�i�ׂ��N���܂��B�܂�Ƃ���A�č��̏؋��J���葱���A�p�e���g�g���[���̊��������������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�A����̓��{�̐��x�ł��A�ٔ����̍ٗʂł�����x�̏؋��J���͒S�ۂł���Ǝv���܂��B�����@105���P���ɂ��A�ٔ����͓����҂̐\���Ăɂ��A���������҂ɑ��A�N�Q�s�ׂɂ��ė����邽�߁A�܂��͑��Q�̌v�Z�����邽�߁A�K�v�ƔF�߂����͕��@�̊J���𖽂��邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�J�����߂����҂́A�����ȗ��R�������������ۂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����K����������܂��̂ŁA���Y���ی��ɂ��A�N�Q�F��⑹�Q�̎Z��Ɏx����������������悤�ł���A�؋����W�͋�������������]�n�͂���Ǝv���܂��B
�@�B�i�בO�؋����W�葱�ɂ��ẮA����15�N�̖����i�ז@�����ɂ��A���@132���̂Q�ɑi�בO���W�葱���K�肳��Ă���܂��B�ł��̂ŁA�܂��͂��̊�?���l����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�����܂��āu�i�Q�j�����̈��萫�v�B
�@�@�R���A�R���A�i�ׂł̗L�������f��̓�?���]�܂�܂����A�����A�R���̎�����̂��߂Ɍ��������x��镾�Q���l������K�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����A�Z�p�̐i������������܂��āA���i�������Z���Ȃ�Ƃ��������ɂ����܂��ẮA�����̑����������́A�r�W�l�X�ł̗D�ʐ���ۂ��߂ɂ͏d�v�ł������܂��B���������A�����̈��萫���d���������ɁA���������x�����邱�Ƃ́A�������҂ɂƂ��Ă������ă}�C�i�X�ƂȂ�P�[�X���������܂��B
�@�����@��104���̂R�A��قǗ��A�����Ȉӌ��������������܂�������ǂ��A����ɂ��܂��ẮA����u�L���r�[�����v�ɉ������ٔ��������Ȃ���Ă���̂ł���A�����Ēlj�����K�v�͂Ȃ��Ƃ̌������ł��邩�Ǝv���܂��B�t�ɁA�ٔ�������ύX���邱�Ƃ��Ӑ}�����lj��ł���Ȃ�A�T�d�ȑΉ����K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�A������ɂ��܂��Ă��A�������R�̂�������o�肪�o�^�ɂȂ�A���A������������ɂȂ�悤�Ȏ{��͔����Ă������������Ǝv���܂��B
�@�����܂��āu�i�R�j���Q�����z�v�B
�@�@���Q�����Ƃ́A�N�Q?�ׂɂ��������҂���������Q��F�肵�����́B��قǂ��\���グ�܂������A���Q�����z�̎Z��ɍۂ��ẮA�N�Q?�ׂ̎��Ԃ�s��K�͂��l�����ׂ��B
�@�A�i�ׂ̃C���Z���e�B�u�ړI�ł̒��������̓����͂��ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�P�ɓ����̑��݂�m���Ă������Ƃ݂̂������Č̈ӐN�Q�Ƃ���A����͕č��̃v���N�e�B�X�ł�����ǂ��A�������������Ƃň��Ղɒ���������F�߂�悤�Ȑ��x�́A�p�e���g�g���[���Ɉ�?���ꂩ�˂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�u�i�S�j��?�������v�B
�@�@���~�߂́A�퍐�ɂ������N�Q?�ׂ��ɒ�~�����Ȃ��ƁA�����ł���������҂����������Q�������ނ�ꍇ�ɔF�߂���ׂ����̂ł��낤�ƁB
�@�A�W���K�i�K�{�����ɂ��ẮA�iF�jRAND�錾���Ȃ��ꂽ�ꍇ�́A���Y�����ɂ�鍷�~��������?�g�͐��������ׂ��ł��낤�Ǝv���܂��B�Z�p�W���́A�Z�p�̕��y���Ӑ}�������̂ł��邩��A�W���K�i�K�{�����̌����Ҏ��炪�iF�jRAND��?�����ꍇ�́A�����������~�����͂Ȃ��܂Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���{�҂̕s�������E���������Ɋӂ݂āA���~�������̍s�g��F�߂�ׂ����Ă͑��݂���ƍl���܂��B���~�������ɂ��܂��ẮA�O��̈ψ���ő����Ƃ����܂�������������Ă���Ǝf���Ă���܂��B���ʁA�@�����͈ꗥ�ɐ������邱�Ƃ͍s�킸�A�X�̎��Ăɉ����đΉ����邱�Ƃ��K���ł��낤�Ɛ�������Ă���܂�����ǂ��A��{�I�ɂ͎��ǂ�������Ɏ^���ł������܂��B���������҂Ǝ��{�҂̃o�����X���l���āA�T�d�Ɍ������ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�����ɖ߂�܂��āA�u�i�T�j�����J�A�C�O���M�v�ł������܂��B
�@�@���E�̋K�͂ƂȂ�i�׃V�X�e����?�w���ߒ��ł̏����J��C�O���M�ɂّ͈��͂������܂���B������������ɓ��{�ɑi�ׂ��������ނ悤�Ȏ{��ɂ͎^�������˂܂��B
�@�Ō�u�i�U�j�m���i�@�A�N�Z�X�v�ł��B
�@�@���ٔ����̕��U�͎��̒ቺ���뜜�����Ǝv���܂��B�n���̕��X�̗���������Ă��܂����A�܂���ICT�̊�?�ɂ���ė����������������]�n������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ȏ�ł������܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�����܂��āA������Ɠ��̑㗝�l�o���̂����R�ψ�������������肢�������܂��B
����R�ψ��@�ł́A���̕��������������Ă��������܂��B
�@�z�t�����́u���Q�����z�Ɋւ���m�����������V�X�e���̖��_�v�Ƃ������ƂŁA���Q�����̖�肾���Ƀt�H�[�J�X���Ă���܂�����ǂ��A���̑O�ɁA���_�Ƃ��đS�̂ɂ��Đ\���グ�����Ǝv���܂��B
�@���ٌ͕�m�Ƃ��Ēm���i�ȊO�̒ʏ펖�������������Ă��܂����A���̌o�����炵�܂��āA�m���i�ׁA���ł������i�ׂ͌��������i���邱�Ƃ�����Ɗ����Ă���܂��B
�@�������i�̘a�����܂߂�A�������i�����S����T���Ƃ�����ӌ�������܂����A�����Ƃ���ɂ��܂��ƁA���̊����Ƃ����̂͂�������K���t�����������Ă�����̂̊����Ƃ������Ƃł�����ǂ��A�����҂̎����s�i�̏ꍇ�ł��A���������ڂł킸���̋��K��퍐���猴���ɕ����Ęa��������Ƃ����P�[�X������܂��̂ŁA�������������̂�����̂��Ƃ���ƁA���̐��������̂܂����I���i�̊����Ƃ��ĕ]���ł���̂��ȂƂ����̂��^��Ɋ����Ă���Ƃ���ł��B
�@�ł́A���̂Ȃ��Ȃ������Ƃ�������Ƃ����ƁA���̗��R�̈�͗��̍���ɂ���܂��B�ʏ�̊�ƊԂ̎����ł���A�����̏ꍇ�͑i�ג�N�̑O�̒i�K�Ŏ���W�̏��ނł��Ƃ��A�W�ҊԂ̃��[���Ȃǂ����邽�߁A�������������܂��܂ȏ؋��ő������x�̗����\�ł��B����ɑ��āA�����N�Q�̏ꍇ�́A�K�v�ȏ؋��͂قƂ�ǔ퍐�̓����ɕ݂��Ă���B��O�҂����肷�邱�Ƃ��ɂ߂č���ł���B���邢�́A���i�̍\���̂悤�ɁA�������ĕ��͂��邱�Ƃ��\�Ȃ��̂�����Ƃ͂����A�ŋ߂̐��i�͔��ɕ��G�ŁA���������Ȃ�̋@�\���g���݃\�t�g�E�G�A�Ŏ�������Ă���Ƃ��������̂����邽�߂ɁA���ۏ�A���͂͋ɂ߂č���ł����A���ɉ��炩�̕��͂��ł���Ƃ��Ă��A���̔�p�����ɍ��z�����Ă���B���������āA������Ƃ̑㗝�l�̗���Ƃ��ẮA������Ƃ�������������p���x�ق��邱�Ƃ����ۏ�A�s�\�ł���Ƃ������ƂŁA���؎�i�������Ă��܂��B�������������������ɓ����N�Q�i�ׂ̏ꍇ�ɂ͌����܂��B
�@�܂��A�����̕s���萫���A�����҂ɂƂ��Ă͔��ɑ傫�ȓ����i�ד��L�̖��ł��B����ɂ��ẮA���̐M���Ɋ�Â����������Ă����A����ɂ́A�������x�̘J�͂��₵�āA�i�ג�N�����A���������������҂̗��v�A�ی����͂�\���l������K�v������Ǝv���܂��B
�@�؋����W��i�ɂ��ẮA������o���߂ł���Ƃ��A�C���J�����ł���Ƃ��A���j���[�Ƃ��Ă͔��ɕi�������L�x�ȏɂ���܂��B�t�Ɍ����A���̂��ꂾ����������̃��j���[���@�����Ŏ��X�ƒlj�����Ă������Ƃ����ƁA��͂�����̐��x���������̂�����̂Ƃ��Ďg���Ă��Ȃ��Ƃ������������������߂��Ǝv���܂��B�����g�A�����҂̑��ɗ����ĕ�����o���߂̐\���Ă��F�߂�ꂽ�Ƃ����o���͂���܂���B���x�Ƃ��Ă͗p�ӂ���Ă��Ă��A���Ƀn�[�h�����������x�ɂȂ��Ă���Ƃ������ƂŁA�����������ۂɊ��p�ł���悤�Ȑ��x�ɂ��Ă������Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@����ȏ�ɁA�㗝�l�Ƃ��Ċ�����d�v�Ȗ��́A���Q�����z�̒Ⴓ�ł��B�ʏ�̎����Ɣ�ׂĂ��A�����̖����x�͂��Ȃ�Ⴂ�Ɗ����Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��ẮA�����E�Ŏ��ƂɌg����Ă��铖���҂̊��o�Ƃ��āA�����ŔF�e�����z�����������ꂾ�����Ƃ������x�̐����ɂƂǂ܂��Ă���A�������������o�ő�������悤�Ȑ����ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�傫�Ȗ�肾�Ǝv���܂��B
�@���Q�����z���������Ⴂ���Ƃ������ƂɊւ��ẮA�悭���O���Ƃ̔�r������܂����A����͗]��Ӗ����Ȃ��c�_���Ǝv���܂��B���Ƃ��Ǝs��K�͂��Ⴂ�܂����A�Ώۂ̐��i���Ⴄ���߁A���Q�����z�̐�Ίz���r����c�_�͐����͂������Ǝv���܂��B
�@�����ŁA�����ŋߌo���������Ă܂��āA�����@��102���R���̑������{�����ɂ��Č������Ă݂Ă͂ǂ����Ƃ������ƂŁA���茳�ɔz�t���Ă��鎑����������������Ǝv���܂��B
�@�������{�����ɂ��ẮA��Ίz�ł͂Ȃ��āA�ǂ̒��x�̎��{�����Ɋ�Â��������x���킹�邱�Ƃ��Ó����Ƃ������{�����Ŕ�r�ł��܂��̂ŁA�����тł̔�r���\�ł���Ƃ����_�ŁA���̖��̌����ɂ͓K���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�z�t�����̂P�y�[�W�ځA�܂��P�ԁA�䂪���̍ٔ���ɂ����鑹�Q�����z�A�����ŋ�̓I�Ɍ�������̂́A���{�����ł�����ǂ��A���ꂪ�Ⴂ�̂��ǂ����Ƃ����ƁA�Ⴂ�ƍl���Ă���܂��B
�@�P�Ԗڂ́A�܂��A���Ȃ�Â������ŕ����X�N�̂��̂ł��B
�@�č��ł͕���11���B�č��͔��ɍ��߂��āA�����Ɣ�r���邱�Ǝ��̂��i���Z���X���Ƃ����ӌ��͂悭������܂�����ǂ��A�h�C�c��t�����X�͂ǂ����Ƃ����ƁA�h�C�c�͂W�`10���A�t�����X�͂W���ŁA���̓����̒����ʼn䂪���ŔF�e���ꂽ���{�����̕��ρA����͔����̕��ςł�����ǂ��A�S���Ƃ������ƂŁA�Q�{�ȏ�̊J��������Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂��B
�@�Q�ԖځA����19�N�x�������Y�ƍ��Y�����x��蒲���������̌����ł́A�č��ł�20���`30�����F�肳��鎖�������Ȃ��Ȃ����Ƃ�����Ă��܂��B
�@�R�ԖځA21�N�x�A���͂������̂ŏȗ����܂�����ǂ��A���̕ł��ƁA2004�N�`2008�N��46���̔���͂������ʁA���Ԃɂ�������{���������i�@������{�����̕����Ⴂ���Ƃ����������Ƃ������Ƃ�����Ă��܂��B
�@���́A���O���̔�r�����A�ނ��낱�̖��ԂŔC�ӂ̌`�Ń��C�Z���X�_��Őݒ肳��闿�������A�N�Q�i�ׂɂ����ď��i�����������҂ɑ��ĔF�߂��闿���̕����Ⴂ�Ƃ������Ƃ����d��Ȗ��ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@�Q�ԖځA�����@��102���R���̔���̔��f�Ɋւ�����_�Ƃ������Ƃł�����ǂ��A�܂��͂Q�y�[�W�ځA�ٔ���̑������{�����̎Z��̍l�����Ƃ����̂́A�܂���ƂȂ闿����F�肵����ŁA����Ɍʋ�̓I�Ȏ��Ă̎�����������đ���������Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̂Q�ɕ����Č�������܂��ƁA�܂��A�Q�j�u����̓����̎��{�����̕��ϒl�v�ɂ��Ăł�����ǂ��A����ł́A���C�Z���X���т�����ꍇ�ɂ͎��ђl�A�Ȃ��ꍇ�ɂ͓���Z�p����̓����̕��ϒl���邢�͍��L�����̃��C�Z���X������p���邱�Ƃ���ʓI�ł��B
�@�������A�C�ӂ̃��C�Z���X���Ō_��Őݒ肵�������ƁA�N�Q�i�ׂɂ܂Ŏ����ď��i���������҂ɔF�߂��闿��������Ƃ����̂́A�����҂̗��ꂩ�炷��Δ��ɕs�������Ɗ������邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA�t�����X�ł́A����ŔF�߂�����̂͋ƊE�Ŋ��K�I�ɔF�߂��Ă�����̂�1.5�{�ł���Ƃ������Ƃ�����Ă��܂���B���R�Ƃ��ẮA�N�Q�҂ł���퍐�́A�����ɉۂ��ꂽ���������߂闧��ɂȂ�����ł���Ƃ��������Ƃ��������Ă��܂��B
�@�����A�Ⴆ�����ɋ����Ă���悤�ɁALTE�����v�[���ł���Ƃ��A���̑��̓����v�[���A���邢�͌ʂ̓����̃��C�Z���X���ł��A�����Ƀ��C�Z���X�_���������Ă����A���ꂮ�炢�̗����ł����ł��B�����A�R�J���ȓ��Ɍ����܂Ƃ܂�Ȃ��ꍇ�ɂ́A1.5�{�ɂ��܂��Ƃ��A�����������`�Ŏ��������ɂ��������قǍ��������łȂ�����ӂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ʏ�ł����A���ꂩ��A���쌠�N�Q�̎��ĂɂȂ�܂����A�\�t�g�E�G�A�̊�Ɠ��̈�@�R�s�[�������ʕ�Ȃǂɂ���Ĕ������ꂽ�ꍇ�A�����Ғc�̂́A�a���Ō���������ꍇ�́A���K�i�̍w�����ɉ����āA���{���x�̔��������x���킹�邱�Ƃ������Ƃ��邱�Ƃ���ʓI�ł��B���\����Ă���Ƃ���ł��ƁA�^�s�������s���R�s�[��F�߂��Ƃ������ƂŁA1.5�{�̔��������x���������Ƃ�����Ă��܂��B���K�i�̍w���ƍ��킹���2.5�{�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
�@���̂����������Ƃ�����Ă��邩�Ƃ����ƁA���K�i�̍w���������x�����ςނƂ����̂ł���A������Ȃ����蓾�ł�����A�܂Ƃ��ɔ������Ƃ����l�Ԃ͒N�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���������āA�i�ׂɎ������ނ̂ł͂Ȃ��A�C�ӂŌ�������̂ł���A��������ɂ݂�������z�ɐݒ肷��K�v������A�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
�@���������āA�t�����X�̍l�����ɂ���悤�ɁA��{�ƂȂ闿�����̂��̂��ʏ�̃��C�Z���X�_��Őݒ肳��闿�����������Ȃ���A�s�����ł���Ƃ������Ƃ�������Ǝv���܂��B
�@�R�y�[�W�A���x�͋�̓I����Ɋ�Â������Ɋւ���]���ɂ��Ăł�����ǂ��A���͂�����ƁA���z�����ɔ��f�����ꍇ�����ɑ����Ƃ����肪���ĂƂ��ƍl���Ă���܂��B
�@�R�y�[�W�̐^���ɕ\������܂�����ǂ��A����͓��{�ٗ��m������ψ���̓��\���Ɍf�ڂ���Ă�����̂ł�����ǂ��A145���̔���͂������ʁA���܂��܂ȃt�@�N�^�[�����������A���������A�ǂ���ōl������Ă��邩�Ƃ������v���Ƃ������̂ł��B
�@���̕\�̉��̖@�����O�Ə����Ă���܂�����ǂ��A����10�N�����ŁA�����̓����@�͑�102���Q���A���݂͂R���ł�����ǂ��A�����͒ʏ��ׂ������Ȏ��{�����Ƃ����u�ʏ�v�Ƃ����������������̂��A�ʋ�̓I�Ȏ��Ă̎�����l�����āA��荂�z�ȔF����\�ɂ���Ƃ������ƂŁA�u�ʏ�v�̕������폜���ꂽ�Ƃ����̂����̖@�����ł�����ǂ��A�@�����O�́u�ʏ�v���������������A�قƂ�njʋ�̓I�Ȏ��Ă��l������Ă��Ȃ������B����ɑ��āA�@������͍l��������̂����ɑ����Ă���̂ł�����ǂ��A���̃}�C�i�X�Ƃ����̂́A���z�v�����v���X�P�A���z�v�����}�C�i�X�P�Ƃ������ƂŁA�������Ă���v���̐���ςݏグ�����̂ł�����ǂ��A�����ςݏグ��ƁA���������̋Z�p���e��d�v���̓}�C�i�X�U�Ƃ����悤�ɁA�����݃}�C�i�X�ɂȂ��Ă���B���Ɂu���̑��v�Ƃ������ƂŁA���܂��܂Ȏ���ɂ��Ă̓}�C�i�X14�ƂȂ��Ă���A�S�̓I�Ƀv���X�����ɍl������鎖��͂Ȃ��Ȃ��F�肳��Â炭�A���z�����̎���ϋɓI�ɔF�肳��Ă���X��������Ƃ������Ƃ������܂��B
�@���Ԃ̊W������܂��̂ŁA�ʋ�̓I�Ȕ���̓��e�͊������܂�����ǂ��A�P���������܂��ƁA�Z�p�I�ȏd�v�x�Ƃ����_�ł́A����̒��ɂ͂��̓��������͔��ɃV���u���ŁA�Z�p�I�ɂ͓�Փx�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���z�����ōl�����Ă�����̂����Ȃ肠��܂��B
�@�������A���p���̗e�Ր���R�X�g�̊ϓ_���猾���A�V���v���Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ͂������{�����Ƃ������ƂŁA���������ł���Ƃ����ꍇ������܂��B���A�V���v���ł���Ύ��p�������ۂ��i���������Ȃ�A�R�X�g���ጸ�ł���ꍇ������A�Y�Ə�̗��p���l�͍����Ƃ������Ƃ�������ꍇ������܂��B�������A�ٔ��������ƁA����v�f�����z�����ōl�����邱�Ƃ��\���ȗ��t��������̂��Ƃ������Ƃɂ��āA�^�₪������̂����Ȃ��炸�����܂��B
�@�X�̔���̓��e����̓I�Ɍ������Ă��A�ٔ���͗l�X�Ȏ�������z�����ōl������A�����������}�C���h�Ɏx�z����Ă���悤�Ɍ����܂��B
�@�Ƃ������ƂŁA�S�y�[�W�̉�����Q�ڂ̂Ƃ���ł�����ǂ��A��قǂ̕ɂ������Ƃ���A�X�̍ٔ���̒������Ă��A���Ԃɂ�������{���������i�@������{�����̕����Ⴂ�X���Ƃ������Ƃ��m�F�ł��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�S�y�[�W�̈�ԉ��ɏ����Ă���̂́A����10�N�����@�Ɋւ���H�Ə��L���@��������̕��͂ł�����ǂ��A�u�N�Q����������Ȃ���A���{�����略���K�v���Ȃ��A���ɐN�Q���������ꂽ�Ƃ��Ă��A�x�����ׂ����{�������z�������Ƀ��C�Z���X���������҂Ɠ������{���ł́A���l�̌����d���A���O�Ƀ��C�Z���X��\�����ނƂ����C���Z���e�B�u���������A�N�Q�����������˂Ȃ��B�v�A����͕���10�N�ɉ����@�̍ۂɎw�E����Ă������_�Ȃ̂ł�����ǂ��A���A�䗗�����������悤�ɁA�ŋ߂̍ٔ���ł́A�N�Q���������ꂽ�Ƃ��Ă��A�x�����ׂ����{�������z�������Ƀ��C�Z���X�����҂Ɠ����ǂ��납�A��������Ⴍ�čςނƂ����ɂȂ��Ă���B����͔��ɑ傫�Ȗ��ł���ƍl���Ă���܂��B
�@�T�y�[�W�ł́A����10�N�����̑O��ōٔ���ɕω��͂Ȃ������̂��Ƃ����܂��ƁA������ׂ����Љ�͊������܂�����ǂ��A���̔�������܂��ƁA����10�N�����̂��炭��́A��قǃt�����X�̍l��������Љ�܂������A�ʏ�̃��C�Z���X�_��������߂̗����Ƃ��邱�Ƃ������ҊԂ̍����I�ӎv�ł���Ƃ����l�����Ɋ�Â��āA���߂̗�����F�肵�Ă�����̂���������܂������A�����o��ɏ]���āA��������������͌����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���Ƃ����ł��B
�@���A�T�y�[�W�̂T�j�N���b�N�z�C�[�����ڂ�iPod�̓����N�Q�ɓ�����Ɣ��f���ꂽ����B����͎��������҂̑㗝�l�߂����Ăł�����ǂ��A���̎��Ă͂����镔�i�����ł͂Ȃ��āA�T�y�[�W�̈�ԉ��̎ʐ^�ɂ���悤�ɁAiPod�̑S�ʂ̉������̊ۂ��^�b�`�Z���T�[�̕����̍\�����̂��̂����������̑Ώۂł���Ƃ������ƂŁA���i�̒��j�����������̓����I�����ł���Ɣ��f���ꂽ���Ăł��B�U�y�[�W�A�݂͂̒������Q�z�̔F��Ɋւ��锻�����̔����ł��B���{������T�łɂ��A���̕���̕��ϒl��5.7���ł���Ƃ������ƂŁA��قǂ̊�l��5.7���ł���Ƃ����F�肪����܂����B
�@���̉����ʋ�̓I�Ȏ��ĂɊւ��锻�f�̕����ł�����ǂ��u�؋��ɂ��A�A�b�v�����g�A�N���b�N�z�C�[���������e���i�̑��쐫�̗v�Ƃ��Ĉʒu�t���A�V�@�\�A�Z�[���X�|�C���g�Ƃ��Ă����ϋɓI�ɐ�`���A�D�]���Ă������Ƃ��F�߂���v�Ƃ������ƂŁA���������̎����F�肵�Ă��܂��B
�@����ɑ��āu�܂��v�ȉ������z�����̔��f�ɂȂ�̂ł�����ǂ��A�؋��ɂ��A�u�A�b�v���v�̃u�����h�̉��l�͔��ɍ����A�����e���i�̃f�U�C���A�J���[�o���G�[�V�������X�̑i���͂͂��Ȃ苭�����̂ł���AiPod�̌����V�F�A60���ɒB���Ă��邪�A����͌����̔̔��w�͂��������x�v�����Ă��邱�Ƃ��F�߂���ƁB
�@���̕]�����̂͌����҂̑㗝�l�̎��Ƃ��Ă������Ƃ����Ƃ͎v���܂��B�����A���͂��̎��ŁA�u�����Ȏ��{�����́A�����ƔF�߂�̂������ł���v�Ƃ������ƂŁA���̕����͔閧�ێ��̑ΏۂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��̓I�Ȑ����͊J���ł��܂��A5.7���̐��\���̈�Ƃ����������F�肳��Ă��܂��B���̐��\���̈�ɂ��Ă��闝�R�Ƃ��ẮA�����̐��s�̕��������ł��B�Ƃ������ƂŁA���́A�����̗����̐ݒ�Ɋւ��锻�f�̕������A���Q�z�̕]���̖��ł���Ƃ������ƂŁA�ٔ����̍ٗʓI�Ȕ��f�Ɉς˂��Ă���̂ł����A���̕]���ɑ��錠���҂̔[���x���Ⴂ�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�Ō�A�V�y�[�W�ł����A�d�v�Ȃ͖̂��Ԃ̔C�ӂ̃��C�Z���X�_������ٔ���ŔF�߂��Ă��闦���Ⴂ�Ƃ������ƂŁA����͂P���ƂQ���ɂ��Ă��A���l�̌X�����F�߂���ƍl���Ă���܂��B
����ł́A�����E�x���`���[��ƂɂƂ��āA�������擾���悤�Ƃ����C���Z���e�B�u�������Ȃ��B���ꂩ��A�悭�m���̗L�����p�Ƃ������ƂŁA�m�I���Y����S�ۂƂ��ċ�s�Z������Ƃ������Ƃ��c�_�����Ƃ���ł�����ǂ��A�����������ł͌o�ϓI���l���F�߂�ꂸ�A�����p���ł��Ȃ��Ƃ����͓̂��R�̌��ʂł��낤�Ǝv���܂��B
�@�ȏ�Ő������I��点�Ă��������܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�Ō�ɁA�������x�����ǂ������������̐��������肢�������܂��B
���m�Ȓ������@�ψ����A���肪�Ƃ��������܂��B
�@���茳�ɂ������܂������T�u�m�����������Ɋւ��錻��Ɠ������̎�g�v�ɂ��āA����������Ă��������܂��B�e�X���C�h�E���̕��Ƀy�[�W�ԍ����������܂��̂ŁA�y�[�W�ԍ����w�肵�Ȃ������������Ă������������Ǝv���܂��B
�@�X���C�h�P�ł����A�^�ɐ}�Q�Ƃ����\���������܂��B�䗗���������܂��ƁA���̕��ɉ��F���Ђ��̂悤�Ȃ��̂��L�ڂ���Ă���܂��āA200���Ƃ����\�������Ă���܂�����ǂ��A���ꂪ���{�ɂ�����i�����̐��ڂ�\���Ă���܂��āA��ē��̂Ƃ���A�����̏ł������܂��B
�@���̂悤�ȉ����̏ɂȂ�܂��ƁA���{�ł͌����J�����i�܂Ȃ��Ȃ�Ƃ��A���邢�͊C�O�̊�Ƃ��猩�āA���{�ɏo�肷�邱�Ƃɖ��͂��Ȃ��Ȃ�Ƃ����w�E������܂��̂ŁA���̓_�ɂ��܂��āA�m�F�������Ǝv���܂��B�䗗���������Ă���܂��A�����}�Q�ɁA�Ԃ��܂���O���t�Ɛ��܂���O���t���������܂��B�Ԃ��܂���O���t�͊�Ƃɂ����錤���J�����\���Ă���܂��B���܂���O���t�͏o�茏����\���Ă���܂��āA�i�����������ł���ɂ�������炸�A���{�̊�Ƃ͔��Ɍ����J���ɒ��͂���Ă����܂��āA�����J����͂�������L�тĂ��܂����A�o��ɂ��܂��Ă����l�ɉE���オ��̏ł������܂��B
�@�����A�o��ɂ��܂��ẮA�ߔN�A����~�X���ɂ������܂��āA���̌�����T�肽���Ǝv���܂��B���ׂɂ������܂��}�R���䗗���������܂��ƁA���ۏo��̌�����\���Ă���܂��B�䗗�̂Ƃ���A���ۏo��̌����͔��ɑ����Ă���܂��āA��Ƃ̊F�l�͌���ꂽ���\�[�X�̒��ŁA���ۏo��Ƀ��\�[�X��U�蕪���Ă���������l�q���m�F�ł��邩�Ǝv���܂��B
�@�܂��A��ԍ��̐}�P���䗗���������܂��ƁA�_�O���t���������܂��āA�����̏o�茏���Ɠo�^����\���Ă���܂��B�s���N�̂Ƃ���͓o�^�̌�����\���Ă���܂��B�o�^�̌������䗗���������܂��ƁA�ߔN�A�����X���ɂ��邱�Ƃ���m�F���������邩�Ǝv���܂��B�܂��A���܂���O���t�͓o�^���ł������܂����A��������㏸�X���ɂ��邱�Ƃ���m�F���������邩�Ǝv���܂��B
�@���̂悤�ɁA�ߔN�̏o��̌����ɂ��܂��ẮA���ۏo��ւ̃��\�[�X�̐U�蕪���ł��Ƃ��A���邢�͊�Ƃ̊F�l�������̗ʂ��玿�ւ̓]����}��ꂽ���ʂł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@�P�y�[�W�̉��̕��ɕ\���������܂�����ǂ��A���̈�ԉ��̂Ƃ���ɁA�O���l�ɂ��o��̌������L�ڂ��Ă������܂��B��������䗗���������܂��ƁA���[�}���V���b�N�ȍ~�A�����X���ɂ������܂��āA�����ē��{�̓����V�X�e���A�����o�肪�O���l����I��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@���̃X���C�h�Q�A������̓g���\���E���C�^�[�Ђ��s���Ă���܂��������w�W�Ƃ�����Ƃ̃����L���O�ł������܂��B
�@������ɂ�2015�N��2014�N�ƃf�[�^���d�˂ĕ\�L���Ă���܂�����ǂ��A���{��Ƃ́A���E�̏��100�Ђ̒���40�Ђ��A2015�N�ł��ƃ����L���O�ɓ����Ă���܂��āA�Q�N�A���Ő��E�P�ʂɂȂ��Ă���܂��B�����������������w�W�ɂ��������͂�����A���{�̊�Ƃ̌����J���̐��ʂ��o�Ă���l�q���ǂݎ��邩�Ǝv���܂��B
�@���ɁA�X���C�h�R�Ɉڂ��Ă��������܂��āA��قnj䗗���������܂����X���C�h�P�̃A�����J�łł������܂��B��قǂƓ��l�A�^�ɂ������܂��}�Q���䗗���������܂��ƁA�A�����J�̏ꍇ�ɂ́A�i������R&D����o�茏�����A�S�ĉE���オ��̂悤�Ɍ����邩�Ƒ����܂��B�����A�o�茏���ɂ��܂��ẮA�E���ɂ������܂��}�R���䗗���������܂��ƕ�����܂��悤�ɁA�A�����J�̓������x�ł́A�o��̒��ɐV�K�̏o��ƍēx�o�肷��o��Ƃ��������Ă���܂��āA�Ԃ����ŕ`���Ă������܂��V�K�̏o��ɂ��܂��ẮA2000�N�ȍ~�A�قډ����̏ł������܂��B�i����������������Ƃ����܂��āA�V�����o�肪�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�\���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@�܂��A��ԍ��̐}�P���䗗���������܂��ƁA�A�����J�̏ꍇ�́A�s���N�ŕ\���Ă���܂��o�^�������ߔN�A�����X���ł������܂����A�o�^�������܂���O���t�ŕ\���Ă���܂����A�����X���ł��邱�Ƃ��ǂݎ��邩�Ƒ����܂��B
�@���̃X���C�h�S�ł����A�����b���ς��܂��āA�Z�p�̕ω��������ɂǂ��������e�����y�ڂ����Ƃ����ϓ_�ō���������ɂȂ��Ă���܂��B
�@������ł́AIT�Z�p���Љ���Ă��������Ă���܂�����ǂ��AIT�Z�p�̐i���ɂ��܂��āA�\�t�g�E�G�A�Ƒg�ݍ��킹��ꂽ�o�肪���ɑ����Ă���ƔF�����Ă���܂��B
�@����������IT�Z�p�𗘗p���鐻�i�ɂ��܂��ẮA�c��ȓ������֗^���邱�ƂɂȂ�܂��āA�܂��A�����֘A���������L���錠���҂����l�����Ă���ƔF�����Ă���܂��B
�@�X���C�h�S�ł́A�v�����^�[�̗�ƃJ�����̗�������Ă������܂����A������̐}�Ɏ������Ƃ���A���ɑ����̓���������ł���Ƃ������Ƃ���m�F���������邩�Ǝv���܂��B
�@�X���C�h�T�A���̂悤�ȎY�ƍ\���̕ω����m���ɋy�ڂ��e���ł������܂����AIT�Z�p�����p����邱�Ƃɂ��܂��āA��قnj���������Ƃ���A�ꐻ�i�̒��ɐ�߂�����̐��͔���I�ɑ��債�Ă���܂��B
�@����������IT�Z�p�́A�䂪�������ɋ����͂������Ă���܂������Ƃł��Ƃ��C���t���Y�Ƃɂ��A����L���邱�Ƃ��\�z����Ă���܂��B
�@�����������Y�ƍ\���̕ω��ɔ����A�ߎ��ł́AIT�����ł͂Ȃ���IoT�Ƃ������t���b��ɂȂ��Ă���܂�����ǂ��A�i�ׂƂ��Č��݉����Ȃ����̂��܂ޒm�����������̂��߂̃R�X�g�̑��傪�����܂��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@���̃R�X�g�̑��傪�Z�p�̐i�W�ɍ��킹���K���Ȃ��̂ł���A�S�����͂Ȃ��킯�ł������܂�����ǂ��A���ꂪ�ߑ�ȃR�X�g�̑���Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA�C�m�x�[�V������j�Q���邨���������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��āA��ԉ��ɋL�ڂ��܂����Ƃ���A�����������̌����ɓ�����܂��ẮA�Y�ƍ\���̕ω��������炷�e��������ɓ��ꂽ�c�_���d�v�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@���A�X���C�h�U�Ɉڂ�܂��āA������̌����ψ���Ō䌟�����������Ă���܂��e�_�_�ɂ��܂��āA����̌�����������Ă��������܂��B
�@�܂��A�X���C�h�U�͌����̈��萫�ɂ��Ăł������܂��B������̓X���C�h�ɋL�ڂ��Ă���܂��悤�Ȍo�܂��o�܂��Ė@�������Ȃ���Ă��Ă���܂��B��ԉ��ɂ������܂��Ƃ���A����26�N�����ɂ��܂��āA�ًc�̐\�����x��n�݂��Ă���܂��B�������Ƃ��܂��ẮA���̑n�݂̖ړI�������̑����̈��艻�Ƃ������Ƃł������܂��̂ŁA���̓����𒍎��������ƍl���Ă���܂��B
�@���A�X���C�h�V�͏؋����W�葱�ɂ��܂��Ă܂Ƃ߂����̂ł������܂��B���ɕ\�ł܂Ƃ߂Ă������܂����A�\�ɋL�ڂ̂Ƃ���A�����@�͕���11�N�A16�N�ɂ��낢��@�����������Ă��������Ă���܂�����ǂ��A������������i�ז@���邢�͖����i�ז@�K���̓����Ƃ����`�ŋK��𐧒肳���Ă��������Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@���̂悤�ɁA�����@�ɂ�����؋����W�葱�݂̍������������ɂ�����܂��ẮA�����i�ז@�Ƃ̐������ł��Ƃ��A�o�����X�ɂ��čl�����Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@�܂��A���݂̏؋����W�葱�ɂ��܂��āA���낢��c�_���Ȃ���Ă���Ƃ���ł������܂����A�������ɂ��܂��ẮA�����������ɂȂ蓾��Ƃ������ꐫ���������܂��̂ŁA�����������Ƃ�����l�����Ă��������K�v������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@����ɁA�؋����W�葱���L���܂����v�Ɛ��x�̈��p�̂�����ɂ��܂��Ă��A���̗��ʂ��猟�����K�v�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@���ɃX���C�h�W�ԁA������͐�قǏ�R�ψ�������A�O���Ƃ̔�r�ɂ����܂��āA���Q�����z���Ίz�Ŕ�r���邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E���������܂������A��������������̂ɂȂ��Ă���܂��B
�@�X���C�h�W�ɂ������܂��O���t�́A�A�����J�Ɠ��{�ɂ�����m���i�ׂɂ����ĔF�肳��܂������Q�����z�̒����l���r�������̂ł������܂��B�R�̋�Ԃɕ�����Ă���܂��āA��ԍ�����2000�N����2004�N�ɓ��{�ŔF�߂�ꂽ���Q�����z�̒����l��\���Ă���܂��B���̉E�����A�A�����J�œ������Ԃɂ����ĔF�߂�ꂽ���Q�����z�̒����l�B���̉E�ׂ��A�A�����J�ɂ����Ĕ��R�݂̂𒊏o�������́A����ɂ��̉E�ׂ��A�����J�ɂ����čٔ����ɂ��F�e���ꂽ���Q�����z�𒊏o�������̂ɂȂ��Ă���܂��B
�@���̂R���r���Ă��������܂��ƁA�A�����J�ɂ����܂��Ă��A�ΐF�̒����l�ɂ��܂��ẮA�ߔN�A�E��������̌X���ɂ��邱�Ƃ���m�F���������邩�Ǝv���܂��B
�@�܂��A���{�ƃA�����J���r����ɓ�����܂��ẮA�����̕��̓A�����J�ɂ����锆�R�ŔF�߂�ꂽ���Q�����z�Ƃ̑Δ�œ��{�̔����z�����Ȃ��Ƃ����c�_������Ă���Ǝv���܂�����ǂ��A��͂肱�������������z�̐�Ίz���r����ɓ�����܂��ẮA�@���x�̈Ⴂ�ɂ����ӂ��Ă��������K�v������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@���ɃX���C�h�X�A������͒m���i�ׂɂ����܂��āA�A�����J�����������̂ł������܂�����ǂ��A�ߋ��ɔF�e����܂������Q�����z�̍ō��l��\�������̂ł������܂��B�ō��l�ł������܂��̂ŁA���ْl�Ƃ������ƂɂȂ�܂��āA���낢��ƈ٘_�͂��邩�Ǝv���܂�����ǂ��A��������������Ă����|�́A���̍��̕��������V�X�e���̒��łǂ��܂Ŕ����z���F�߂�꓾��̂��Ƃ������E�l�������Ƃ����Ӗ��Œ��Ă������܂��B
�@�䗗�̂Ƃ���A���{�͍�����R�ԖڂɈʒu���Ă���܂��āA�悭��r�̑ΏۂƂ���܂��؍��A�����A�C�M���X�A�h�C�c��葽���z�ɂȂ��Ă���܂��B�����A���������قǐ\���グ�܂����Ƃ���A�e���̖@���x�̈Ⴂ����������F��������Ŕ�r����K�v���������܂��̂ŁA�����������ϓ_����䗗����������Ǝv���܂��B
�@�܂��A�����z�������Ȃ�ƃC�m�x�[�V�����͑��i�����̂��Ƃ����c�_���������܂����A��̓I�ȍ��̖��O��������ƍ����x�������邩������܂���ǂ��A���{���������ɂ������܂��Q�J�����A���{�����C�m�x�[�V���������i���ꂽ�����ƍl���܂��ƁA�����͂ǂ����ȂƂ����l�������������܂��āA�����z�ƃC�m�x�[�V�����Ƃ̊W�Ƃ������̂��A�]��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@�X���C�h10�A11�Ԃ͌�Q�l�܂łɒ������̂ł������܂��B��قLjψ��̊F�l�̒�������A�����J�ɂ�����p�e���g�g���[���̓����̌�Љ����܂�������ǂ��A�A�����J�ł̓p�e���g�g���[���ɂ��i�ׂ��}�����Ă���܂��āA������K������悤�Ȑ��x�̉���������Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@11�Ԗڂ̃X���C�h�ɂ́A�i�����ɂ��܂��āA�A�����J�ł͑����X�������������̂��A2014�N���猸�����Ă��邱�ƁA�܂��A������}�邽�߁A�����҃��r���[�̂悤�Ȑ��x���������ꂽ��ł��Ƃ��A���邢�͓����K�i���̗v���̌��i�����Ȃ��ꂽ��ł��Ƃ��Ƃ����Ƃ������Љ�Ă���܂��B
�@�X���C�h12���������ɂ����錟���ɂ��܂��Č�Љ����̂ł������܂��B������̌����ψ���̕��ł����������V�X�e���ɂ��܂��āA���낢���c�_���������Ă���Ƃ���ł������܂����A�������Ƃ��܂��Ă��A�������̗���ł�����̘g�͂��̒��ɋL�ڂ��܂��悤�Ȋϓ_�ŕ��������V�X�e���̍��x���ł��Ƃ��A���邢�͓����̌����̈��艻�A���邢�͎��̌����}�邽�߂̎{����������Ă��������ƍl���Ă���܂��B
�@�P�Ԗڂ́A������Ƃł��Ƃ��A�n����Ƃ̕��������V�X�e���̃A�N�Z�X���̌���A�����R���E�R���̑̐��̈�w�̏[���A�R�Ԗڂ���قǂ��炢�낢��j�[�Y�������Ă���܂�����ǂ��A�����������Y�ƊE�̊F�l�̃j�[�Y�ɉ�����悤�ȃT�[�r�X�̌���A����ɁA�Z�p�Ɩ@���Ƃ̑o���ɂ��Ēʂ����m���l�ނ̈琬�A�܂��A�䂪���̒m�����x���A�W�A�����ɓW�J���܂��āA��Ƃ̊F�l���������₷���������ׂ��Ƃ�����ӌ����������܂��̂ŁA������������g�ɂ��܂��Ă��A�������Ă��������ƍl���Ă���܂��B
�@�g�͂��̉��ɋL�ڂ��܂����悤�ɁA������̌����ψ���̈ψ��ł���������Ⴂ�܂��A���ѐ搶�ɓ������ŊJ�Â��Ă���܂����������̈ψ���̈ψ����ɂȂ��Ă��������Ă���܂��āA�����̈��萫�A�؋����W�A���Q�����݂̍���ɂ��܂��āA�@���ʂ���䌟�����������Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@������̏��ɂ��܂��ẮA�m�������ǂɂ������Ă��������Ă���Ƃ���ł������܂��B
�@�܂��A�����̈��萫�̋c�_�A����͂�������������ݒ肷��i�K�ł�������Ƃ���������ݒ肷�邱�Ƃ��̗v���Ƒ����܂��̂ŁA���ɏ����Ă������܂��Ƃ���A�Y�ƍ\���R�c��̒��ɍ�N����R���i���Ǘ����ψ���Ƃ������̂�݂��܂��āA�R���̎��̌���Ɍ�������g�����{���Ă���Ƃ���ł������܂��B
12�y�[�W�ڂ̈�ԉ��̘g�݂͂ł������܂����A���N�x�ȍ~�A����܂łɌ�Љ���Y�ƍ\���̕ω��ł��Ƃ��A�������ōs���Ă���܂����������̌��ʁA���邢�͂�����̌����ψ���ł̌䌟���̌��ʂ܂��܂��āA�K�v�ɉ����܂��āA�������̎Y�ƍ\���R�c��̒��ŐR�c�����Ă��������ƍl���Ă���܂��B
�@�Ō�ɂ��Ă���܂��X���C�h13�ł������܂����A��قnj�Љ�܂����Y�ƍ\���R�c��̒��ɂ������܂��R���i���Ǘ����ψ���ōs���Ă���܂��c�_�ƁA������������i���Ǘ��̎�g�̊W������������̂ł������܂��B��Q�Ƃ���������K���ł������܂��B
�@����������̌�����͈ȏ�ł������܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B���Ԃ̐��������܂�����ǂ��A�������܂��O�����炢�������܂����ɂ��āA�����䔭����������肢�������Ƒ����܂��B�������ł��傤���B
�@�ǂ����A����c�ψ��B
������c�ψ��@�M�d�Ȍ�ӌ��A�v���[���A���肪�Ƃ��������܂����B�ʋ{�Q�l�l�̃y�[�p�[�̂Q�y�[�W�ڂ̏؋����W�̇B�A�i�בO�̏؋����W�葱�ɂ��ĂƂ����Ƃ���ł������܂����A���i�@�����ɂ���132���̂Q�ɑi�בO���W�葱���ł����Ƃ����̂́A����͌�w�E�̂Ƃ���Ȃ̂ł����A����͎��ǂ��ٌ�m�����炵���Ȃ��̂�������܂���ǂ��A���Ɏg�����肪�����A�g���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁA���̈�Ԃ̗��R���A��͂�T���N���V�������Ȃ��A�����͂��Ȃ��Ƃ����_�ł͂Ȃ����ƌ����Ă���̂ł����A�����̇B�́u�܂��͂��̊��p���l����ׂ��v�Ƃ������Ƃ́A����͌����x�̂܂܂Ƃ������ƂȂ̂��A����Ƃ�������x�@���������l���ɂȂ��Ă���̂��Ƃ����_���������������Ǝv���܂��B��낵�����肢���܂��B
���ɓ��ψ����@�ǂ����A�ʋ{�Q�l�l�A���肢���܂��B
���ʋ{�Q�l�l�@�䎿�₠�肪�Ƃ��������܂��B���̓_�ɂ��܂��ẮA������A�m�I���Y����̉���̒��ł��A������������132���̂Q�Ɋ�Â��؋����W�Ƃ����̂��ł����Ƃ�����̓I�ȗ�͎������ۂ̂Ƃ��땷���Ă���܂���B
�@�ł��̂ŁA�����ł̎�|�́A�Ȃ����p�ł��Ă��Ȃ��̂��A�Ȃ����p�ł��Ă��Ȃ��̂��A�܂����̌������c�_����K�v������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����|�ł������܂��B�ł�����A�@�������肫�ƌ�������͂������܂���B�܂��͌����̋������Ȃƍl���Ă���܂��B
���ɓ��ψ����@�����̈�Ƃ��āA����c�ψ������w�E���������悤�Ȃ��Ƃ�����̂�������܂��A�����͂܂��ʓr�������������Ǝv���܂��B
�@���ɂ������ł��傤���B�ǂ����A���C�шψ��B
�����C�шψ��@�P�����m�F�������Ă������������Ǝv���܂��B
�@��قǁA��R�ψ��̕�����A�ٔ����̏��i���̊W�ŁA���{�̏ꍇ�A�a�����܂߂��ꍇ�S���Ȃ����T���Ƃ������b�̒��ŁA���͔��ɔs�i�I�Ȃ̂�����ǂ��A���z�̑��Q���������܂߂Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E���������܂�������ǂ��A���̔F�����Ă������A�m�I���Y�������̕��œ��v���܂Ƃ߂��ۂɂ́A����������I�Ȃ��́A���邢�͌����̕����ł͂��邪�A�~����������Ƃ����ړI�ői�ה�p���x�̋��z��퍐���x�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����̂ł�����ǂ��A�����͓��v�̒��ɂ͓����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����܂ŏ��i�I�Șa���Ƃ������Ƃł��̂ŁA�ٔ����̕��͐S���J�����Ă���A���̂Ƃ��͐N�Q�Ƃ����O��Řa�������߂܂��̂ŁA�����������z�̘a���Ƃ����̂͏��i�I�a���Ƃ͌���Ȃ��ƔF�����Ă���܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@���ɂ͂�낵���ł��傤���B�����ψ��B
�������ψ��@�m�I���Y����̂��̂܂Ƃ߂ɑ��Ĕ��_����悤�Ȃ��ƂɂȂ��āA�����ȂƎv�����肷��̂ł�����ǂ��A��{�I�ɂ͂��̍l�����Ȃ̂ł��傤����ǂ��A���������|�W�e�B�u�ɂƂ������A������ƃl�K�e�B�u���������̂��������Ȃ��̂��ȂƎv���܂��B
�@���낢��Ȗ��͊m���ɂ���܂����A���Ƀp�e���g�g���[���Ƃ�����������ł��傤����ǂ��A����͑����ƊE�ɂ���čl����������Ă���Ǝv���Ă���̂ł��B�Ⴆ�A���ɐ������[�J�[�ł��g���^�̂Ƃ���͂��Ȃ�e��������Ƃ������A���ɕč��Ő���ɍs���Ă��邱�Ƃ���A�����悤�Ȍ`�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ������Ǝv���̂ł��傤���A���ނƂ����i�Ƃ������A�������Ƃ������A�f�ގY�Ƃł͂���ȂɈႤ�Ƃ����悤�ȃC���[�W�͂Ȃ��̂ł��ˁB���̈Ӗ��Ō����ƁA���낢��Ȍ�ӌ��������Ă��̂悤�ɂȂ����̂��Ǝv���̂ł�����ǂ��A���������|�W�e�B�u�Ȉӌ��������Ă��������ȂƂ����C���������܂��B���炵�܂����B
���ɓ��ψ����@�Q�l�l���炢����������ӌ��܂��āA���ǂ��ł܂��c�_���d�˂�Ƃ������Ƃɂ������Ƒ����܂��B
�@���Ɍ䔭���͂������܂����B�ǂ����A�ψ��B
���ψ��@������Ƃ̗���ŏq�ׂ����Ă��������܂��B������ƂɂƂ��ē����Ƃ��̌o�ό��ʂƂ����̂͑傫�ȊW�ɂ���̂ł��B���ƓI�ɖ��ɗ����Ȃ��悤�ȓ������A������Ƃ͏o���Ȃ��Ǝv���̂ł��ˁB�ł�����A���ł���Ƃ����悤�Ȓ��q�ł͓����͏o���܂���B���i�̕t�����l�����߂�B�Ⴕ���́A�����ɂ���Ĕr���I�Ȍ����ď��i��ۂɍ��������B�����������Ƃɂ���āA�܂��J���ɂ����������ނ��Ƃ��ł���B���������z�̂��߂ɓ������o�肷�邱�Ƃ������Ǝv���̂ł��B
�@���̏ꍇ�A�Ⴆ�ΐN�Q���ꂽ�Ƃ��ɗ]��h�䂪�����Ȃ��ꍇ�ɁA�ٔ�����Ƃ������Ƃ́A������ƂɂƂ��Ă͂ƂĂ���ςȂ��ƂȂ�ł��B������Ƃ��ٔ��ŏ��Ă�A���i���͋ɂ߂ĒႢ�ƕ����Ă���܂����A�܂���قǂ��b������܂����悤�ɁA���ɑi�ׂ����Ă�������̋��z�Ō������Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA������Ƃ��������o���Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ邩�Ǝv���܂��B
�@�ł�����A�Ⴆ�Α��Q���������Ɋւ��Ă�������I�Ȃ��̂�����A���ꂪ���ɂȂ��ĐN�Q����邨���ꂪ�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ������Ƃ��l�����܂��̂ŁA���̕ӂ���z�������������Ȃ���A�������������������Ă���������Ǝv���܂��B
���ɓ��ψ����@�܂��A����ȍ~�̋c�_�̒��ŁA���̓_���������Ă܂��肽���Ǝv���܂��B
�@���ɂ͂������ł��傤���B��낵�イ�������܂����B
�@����̉�͏؋����W�̎葱�ɂȂ�܂����A����ɂ��܂��ẮA�܂�����Ɍ�R�c�������������Ƃɂ������܂��āA�{���̉�����̂�����ŕ������Ƒ����܂����A�Ō�ɒm�������ǒ����瑍�������肢�������Ƒ����܂��B
�������ǒ��@�����́A�Q���Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B�O���̌����̈��萫�͂ЂƂ킽��c�_�����Ă����������̂ŁA�����Ƃ������A�܂Ƃ߂̐������āA����ȍ~�ɒ������Ă������������Ǝv���܂��B
�@����ȍ~�A�����㔼�̋c�_���������܂�������ǂ��A��̓I�ȏ؋����W�A���Q�����̎葱�_�ɓ����Ă��������Ǝv���܂��B
�@�����̋c�_�̈�ۂł�����ǂ��A�ŏ��ɐ\���グ����������Ȃ��̂ł����A���̋c�_�͏�ɗ����̃T�C�h������܂��āA�����̃T�C�h�ɗ����A�퍐�̃T�C�h�ɗ����Ƃ������Ƃ������āA�m���v��ɂ��������̂ł�����ǂ��A��͂肻�̃o�����X���厖�ł���Ƃ����̂��O�낤�Ǝv���܂��B�����A���̂ǂ����̃T�C�h�ɗ����₷�����Ƃ����̂����Ƃƒ�����Ƃł͎�Ⴂ�������āA���Ƃ̒��ł��A��قǔ����ψ�����w�E�̂������悤�ɁA�ꍇ�ɂ���Ă͋Ǝ�ɂ���ĈႢ�����邩������Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B
�@�����A�����āA�����Ă���l�ɑ��ĉ����藧�Ă����Ă�����Ƃ����̂���{�̔��z�ł͂Ȃ����ȂƂ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��̂ŁA����ł����Đ��x�̉^�p�̘b�Ȃ̂��A���邢�͐��x���̂��̘̂b�Ȃ̂��A���ʂ���܂�����ǂ��A���ۍ����Ďg���Ȃ��Ƃ����l���g����悤�ɂ��邽�߂̎藧�ĂŁA�����]����߂���ƁA���������{�m�I���Y����̎w�E�ɂ�����܂�������ǂ��A�g���[���̖��Ƃ����̂�����̂ŁA�����̕��Q�͋N����Ȃ��悤�ɂƂ����K�v�͂������̂ł����A���������o�����X�̒��ōl���Ă����B
�@����ɂ���āA���ǁA�����A�m���Ƃ����̂���̉��l�����������̂ł����āA���̉��l�����ׂ����̂����ĂȂ��Ƃ�����ԂƂ����̂͌��S�ȏ�Ԃł͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA���O�������̉��l�����ׂ����낢��ȍH�v�����Ă��钆�ŁA���{�Ƃ��Ăǂ����邩�Ƃ������Ƃ����ꂩ��葱�_�̒��ōX�ɍl���Ă��������Ǝv���܂��̂ŁA�ǂ�������������낵�����肢�������Ǝv���܂��B
���ɓ��ψ����@���肪�Ƃ��������܂����B
�@�Ō�ɁA����ȍ~�̉�ɂ��Ď����ǂ�����������肢�������܂��B
���k���Q�����@����ȍ~�ɂ��܂��ẮA��S����12��18�����j���̂X������ł��B��T��̉�́A���T24���ؗj����15������ƂȂ��Ă���܂��B�N�����̉�ɂ��܂��ẮA���ꂼ�ꎑ���U�̂Ƃ���ƂȂ��Ă���܂��B
�@�܂��A����������ł��Ȃ������̂ł����A�{���̎����̍Ō�ɁA�����A���P�[�g���ʂ̎b��ł�����z�t�݂̂Ŕz�t�����Ă��������Ă���܂��B�؋����W�̂Ƃ���ł��̂ŁA�܂�����Ɍ�����\���グ�܂�����ǂ��A�Q�l�܂łɔz�t�������Ă��������Ă���܂��B
�@�����ǂ���͈ȏ�ł��B
���ɓ��ψ����@�{���������Ԃɂ킽��܂��āA�M�S�Ȍ�c�_�����肪�Ƃ��������܂����B�ǂ����������낵�����肢�\���グ�܂��B